玉手箱の計数問題のひとつである「四則逆算」について、基本や例題を解説付きで紹介していきます。
問題自体は簡単ですが、対策していないと焦りからミスをしやすい内容です。まずは様々な問題パターンを見ておきましょう。
また、四則逆算の対策ポイントや解く時のコツもあわせて解説しているので、これから対策を始める際には必見です。
目次
玉手箱の計数問題「四則逆算」とは?
四則逆算は、等式の中の空欄に当てはまる数を計算する問題です。計算力だけでなく、処理能力や瞬発力も必要になります。
玉手箱の問題の中でも特に制限時間が厳しく、数秒で計算を終わらせなければなりません。その分、複雑な計算は求められないため、数学に苦手意識があっても高得点を狙うことが可能です。
また、四則逆算が出る受検形式では必ず電卓が使えるため、自信がない計算は電卓に任せることもできます。
四則逆算|例題と解答・解説
例題1
【 】に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。
【選択肢】
A:
B:
C:
D:
E:
解答: B
・・・①
・・・②
①5を左辺に移す( × 5に変わる)
②左から順に電卓で計算する
例題2
【 】に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。
【選択肢】
A:
B:
C:
D:
E:
解答: C
選択肢から数式は割り切れることがわかる。このときは、かけ算をしてから割り算をする。
・・・①
・・・②
・・・③
①20と6を右辺に移す
②割り切れるように、かけ算を先にする
③左から順に電卓で計算する
例題3
【選択肢】
A:
B:
C:
D:
E:
解答: D
・・・①
・・・②
①0.004を右辺に移す
②左から順に電卓で計算する
例題4
【 】に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。
【選択肢】
A:
B:
C:
D:
E:
解答: B
・・・①
・・・②
・・・③
①「の」をかけ算の式にする。%を100で割って少数にする
②0.57を右辺に移す
③右辺を電卓で計算
例題5
【 】に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。
【選択肢】
A:
B:
C:
D:
E:
解答: C
分母が異なる分数の足し算があるので筆算する。
・・・①
・・・②
・・・③
・・・④
・・・⑤
①右辺の分母を18に揃える
②を右辺に移す。は計算しておく
③はにして計算
④はにして計算
⑤約分を忘れない(18と9を9で割り、10と4を2で割る)
四則逆算|計算力以外の対策も重要
計算の基本ルールを再確認
・ ()の中から計算する
・ 「×」 「÷」は「+」 「-」より先に計算
・ 分数の足し引きでは分母を合わせる
・ 分数で割る時は上下を入れ替えて掛け算にする
四則逆算を解く上で、最低限押さえておきたいのが上記4つの計算ルールです。
「()の中から計算」 「掛け算と割り算から計算」は基本の部分で、覚えている人も多いでしょう。しかし、急いで計算していると抜けやすい要素でもあります。
高い頻度で使う計算ルールだからこそ、一度再確認しておくことが重要です。「ちゃんと計算方法を復習した」という意識があるだけでも、問題に集中しやすくなります。
また、意外と忘れている人も多いのが分数の計算方法です。
分数の足し算・引き算では、両方の分母が同じになるように通分する必要があります。この時、分子と分母の両方に同じ数字を掛けないと全く違う答えになってしまいます。例えば「1/2」の分母を4に合わせる場合は、「2/4」にするのが正しい手順です。
分数の掛け算は単純に分子同士と分母同士を掛ければ問題ありません。一方、分数で割る時は「分子と分母を入れ替えてから掛ける」ことが必要です。
分数で割る時は最終的に掛け算として計算することになるという点を必ず押さえておきましょう。
2~3桁までは暗算できるようにする
四則逆算で高い暗算力は必要なく、数字が大きい場合は電卓を使うことも可能です。しかし、最低限の暗算はできた方が時間に余裕が生まれます。
具体的には、2桁までの掛け算・割り算や、3桁までの足し引きは暗算で済ませたい計算量です。電卓に入力するよりも、暗算した方が早く計算できるでしょう。
また、分数や小数の計算も、ある程度までは暗算できた方が時短に繋がります。電卓によっては分数の計算に対応していないこともあるため、対応機種に替えるか、分数の暗算も練習しておきましょう。
電卓の操作に慣れておく
四則逆算では何度も電卓を使うことになります。1問あたりの時間が非常に短いからこそ、電卓の操作時間は1秒でも短くしたいところです。操作に慣れていれば、入力ミスも減らせます。
「電卓の操作に慣れた」といえるのは、「キーを見なくても数字と記号を入力できる」というレベルです。少なくとも、電卓特有の数字の配置には慣れておく必要があるでしょう。
指の感覚で覚えられることもあるので、なるべく実物の電卓を使うことをおすすめします。スマホの電卓機能も便利ですが、画面を良く見ていないと操作ミスが起こりやすいため、適性検査向けではありません。
四則逆算|解くコツは式の変形!
シンプルな等式は移項でOK
・ 移項する時は正負(+-)を反転する
・ 掛かっている数字を消す時は、その数字で両辺を割る
四則逆算の問題の多くは、「〇+□=△÷●」といったシンプルな等式です。このタイプの問題は、移項と両辺への掛け算・割り算を使って式を整理することで、簡単に計算することができます。
移項できるのは「+10」や「-2」といった、「正負の記号+数字」の一塊のみです。先頭の数字は、正の数である場合は記号が省略されますが、問題なく移項できます。
一方、空欄に数字が掛かっている「3□」のような項について、「3」だけを片方の辺へ移動することはできません。この場合は、両辺の全ての数字を「空欄に掛かっている数」で割る必要があります。
%の問題は書き換えが必要
◆ の
→
→
◆ の
→
→
※をにした値をとして計算すると、
という形で途中式をシンプルにもできます。
%が使われる問題は、書き換えて式をわかりやすくしましょう。空欄に対して何%か表している問題と、空欄自体が%を表している問題の2パターンがあります。
「 【 】の30%」のような問題では、30%の部分を「0.3」に変えると、「 【 】×0.3」という式にすることができます。その後、両辺を0.3で割ることで空欄部分の数字が求められます。
%を変形した数字で両辺を割ることになるので、小数ではなく分数として「3/10」と書き換えても良いでしょう。この場合は割るというよりも、「10/3を掛ける」という形になります。
一方、「70の【 】%」のように、割合が空欄になっている問題もあります。%が不明な場合は「 【 】/100」と表すことができるため、「70×【 】/100」という式に変形できます。
ただし、そのままだと計算がわかりにくくなることもあるので、最初から「 【 】の1/100を□とおく」ことも有効です。この場合は「70×□」と、よりシンプルな式にできます。最後は、求めた□に100を掛ければ、本来の答えである空欄の数値が求められます。
悩まず1問10秒で済ませよう
四則逆算では、50問を9分で解くことになります。1問あたりの時間は10秒程度しかないため、検算したり答えに悩んだりしている時間はありません。
基本的に一度答えを出したらそのまま進み、選択肢と合致する結果が出なくても近いものを選んで先に進みましょう。もし計算ミスに気付いたとしても、計算をやり直す余裕はほとんどありません。
最も避けたい事態は、答えに悩んで未解答のまま時間切れになってしまうことです。玉手箱では、未解答と誤答はどちらも不正解として扱われます。未解答のまま進めてしまうと、「たまたま当たった」ということが起こらなくなってしまいます。
選択肢は全て5択になっているため、「最悪でも20%で当たる」という意識で迷わず選ぶようにしましょう。

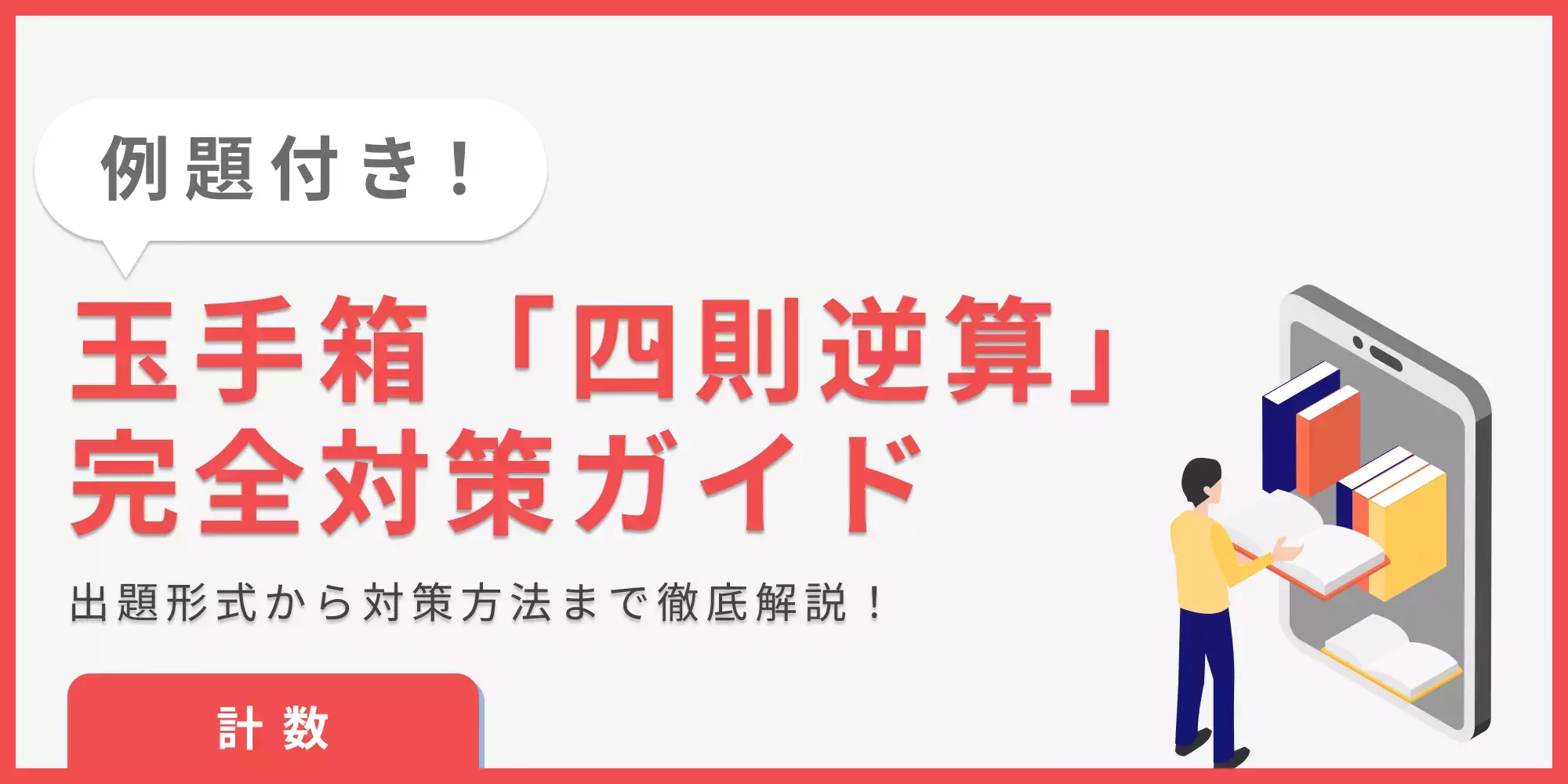


.webp)
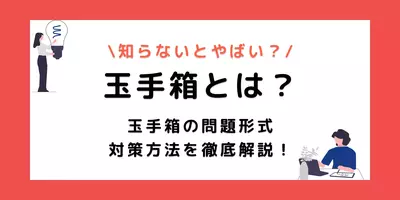
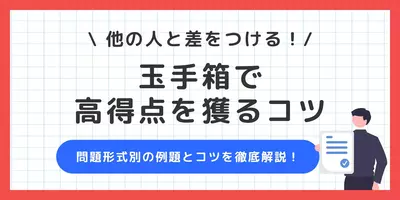
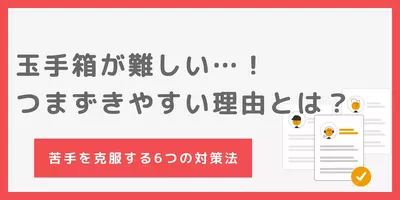
.webp)