玉手箱の言語は、必ず長文読解が出る特徴的な問題です。3種類に分かれており、どれも似たように見える内容になっています。
しかし、実は種類によって解き方や時間配分に大きな差があるため、違いを知っておくことが重要です。
まずは言語問題の基本を押さえ、さらに種類別の解き方や対策法を理解していきましょう。
目次
玉手箱の言語はどんな問題が出る?
| 論理的読解 | ・600字程度の長文1つに4問ずつ出題 ・15分36問または25分52問 ・設問が正しいか3択で答える |
| 趣旨判定 | ・400~600字程度の長文1つに4問ずつ出題 ・10分で32問 ・設問が趣旨に合っているか3択で答える |
| 趣旨把握 | ・1,000字程度の長文1つに1問ずつ出題 ・12分で10問 ・筆者の考えに近い選択肢を4択から答える |
400~1,000字の長文読解のみ
玉手箱の言語では、400~1,000字程度の長文読解をする問題だけが出題されます。難しい単語や熟語の知識は必要とされない反面、語や熟語のと読解力が求められる内容です。
問題は3種類だけであり、内容も似ています。しかし、それぞれ読み取りで注意すべき点や適切なペースが異なるので、一括で対策することは難しいでしょう。
問題ごとに合った対策を行い、どれが出題されても焦らずに解けるようにしておく必要があります。
解答は全て選択式
言語問題は、どれも3~4つの選択肢から選ぶ形式です。記述式の問題がないため、文章作成能力に自信がなくても問題ないでしょう。
論理的読解と趣旨判定では選択肢の内容も固定されています。問題文に対して、「正しい」や「趣旨に合っている」かを3択で判断する内容です。
一方、趣旨把握ではランダムな4択の文章から、筆者の考えに最も近いものを選びます。他の2つに比べて、選択肢の内容まで読み取らなければならないため、特に難しい問題といえます。
時間制限がシビア
玉手箱の言語では、1問あたり1分未満で解いていく必要があります。長文を読むためにも時間がかかるので、実際にはもっと短く感じるでしょう。
長文を素早く読み取ることができないと、その分だけ解答を考える時間も減っていきます。趣旨判定以外は1つの長文に対して4問が出題されるため、数秒の差でも影響は大きいです。
玉手箱では、解き終わらなかった問題は全て不正解として扱われます。もし時間不足で未解答になった問題が多いと、高得点を取るのは厳しくなってしまいます。
問題を正確に解けることに加えて、「素早く読み取って答えられる」ということが重要な科目です。
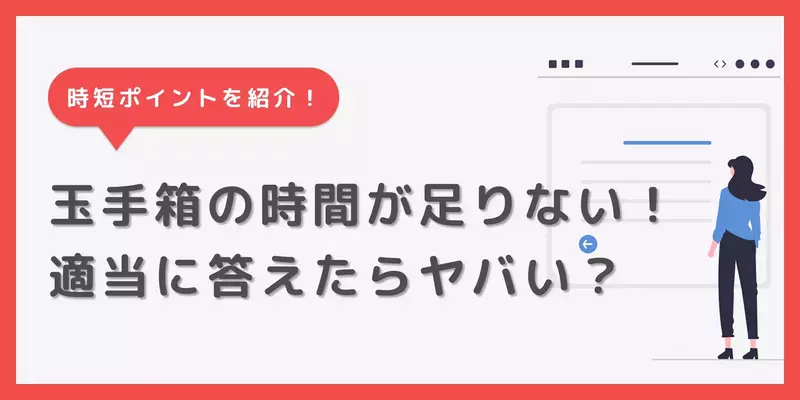
玉手箱の言語問題は3パターン
論理的読解は根拠を明らかにして答える
| 長文 | 問題文と選択肢 |
| ・600文字程度 ・1つの長文に対して4問出題 |
・本文の内容についての記述 ・問題文に対して「正しい」 「間違っている」 「判断できない」を選ぶ |
論理的読解では、600文字程度の長文が出題されます。問題は、本文に関する記述に対して「正しい」 「間違っている」 「判断できない」の3つから選ぶ形式です。
筆者の考えではなく、論理的に正しいかどうかを見極めるものであり、直観的に選ぶことは難しいでしょう。解答の根拠は長文中で示されているため、「どちらかといえば正しい」という感覚で答える問題ではありません。
解答の際は、問題文で問われている 「内容の答え合わせをする」という意識で読むのがコツです。問題文に反する記述があれば「間違っている」、特に言及されていなければ「判断できない」を選びます。
答えが「判断できない」の時は特に苦戦しやすく、無関係な根拠をもとに正誤を無理やり決めてしまいがちです。
また、「長文の中では正しいとされているが、現実には正しくない」という事柄はほとんど出ません。そのため、常識的に考えて答えが明らかな問題は、長文を読むまでもなく解答できる可能性があります。時間がなかったり、どうしても根拠が見つけられない時に役立つテクニックです。
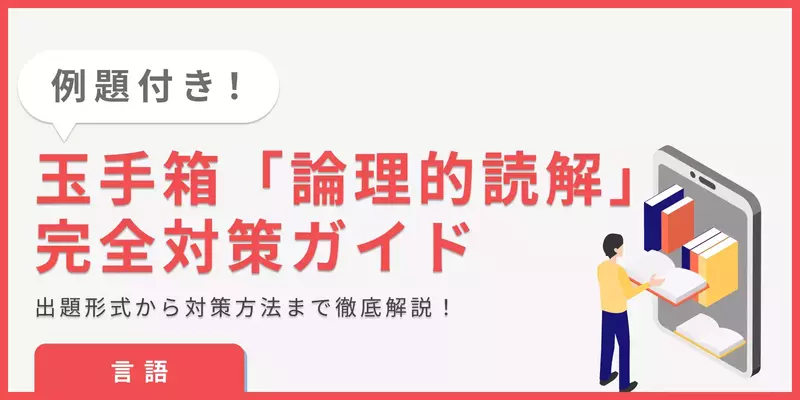
趣旨判定は問題文と本文を比べよう
| 長文 | 問題文と選択肢 |
| ・400~600字程度 ・1つの長文に対して4問出題 |
・筆者の訴えについての記述 ・問題文に対して「筆者が一番訴えたいこと」 「一番訴えたいことではない」 「本文には関係ない」を選ぶ |
趣旨判定は、筆者の主張を読み解く内容です。長文は400~600字程度と比較的短めになっています。
問題文が「筆者が一番訴えたいこと」かどうかを判定する問題であり、現実に正しいかどうかは影響しません。
さらに、「本文に書かれているが、一番訴えたいことではない」という選択肢があるため、単に言及されているだけでは正解がわかりません。長文全体の趣旨を理解した上で、「本題としていること」 「本題の説明のために述べていること」を見分ける必要があります。
解答の際は問題文の内容を踏まえながら、文章全体を流し読みしてみましょう。問題文と関連する内容が続いているなら、「一番訴えたいこと」である可能性が高いです。
逆に、関連する記述が一部にしかなかったり、全く出てこないようであれば「一番訴えたいことではない」 「本文には関係ない」だとわかります。
長文を一通り読んでから問題文を見ていると、どれもそれらしい主張に見えてしまいがちです。問題文を先に読み、長文と照らし合わせることで正しい判断ができるでしょう。
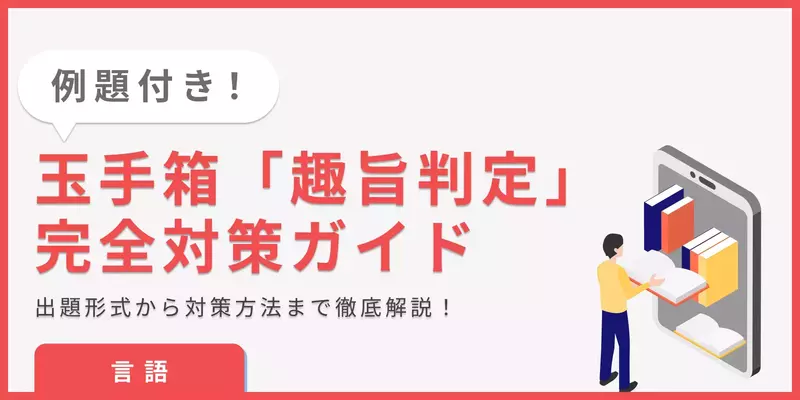
趣旨把握では接続詞がカギ
| 長文 | 問題文と選択肢 |
| ・1000字程度 ・1つの長文に対して1問出題 |
・筆者の考えに最も近いものを1つ選ぶ ・選択肢は「長文に関する文章」が4つ |
趣旨把握では、言語の中では最も長い1000字程度の長文が出題されます。問題は1つの長文に対して1問だけであり、時間に余裕がある問題に見えるかもしれません。
しかし、選択肢が長文の内容によって毎回変わるため、しっかり時間をかけて本文の読み取りをする必要があります。他の問題と同じ感覚で読むと、「言及だけはされている」といった紛らわしい選択肢に引っかかってしまいます。
筆者の考えを効率良く読み取るには、「特に」 「しかし」といった接続詞に注目してみましょう。目につきやすい接続詞の後には、本文の趣旨となる内容が含まれていることが多いです。
また、段落ごとに内容を要約してみるのも良いでしょう。それぞれの段落で共通したテーマが見つかれば、筆者の主張に一気に近付くことができます。
趣旨把握は問題数が少ないため、1問あたりの価値が高い単元です。なるべく正答率を高めるために、長文の読み取りには多めに時間を割くのがおすすめです。
【例題を見る】玉手箱の言語問題
論理的読解
現代社会において、「移動」という概念は大きく変容しつつある。かつて人々の移動は、主に物理的な場所の変更を意味していた。しかし、インターネットの普及により、私たちは物理的な移動を伴わずに、異なる文化や社会と接触できるようになった。この「仮想的な移動」は、従来の移動概念を根本的に覆すものである。
興味深いのは、この仮想的な移動の増加が、実際の物理的な移動にも影響を与えていることだ。たとえば、海外旅行の形態が変化している。以前の旅行者は、現地で初めて異文化に触れ、それを「発見」していった。しかし現在では、インターネットで事前に詳細な情報を得た上で旅行に出かける。そのため、旅行者の多くは「予習済み」の体験を確認するような旅をしている。
一方で、このような仮想的な移動の普及は、新たな問題も生んでいる。情報技術の発達により、私たちは世界中の出来事をリアルタイムで知ることができる。しかし、それは必ずしも深い理解や共感につながっているわけではない。むしろ、安易な理解や偏見を助長する可能性すらある。実際の体験を伴わない知識は、ときとして表面的な理解にとどまってしまうのだ。
【選択肢(共通)】
A: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。
B: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。
C: 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。
【問題】
(1)現代の海外旅行者は、インターネットで得た知識をもとに、その正誤を確かめるような旅をする傾向がある。
(2)仮想的な移動の普及により、物理的な移動の必要性はなくなった。
(3)インターネットを通じた異文化理解は、偏見をなくすことにつながっている。
(4)情報技術の発達により、人々は世界の出来事をリアルタイムで知ることができるようになった。
(1)解答:A
2段落目で、現代の旅行者は「インターネットで事前に詳細な情報を得た上で旅行に出かける」 「 『予習済み』の体験を確認するような旅をしている」と明確に述べられている。設問文は正しい。
(2)解答:B
本文では、仮想的な移動が増加していることは述べられているが、物理的な移動がなくなったとは述べていない。むしろ、仮想的な移動が物理的な移動に影響を与えているという記述があり、両者が共存していることが示唆されている。設問文は間違い。
(3)解答:C
3段落目では、仮想的な移動が「安易な理解や偏見を助長する可能性すらある」と述べているが、実際に偏見をなくしているかどうかについては言及されていない。設問文の正誤は判断できない。
3段落目で「情報技術の発達により、私たちは世界中の出来事をリアルタイムで知ることができる」と明確に述べられている。設問文は正しい。
趣旨判定
次の文章を読み、設問文についてそれぞれA・B・Cのいずれであるか判断して答えなさい。なお、設問文には、AとCに該当するものが必ず1つ以上含まれています。
【面接での質問に向き合う姿勢】
就職活動の面接では、答えにくい質問が投げかけられることがある。「あなたの人生において最も大切なものは何ですか」といった、シンプルながら深い答えを求められる質問だ。このような場合、すぐに答えるのは避け、いったんその質問の意図を考えるべきだ。
即答してしまうと、質問の背景にある面接官の意図を汲み取れない可能性がある。逆に、質問の背景を探るために「この質問はどのような状況を想定しているのでしょうか」といった逆質問をするのは有効だ。たとえば、「家族との時間を優先したいと考える一方で、仕事上の大きなプロジェクトにも関わりたい場合、どのような選択をするか」といった具体的な状況を引き出すことができるだろう。
このような逆質問は、対話を深めるきっかけとなり、面接官に対して「考える力」や「柔軟な対応力」をアピールする機会にもなる。また、面接官はこうした対話の中で学生の価値観や思考の柔軟性を見ている。
質問の意図がつかめないときや、答えに詰まったときには、曖昧な回答で終わらせるのではなく、逆質問をして条件を具体的に絞りながら対話を続けていくことが重要だ。それが、よりよい印象を与えるコツでもある。
【選択肢(共通)】
A: 筆者が一番訴えたいこと(趣旨)が述べられている。
B:本文に書かれているが、一番訴えたいことではない。
C: この本文とは関係ないことが書かれている。
【問題】
(1)面接で逆質問を活用することで対話を深めることが重要である。
(2)面接では、即答が求められる場合があるため、素早い判断力を鍛える必要がある。
(3)面接での逆質問は、面接官が学生の人間性や柔軟さを評価するために重要な手段である。
(4)逆質問を使うことで面接官に良い印象を与えることができる。
(1)解答:A
3段落目で、面接官との対話を深めるために、こちらから逆に質問をすることをすすめている。また、4段落目で、「逆質問をして対話を続けていくことが重要だ」と強調している。設問文は本文の趣旨。
(2)解答:C
本文では即答を避ける重要性について述べられているため、「即答が求められる場合がある」という内容は本文とは関係ない。
(3)解答:B
3段落目で、面接官が逆質問などを通した対話の中で学生の価値観や思考の柔軟性を見ていることが述べられている。しかし、これは本文の主張の補足的な内容である。
(4)解答:B
4段落目で、逆質問を用いて対話を続けることがより良い印象を与えるコツであると述べられているが、趣旨は面接官との対話を深めることの重要性であり、逆質問を使うだけで良い印象を与えられるわけではないため、趣旨ではない。
趣旨把握
次の文章を読んで、筆者の訴えに最も近いものを選択肢の中から1つ選びなさい。
現代社会において、環境問題は深刻な懸念事項の一つとなっています。気候変動、資源の過剰消費、生態系の破壊など、さまざまな環境上の課題が私たちの地球に影響を及ぼしています。これらの問題に対処し、持続可能な未来を構築するために、私たちの生活様式や価値観を見直す必要があります。
一つの重要なテーマは、持続可能な生活への移行です。これは、資源の有効利用、廃棄物の削減、エネルギーの効率的な使用などを含む、地球にやさしい方法での生活を指します。例えば、再利用可能な製品の使用や、公共交通機関の利用を増やすことは、環境に対する負荷を軽減する方法の一部です。また、エネルギー源の選択も重要で、再生可能エネルギーへの移行が二酸化炭素排出の削減につながります。
持続可能な生活への移行は、個人とコミュニティのレベルで始まります。一人ひとりの選択や行動が、大規模な変化につながります。エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの導入は、家庭や企業での取り組みが重要です。また、廃棄物削減のためのリサイクルやコンポストの活用も、個人の貢献が大きな影響を持ちます。
しかしながら、持続可能な生活への移行は容易ではありません。多くの場合、環境にやさしい選択は経済的に負担がかかることもあり、生活様式の変更には課題が伴います。また、環境に配慮した製品やサービスがまだ普及していない地域もあります。そのため、政府、企業、個人の協力が必要です。
さらに、持続可能な生活への移行は単なる環境への配慮だけでは不十分です。社会的な公正や経済的な均衡も考慮する必要があります。持続可能な未来は、環境的な側面だけでなく、社会的な側面も含めて総合的に考えるべきです。例えば、環境に配慮した取り組みが社会的な不平等を助長することは避けるべきです。
総括すると、持続可能な生活への移行は地球環境の保護と未来の世代への責任を意味します。これは私たちの生活様式や価値観の見直しを要求し、地球と共に調和した未来を築くための重要なステップです。個人、コミュニティ、政府、企業の協力によって、持続可能な未来への道を切り開くことができるでしょう。
【選択肢】
A: 持続可能な未来を築くために、私たちは生活様式や価値観を見直し、地球環境の保護に貢献すべき。
B: 持続可能な生活への移行は経済的な負担をかけない。
C: 廃棄物削減のためのリサイクルは個人の貢献がほとんど影響しない。
言語対策の基本は「なるべく長文を読まない」
問題文と選択肢の確認が最優先!
玉手箱の言語では先に長文が提示されますが、そのまま長文から読み始めるのは効率が悪いです。先に問題文や選択肢を確認して、「そもそも何についての長文なのか」を掴んでから読み始めることを優先しましょう。
問題文や選択肢から特徴的が語句を見つければ、それに関連する文章だけを読んで解答することも可能です。
また、長文を読むまでもなく「明らかにこれが答えだろう」という問題は、先に答えを選んでおくこともできます。確実な解き方ではないため、他の問題を解いて時間が余った時に改めて考えてみると良いでしょう。
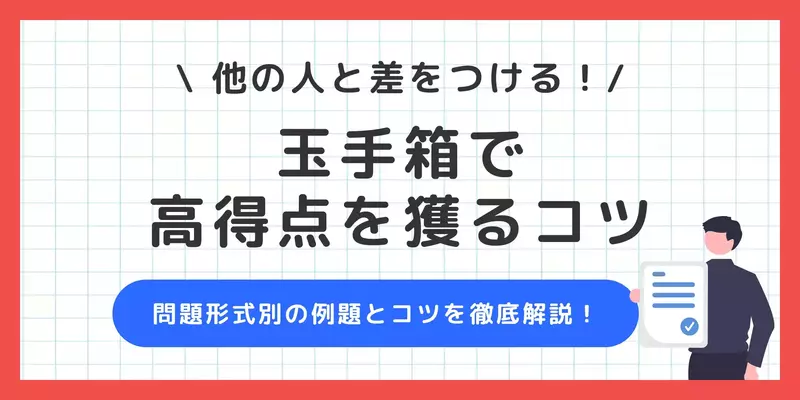
解答に必要な記述だけを探す
言語で出題される長文を隅々まで読み込む必要はありません。ほとんどの問題は1~2行の記述を根拠にして解答できるので、長文の半分近くは「読まなくても答えられる文章」といえます。
読む文章量を減らすことができれば、その分だけ解答時間に余裕が生まれます。読み取り速度に自信がなくても、読むべき文章だけを拾っていけば時間に間に合うでしょう。
言語は時間制限が厳しく、少しでも答えを考える時間を増やしたい科目です。長文の読み取りを手短に済ませることは、正答率の向上にも繋がります。
1問にかけられる時間が種類によって違う
| 問題の種類 | 時間配分の目安 |
| 論理的読解 | 1問30秒/長文1つに2分 |
| 趣旨判定 | 1問20秒/長文1つに1分20秒 |
| 趣旨把握 | 1問に60秒 |
言語の問題は、種類によって適切な時間配分が異なります。1問あたりにかけられる時間は20秒~60秒程度と幅があり、全部に同じような取り組み方をするのは危険です。
例えば、論理的把握では1問30秒が目安ですが、正確には「1つの長文に対する4問を2分」で解くことになります。1問ごとに長文読解と思考にかける時間の割合を決めても、内容によって偏りが出るものです。
そのため、時間配分は長文1つごとに決めるようにしましょう。論理的読解の例では、「読み取りに1分、答えを考えるのに1問15秒ずつ」というイメージの方が、実際の解き方に近くなります。
.webp)
速読力は日常生活で鍛える
言語で重要となる速読力は、いざ勉強で鍛えようとしても中々備わらない能力です。単純な慣れが必要となるので、「日常生活で色々な文章に触れる習慣」を作るのが最大の対策といえます。
読む文章はどんなものでも構いませんが、玉手箱で出る長文は堅めの表現が多いです。政治・経済系のニュース記事や新聞記事を読んでみると良いでしょう。
その際、大まかな文字数と読了までの時間も計ってみると、より効果が出やすいです。
ネットのニュース記事の多くは、玉手箱の言語に近い文字数になっています。こうした記事の概要を、1分程度で掴めるようになれば速読力は十分といえます。
わからなくても正答率を上げられるテクニック
ここまで言語の対策法を紹介しましたが、全て実践しても必ず正解できるとは限りません。時間が足りなかったり、答えに自信がなかったりする時には、勘で答えることになります。
言語の問題は全て3~4択の選択式であり、適当に答えても正解する確率は25~33%程度が期待できます。しかし、適当に選ぶ前に「消去法」で絞っておくと、確率をさらに上げられます。
例えば、趣旨判定で「文中には出てるけど、筆者の一番の訴えか判断できない」という問題があった時は、まず「本文には関係ない」を除外してみましょう。これによって2択まで絞り込めるので、正解できる確率は50%になります。
また、時間が足りなくて長文を読み切れない時でも、「普通に考えて絶対に違う」という選択肢だけを除いておくだけで、確率は大きく上がります。
玉手箱では、誤答も未解答も同じく「不正解」として扱われます。確実に点を落とす未解答よりも、正解する可能性がある適当な解答の方が、良い結果に繋がるのです。
.webp)

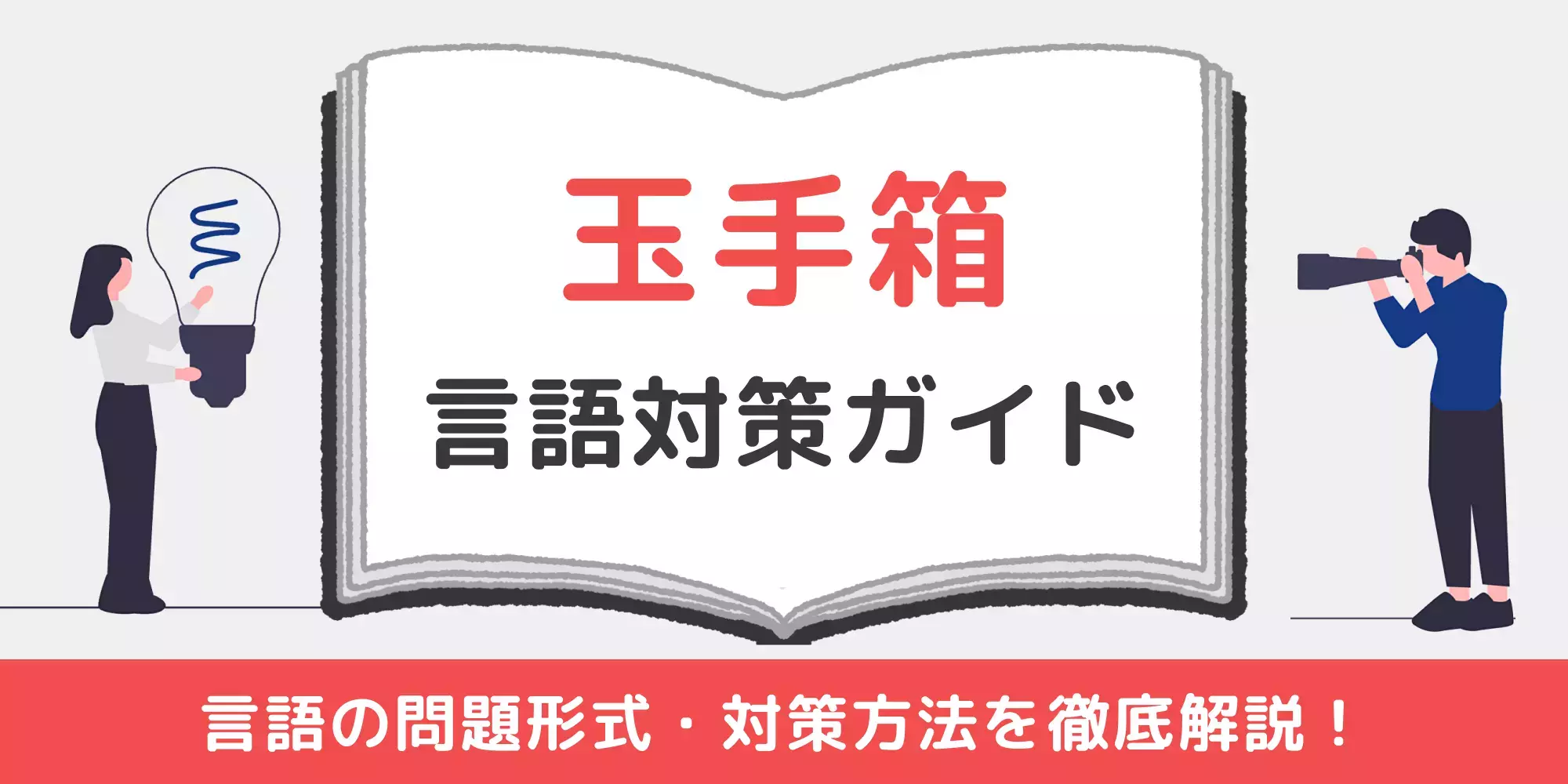


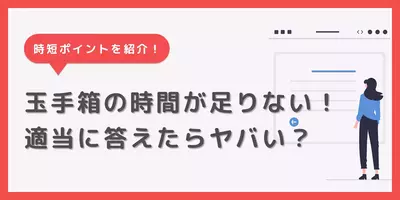
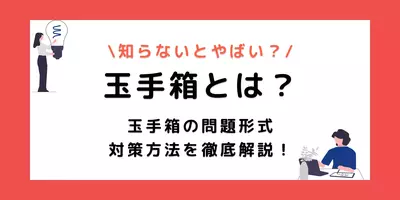
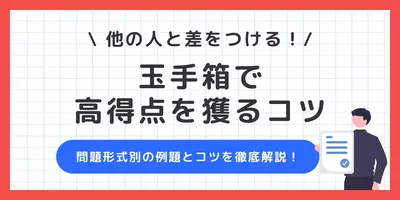
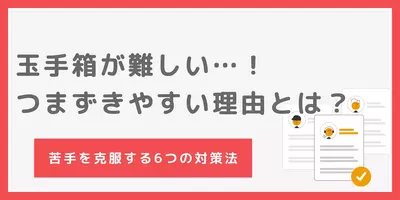
.webp)