玉手箱の言語科目で出る「趣旨判定」は、長文読解をする選択式の問題です。
言語の中では特に時間制限が厳しめであり、適切な読み取り方を知らないと得点を落としやすい形式になっています。
まずは問題の基本事項を掴んでおき、解説付きの例題で形式に慣れていきましょう。趣旨判定に合った長文読解の練習方法や、効率的に解く手順も紹介しています。
目次
玉手箱の言語問題「趣旨判定」とは?
趣旨判定は、400~600字程度の長文から「筆者が一番訴えたいこと」を読み取る問題です。同じテーマでも筆者によって趣旨や結論が異なるため、しっかり読まなければ判断しにくい内容が出題されます。
問題では、長文についての記述に対して、「筆者が一番訴えたいこと」 「一番訴えたいことではない」 「本文とは関係ない」の3択で答えます。この選択肢は毎回固定のため、覚えていれば見る必要はありません。
出題形式は10分で32問ですが、1の長文ごとに4問ずつ出題されるため、実際は「10分で長文8個」という理解の方が正確でしょう。
内容はビジネスに関するものが多く、社会人になる上での一般常識も試されているといえます。
特別な知識は必要ありませんが、長文読解の速度と精度が求められます。時間制限もシビアに設定されているため、事前対策なしでは高得点を狙うのは厳しいでしょう。
趣旨判定|例題と解答・解説
例題1
次の文章を読み、設問文についてそれぞれA・B・Cのいずれであるか判断して答えなさい。なお、設問文には、AとCに該当するものが必ず1つ以上含まれています。
【重要な説明の途中で】
最近の学生の面接で気になる場面があった。丁寧に説明していた会社の事業内容の途中で、学生がスマートフォンを取り出し、メモを取り始めたのである。確かに、熱心にメモを取る姿勢は評価できる。しかし、説明の流れは止まってしまい、私の話は中断を余儀なくされた。
スマートフォンでメモを取ることは今や当たり前になっている。学生たちにとって、スマートフォンは最も使い慣れたツールだ。だが、面接という場で、突然スマートフォンを取り出すことは適切だろうか。画面に目を落として入力している間、面接官との目線は合わない。説明の要点を聞き逃す可能性すらある。
面接の場で重要なのは、相手の話をしっかりと聞き、理解することだ。メモを取ることに気を取られて、肝心の説明内容を理解できないのでは本末転倒である。また、スマートフォンを取り出す行為自体が、説明を遮る形になってしまうことにも注意が必要だ。
もし説明内容をメモしたいのであれば、面接開始時に「メモを取らせていただいてもよろしいでしょうか」と確認するのが望ましい。そして、従来どおりのメモ帳とペンを用意しておくことをお勧めする。手書きであれば、画面を見つめる必要もなく、相手の表情や仕草も自然と目に入ってくる。これも面接での大切な情報源となるはずだ。
【選択肢(共通)】
A: 筆者が一番訴えたいこと(趣旨)が述べられている。
B: 本文に書かれているが、一番訴えたいことではない。
C: この本文とは関係ないことが書かれている。
【問題】
(1)面接では、説明内容を正確に記録するために、スマートフォンでメモを取るべきだ。
(2)面接開始時に、メモを取ることの許可を得ておくとよい。
(3)学生は、会社の事業内容について事前に十分な知識を持っておく必要がある。
(4)説明を聞くことに集中し、内容を理解することが面接では重要である。
(1)解答:C
本文は、面接における説明を聞く姿勢の重要性について述べた文章で、スマートフォンでのメモ取りが説明の理解や面接官とのコミュニケーションの妨げになる可能性を指摘している。スマートフォンでメモを取るべきだという主張は本文の内容と異なる。
(2)解答:B
4段落目で、メモを取る場合は「面接開始時に『メモを取らせていただいてもよろしいでしょうか』と確認するのが望ましい」と述べられているが、これは本文の主張の補足的な内容である。
(3)解答:C
本文では、会社の事業内容についての事前知識の必要性については触れられていない。
(4)解答:A
3段落目で「面接の場で重要なのは、相手の話をしっかりと聞き、理解することだ」と明確に述べられている。また、「メモを取ることに気を取られて、肝心の説明内容を理解できないのでは本末転倒である」とも指摘されており、これが本文の趣旨である。
例題2
次の文章を読み、設問文についてそれぞれA・B・Cのいずれであるか判断して答えなさい。なお、設問文には、AとCに該当するものが必ず1つ以上含まれています。
【インターンシップ】
就職活動において、「インターンシップ」は今や欠かせない経験となっている。多くの学生が参加するこの制度だが、果たしてその本当の意味を理解しているだろうか。単なる企業見学や、将来の職場の雰囲気を知るためだけのものではない。
インターンシップの最大の目的は、実際の仕事を通じて自分自身を知ることにある。与えられた課題に取り組み、チームで働く中で、自分の強みや弱み、適性を理解することが重要だ。机上の空論ではなく、リアルな職場体験を通じて、自分に合う仕事や企業文化を見極めることができる。
ただし、安易に人気企業や知名度の高い企業のインターンシップを選ぶのは賢明ではない。自分のキャリアビジョンや興味、学びたいことに合致する企業を選ぶことが何より大切だ。単なる履歴書の飾りや、友人に自慢できる経験としてではなく、自己成長の機会として捉えるべきである。
インターンシップは、就職活動の通過点ではない。むしろ、自分の未来を考える重要な学びの場なのだ。真摯に向き合い、積極的に学び、自分自身と向き合う姿勢が求められる。企業は、与えられた課題をこなすだけでなく、どれだけ主体的に考え、行動できるかを評価している。
【選択肢(共通)】
A: 筆者が一番訴えたいこと(趣旨)が述べられている。
B: 本文に書かれているが、一番訴えたいことではない。
C: この本文とは関係ないことが書かれている。
【問題】
(1)インターンシップでは、事前に企業について十分に調べておくべきである。
(2)インターンシップの目的は、企業の雰囲気を知ることである。
(3)インターンシップは、自己成長のための重要な学びの場である。
(4)人気企業のインターンシップを安易に選ぶのは得策ではない。
(1)解答:C
本文では、事前に企業について調べることについては述べられていない。
(2)解答:B
本文の1段落目で、インターンシップは「単なる企業見学や、将来の職場の雰囲気を知るためだけのものではない」と明確に述べられている。本文に書かれているが、最も訴えたいことではない。
(3)解答:A
本文全体を通して、インターンシップを「自己成長の機会」「未来を考える重要な学びの場」と繰り返し強調している。これが本文の最も訴えたい趣旨である。
(4)解答:B
3段落目で、「安易に人気企業や知名度の高い企業のインターンシップを選ぶのは賢明ではない」と述べられている。しかしこれは、本文の主張の補足的な内容である。
趣旨判定|長文読解の練習になる文章はある?
筆者の主張がよく見えるコラム系
- ・ コラム
- ・ エッセイ
- ・ 社説
- ・ 高品質なブログ
趣旨判定は「筆者の訴え」を読み取る問題です。文中で主張しているということが重要であり、現実に正しいかどうかは答えに影響しません。
そのため、筆者の訴えが強く表れる「コラム」 「エッセイ」 「社説」のような文章をいくつも読んでみると、良い練習になります。事実だけを述べる解説系の文章や、ニュース記事には筆者の主張が含まれにくいです。練習用の文章としては使いにくいでしょう。
コラム系の文章はブログなどでも見ることができますが、書籍や新聞として「商品」になっている文章と比べると、読みにくいことも多いです。信頼できる組織の高品質なブログに絞った方が良いでしょう。
読みやすい文章でなければ、「趣旨を読み取る」以外に余計な手間がかかってしまいます。なるべく書籍や新聞レベルの文章を使うようにしましょう。
600字程度を30~40秒で読み切りたい
趣旨判定で出る400~600字程度の文章は、30~40秒で読み切れると時間に余裕が持てます。通常は1分~2分かけて読む文章量ですが、問題を解くために隅々まで読み取る必要はありません。
最終的に趣旨が理解できればいいので、要点だけに目を通しながら流し読みする感覚であれば、30~40秒でも十分に読み切ることができます。
また、実際に出題される長文には、解答に関係しない文章も多く含まれます。問題文と関係ないと思った記述は飛ばすことができるため、より短い時間で終わらせられることもあるでしょう。
練習段階では40秒を多少オーバーしてもいいので、「時間内に読み切れる」という感覚を掴んでおくことが重要です。
段落ごとに内容をまとめる癖を付けよう
文章全体を一度に要約するのは難しく、結論が出せないまま時間切れになってしまう可能性もあります。そこで、先に段落ごとの趣旨を整理しておけば、無理なく全体の趣旨を理解することができます。
こうした読み取り方は日常生活で行うものではないので、実際に試しておくようにしましょう。
この練習に使う文章は、問題に合った600字程度のものでなくても構いません。100~200字程度で段落が区切られていれば似たような感覚で要約できます。
趣旨判定|解く手順で効率は大きく変わる!
- 1. 先に問題文を読む
- 2. 長文の目立つ部分から主張を拾う
- 3. AかCを最低1個ずつ選んでおく
まずは問題文をチェック
長文を読む前に、まず問題文を確認しておきましょう。問題文から特徴的な語句を抜き出し、長文から関連する記述を探す形で読解を進めれば、余計な文章を飛ばしやすくなります。
この時、単に一致する語句を探すだけでは、中々答えを断定できないこともあります。答えが「一番訴えたいことではない」か「本文とは関係ないこと」だった場合、問題文と一致する記述はないかもしれません。
問題文が長文の趣旨でなければ、次は「言及はされているか」 「一切記述がないか」と順番に選択肢を絞り込んでいきます。
また、明らかに本文の趣旨と正反対のような問題文は、読むまでもなく「関係ないこと」が答えだと推測できます。「反対」と「無関係」と区別する選択肢がないために使えるテクニックです。
接続詞や段落区切りの前後に注目
文章構造として、筆者の主張が表れやすいのは「したがって」 「しかしながら」といった目立つ接続詞や、段落の区切りの前後です。
目立ちにくい部分に主張を置くという執筆方法は一般的ではないため、「自然と目につきやすい場所」には趣旨が含まれている可能性が高いです。
この読み方では要所だけを拾っていくことができるため、ただ文章の頭から読んでいくよりも大幅な時短が期待できます。ただし、他の箇所に重要な記述があった場合に見逃しやすいというデメリットも理解しなければなりません。
制限時間とのバランスを考えて、「普通に読む」 「要所だけを拾う」という2つの読み方を適切に使い分けることが大切です。
4問中で必ず使う選択肢は2つ
趣旨把握では、「4問の中で、A(一番訴えたいこと)またはC(本文とは関係ないこと)がそれぞれ1つ以上正解になる」という共通の条件が与えられます。
言い換えれば、「AかCがそれぞれ一度も選ばれない長文は無い」ということです。一方、Bの「一番訴えたいことではない」が一度も正解にならないケースは存在します。
そのため、AかCを1つも選ばず4問が終わった場合は、どれか1つの解答を足りない方に変更することが有効です。「自信がなくBと答えた」といった問題があれば、優先的に変えてみると良いでしょう。
「筆者の主張」と「実際に正しいか」は別
趣旨把握における「筆者が一番訴えたいこと」が、必ずしも実際に正しいことだとは限りません。未確定の風説や、人によって答えが変わるようなことが趣旨になっていることも多いです。
そのため、客観的な正しさや自分の感覚とは異なる意見が「筆者が一番訴えたいこと」として正解になっていることがあります。本文の記述を無視して、「現実的に考えてこうだろう」と間違った選択肢を選ばないよう注意が必要です。
読解を進める際は、自分の価値観では判断せずに、あくまで筆者がどう考えているかだけに集中しましょう。
読解には多めに時間を割く
趣旨把握で長文1つに使える時間は1分程度で、1問あたり20秒弱しか割り振れません。しかし、関係する記述さえ見つかればすぐに解答はできるので、長文読解に半分以上の時間を割いても問題ありません。
考えるだけでなく、入力するためにも数秒はかかるものの、少なくとも1問10秒以上は読解に使うことができます。
また、4問分の内容を踏まえて一気に読解をすることで、途切れずに内容を追いかけることもできるでしょう。どちらの解き方が合っているかは練習で確認する必要がありますが、読解の時間重視という方針は共通です。
本番は時間の厳しさから焦ってしまいがちですが、時間が短い前提で練習していれば焦りも少なくなるでしょう。

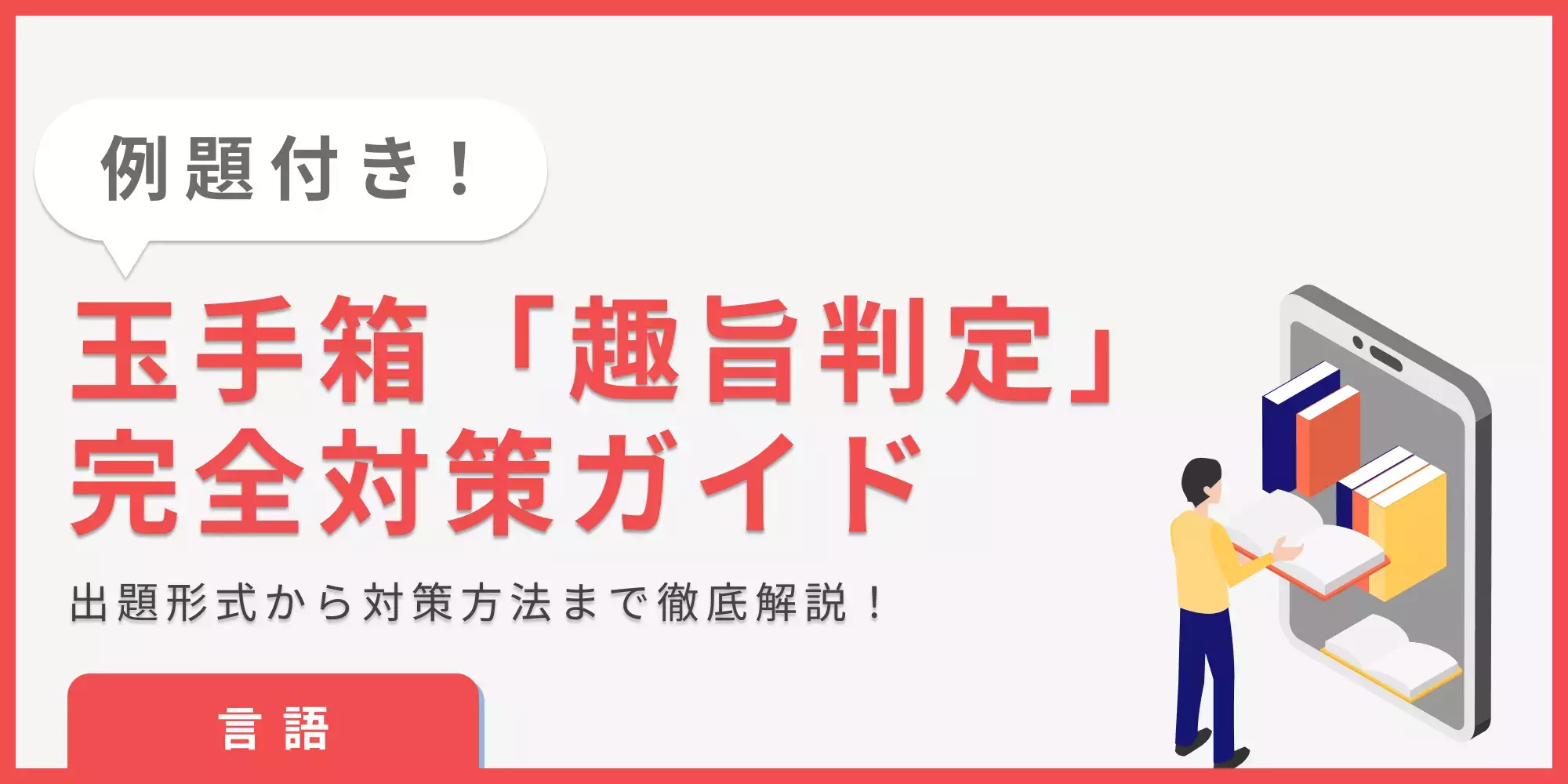


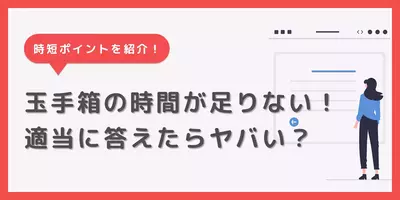
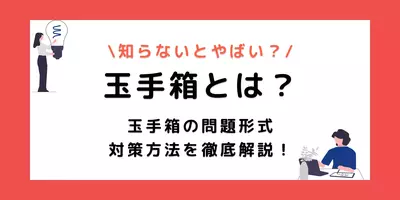
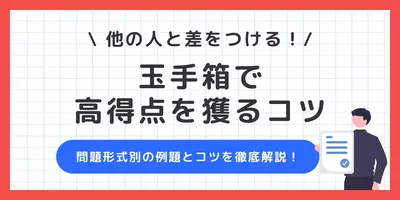
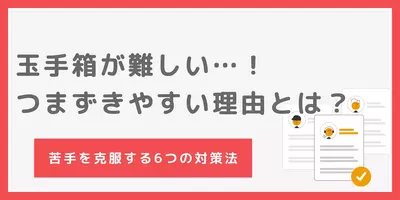
.webp)