玉手箱は時間制限が厳しい適性検査です。他の適性検査と同じ感覚で解いていると、簡単に時間切れになってしまいます。
この記事では、玉手箱の時間が短いと感じる理由や、科目別の時間配分の例を解説していきます。
さらに、時間不足になる原因や対策法に加え、時間内に解くためのコツも紹介しています。本番のペースに慣れたい人へ向け、おすすめの模試サービスも取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
玉手箱の時間制限が短いと感じるのはなぜ?
玉手箱の実施時間の例
| 出題内容 | 実施時間 |
| 言語(趣旨判定)/32問 計数(四則逆算)/50問 性格(パーソナリティ)/68問 |
10分 9分 20分 合計:39分 |
| 言語(論理的読解)/32問 英語(長文読解)/24問 性格(パーソナリティ)/68問 |
15分 10分 20分 合計:45分 |
| 計数(表の空欄の推測)/20問 性格(意欲)/36問 |
20分 15分 合計:35分 |
| 言語(論理的読解)/24問 計数(図表の読み取り)/29問 英語(論理的読解)/24問 性格(意欲)/36問 ※テストセンター形式 |
15分 15分 10分 15分 合計:55分 |
玉手箱の実施時間は、企業が出題する問題によって異なります。通常は40~60分程度が目安ですが、さらに短いこともあるでしょう。
1つの科目ごとの制限時間は短めで、例えば計数の四則逆算では50問を9分で解かなければなりません。そのため、代表的な適性検査のSPIと比べると、全体的に短時間で終わる傾向があります。
ただし、玉手箱は科目ごとに検査が区切られるため、合計の実施時間が短くとも解答に影響はありません。

問題数に対して時間が短い
玉手箱の問題は、基本的に1問あたり1分程度で解かなければなりません。とにかく進行スピードが早く、集中力が欠けて1問に時間を使いすぎると、その後の問題全てに影響してしまうのが特徴です。
さらに、解答画面では常にタイマーが表示されており、残り時間が気になって焦ってしまいがちです。
勉強している時は制限時間がないため、こうした焦りを感じることはないでしょう。しかし、本番では時間に追われることになり、普段とは違った集中力が求められる点に注意が必要です。
1問ごとに時間がかかりやすい
短時間で解ける問題は計数の「四則逆算」のみで、他の問題は長文や図表をしっかり読む必要があります。
長文と図表問題はそれなりにボリュームのある内容で、解答を考える時間よりも問題を読み取る時間の方が長くなりやすいです。
そのため、単純な知識量や計算力だけでは良い結果を出すことができません。速読力や分析力も鍛えなければならない点が、玉手箱で時間不足を感じる最大の原因といえるでしょう。
対策不足だと難易度が高い
玉手箱は、解き方のパターンを把握していないと苦戦する問題が多いです。内容は中学・高校レベルの知識で対応可能ですが、形式に慣れていないとスムーズに解けません。
特に、計数は苦手とする人も多い問題です。図表を使う問題は、数的処理の能力が求められる独特な内容になっています。大学受験の数学とは異なる視点が必要であり、「数学は得意」という人でも対策は必須です。
全体的に他の適性検査の知識が活かせない問題も多いため、玉手箱独自の対策が求められます。

【科目別】玉手箱の解答時間と時間配分の例
言語問題
| 出題内容 | 問題数と時間 | 時間配分の例 |
| 論理的読解 | 32問(長文8個に各4問)/15分 | 長文を読むのに50秒 4問解答に50秒 |
| 趣旨判定 | 32問(長文8個に各4問)/10分 | 長文を読むのに40秒 4問解答に30~40秒 |
| 趣旨把握 | 10問(長文10個に各1問)/12分 | 長文を読むのに1分 1問解答に10~20秒 |
言語は3種類の内容に分かれますが、どれも必ず長文読解の問題になっています。
論理的読解では、長文8個に対してそれぞれ4問ずつ解答し、合計32問を解きます。
制限時間は15分のため、1つの長文にかけられるのは2分弱です。長文の読み取りと4問の解答に、各1分弱ずつ使うイメージで進めましょう。
趣旨判定も同様に、長文8個に対して4問ずつ出題されます。ただし、制限時間は10分と非常に短いです。
そのため、長文の読み取りと解答には、それぞれ30秒程度しか使えません。少しでも悩んでいると時間切れになりやすい内容です。
一方、趣旨把握は長文10個に対して1問ずつの出題です。制限時間も12分と、1問あたりの時間は比較的長めになっています。
しかし、長文の文字数が言語問題の中で一番多く、読み取りにはかなりの時間が必要です。長文を読んでいるだけで制限時間が迫ってくるため、時間配分が特に難しい内容といえます。
.webp)
計数問題
| 出題内容 | 問題数と時間 | 時間配分の例 |
| 四則逆算 | 50問/9分 | 1問を10秒 |
| 図表の読み取り | 29問/15分 または40問/35分 |
1問を25~30秒 または1問を45~50秒 |
| 表の空欄の推測 | 20問/20分 または35問/35分 |
どちらも1問を1分 |
計数は、計算問題と図表問題で内容が大きく異なります。
四則逆算では、50問の計算問題を9分で解く必要があり、計算速度が求められます。計算は単純なものばかりですが、1問あたり10秒しかかけられません。
解答を考え直す時間が無いため、一度出た計算結果をそのまま使うことになるでしょう。玉手箱の中では最も時間制限が厳しい問題となっています。
一方、それ以外の2種類では、計算速度はそれほど求められません。グラフや表から、問題で問われているデータを素早く読み取る力が必要です。
図表の読み取りは、29問を15分、または40問を35分で解く問題です。15分の場合は1問あたり25~30秒、35分の場合は1問あたり45~50秒で解く必要があります。
35分の場合は時間に余裕があるものの、難易度は15分の場合よりも高くなっています。一般的には、35分で出題されるケースが多いです。
表の空欄の推測では、20問を20分、または35問を35分で解答します。どちらの場合でも1問を1分で解いていくため、ペースに違いはありません。
計数の中では1問あたりの時間が最も長いですが、その分だけ難易度も高めです。他の2種類とは異なり、図表の数値の規則性から推測して答えを導く必要があります。具体的な数値を計算で求められないため、苦手な人も多いです。
.webp)
英語問題
| 出題内容 | 問題数と時間 | 時間配分の例 |
| 長文読解 | 24問(長文8個に各3問)/10分 | 長文を読むのに45秒 3問解答に30秒 |
| 論理的読解 | 24問(長文8個に各3問)/10分 | 長文を読むのに45秒 3問解答に30秒 |
英語の問題は、長文読解と論理的読解の2種類です。どちらも長文読解系の内容で、長文8個に対して3問ずつ答える問題になっています。
時間制限は共通で10分のため、長文1つにつき1分~1分30秒程度が解答時間の目安です。英文の読解は難しいので、長文を読み取る時間を多めに取ると良いでしょう。
長文は200語前後のものが多いため、この量を目安として速読の練習をしておくと効果的です。
.webp)
性格検査
| 出題内容 | 問題数と時間 | 時間配分の例 |
| 性格 | ①68問/20分 ②30問/無制限 |
1問を15~20秒 |
| 意欲 | ①36問/15分 ②36問または48問/無制限 |
1問を15~20秒 |
性格検査では性格と意欲を計測する質問が行われます。能力検査とは異なり、両方を実施するケースがあります。
性格は68問を20分で答える本格版と、30問を時間無制限で答える簡易版に分かれます。本格版は1問を15~20秒とハイペースで答える必要があります。
簡易版であっても、あまりに時間をかけすぎると不自然だと判断されます。基本的には、本格版と同じペースを意識して答えましょう。
意欲には36問を15分で答える本格版と、36問または48問を時間無制限で答える簡易版があります。こちらも性格同様、1問15~20秒ペースで答えていきましょう。
.webp)
玉手箱の時間に関してよくある失敗
【言語】長文をじっくり読みすぎた
- ・ 問題を解く時間が少なくなる
- ・ 後半の問題に着手できなくなる
- ・ 序盤に時間をかけすぎるのが特に危険
言語問題では、長文をできるだけ早く読み取ることが最も重要です。しかし、解答に必要な情報がなかなか見つからないと、つい読み取りに時間をかけすぎてしまいがちです。
特に、序盤の問題で1問にこだわりすぎると、後半の問題に回す時間が不足する原因になります。
長文の読み取りを素早く進めるには、先に問題文や選択肢を確認しておくようにしましょう。探すべき情報や単語があらかじめわかっていれば、関係ない文章を飛ばすことができます。
.webp)
【計数】計算や数値の読み取りが遅かった
- ・ 四則逆算の速度についていけない
- ・ 図表の数値を全て把握する必要はない
計数での失敗は、計算問題と図表問題で原因が分かれます。
計算問題は比較的シンプルな形式であり、計算速度の高さが点数に直結します。そのため、暗算力が低かったり、電卓を使うべき計算で暗算したりしていると、時間が不足します。
1問ごとの時間も少ないため、焦ってしまうと一気にパフォーマンスが落ちやすいです。
一方、図表問題では必要な数値だけに注目する力が求められます。図表には多くの数値が含まれていますが、ほとんどは問題と無関係なものです。
見る必要のない数値を読み取り、時間不足になってしまうのはよくある失敗です。図表の種類が多く、問題によって注目するべき箇所が異なるのも失敗しやすい理由となっています。

【英語】英文をいちいち翻訳していた
- ・ 翻訳する時間がない
- ・ 言語よりも制限時間が短い
長文と問題文を読むのに時間をかけすぎて、解答時間が不足することが英語で多い失敗です。
英文を読む時に、頭の中で日本語に翻訳している時間はありません。英文のまま意味を理解できなければ、すぐに時間切れになってしまいます。
英語問題では、言語問題と同様に、問題文をあらかじめ読んでおくことが有効な対策になります。ただし、選択肢も全て英文で記載されているため、問題文を全て覚えておくことは難しいでしょう。
問題文と選択肢からは特徴的な単語だけを見つけておき、関連するキーワードなどを長文から探すようにすると効率的です。
【性格】1問1問で熟考しすぎた
- ・ 未解答があると正しい結果が出ない
- ・ 熟考した答えは求められていない
性格検査は、1問あたりの時間が短めです。深く考えて答えようとすると簡単に時間切れになってしまいます。未解答の質問があると、企業も志望者の性格を正しく判断できません。
深く考えてしまう理由としてよくあるのは、「企業にウケが良さそうな答え」を探していることです。特に、能力検査の結果に自信がないと、性格検査で挽回しようとしてしまいがちです。
しかし、企業が求めているのは志望者の素直な解答です。深く考えずに、その時の直感で答えた方が企業への印象は良くなるでしょう。
玉手箱で時間切れにならないための対策
問題ごとの時間配分を覚える
1問あたりの解答時間の目安は、問題によって異なります。大まかな目安を覚えていると、余裕を持って解答を進められるでしょう。
また、時間配分は数字だけ暗記するよりも、体感で覚えている方が役立ちます。実際の画面では秒単位での時間表示は行われないため、正確に時間を測って進めることはできません。
練習問題などを通じて時間配分の感覚を掴んでおくと、本番での安定感が大きく高まります。
電卓や計算機の使い方に慣れておく
Webテスト形式の計数では、電卓や計算機を使用できます。暗算だけでは厳しい計算も求められるため、実際には必須といえます。
しかし、電卓を普段使いしていない場合、本番でいきなり素早く操作することは難しいでしょう。操作に手間取ると、それだけで時間が不足しかねません。勉強の段階から実物の電卓を使い、操作に慣れておくことをおすすめします。
なお、スマホアプリやPCソフトなどの代用品はデメリットも多いです。電卓と比べ、誤操作に気付きにくいため、計算ミスの原因にもなります。必ず実物の電卓を用意しておきましょう。
時間を測って練習する
玉手箱の練習は、時間を意識して進めることが大切です。全体的に短時間での解答を求められる検査なため、正確に解けるだけでは高得点は狙えません。
問題別に時間を測って練習し、時間が足りない理由や短縮できる手順などを探してみましょう。「余計な文章まで読んでいる」「不要な数値まで見ている」といった改善点が見えてくるはずです。
最初は1問ずつ時間を測り、最終的には本番と同じ問題数・時間で練習すると効果的です。
志望していない企業で練習する
玉手箱は業種を問わず実施されているため、応募する予定がない業種の企業で試験を受けてみるのも良いでしょう。
試験本番の流れや雰囲気を体験しておくことで、本命の企業を受ける時に落ち着いて臨むことができます。さらに、練習時のペース配分が正しかったのかを再確認する機会にもなります。
練習で玉手箱を受ける際は、本命の企業と同じ形式か確認しておきましょう。練習したい科目が出題されないと、受ける意味が薄くなってしまいます。特に、計数と英語は出題されない企業もあるため、注意が必要です。

玉手箱の本番で時間内に解き切るポイント
わからない問題は適当に答えて進む
玉手箱では、解答数に対する誤答数の割合である「誤謬率」は計測されません。そのため、わからない問題は無解答のままにするよりも、適当に答えて進む方が得点に繋がります。
玉手箱は解答が全て選択式なため、当てずっぽうでも正解する確率が十分にあります。ある程度選択肢を絞った後で適当に選ぶのであれば、さらに正解の確率は上がるでしょう。
正答数さえ企業の基準を満たしていれば、誤答数は評価に影響しません。評価に影響するのは、不自然な解答時間や不正検知の記録のみです。
正答率を重視しすぎない
1問1問の正答率を重視しすぎるより、全ての問題に手を付けられるように意識しましょう。
特に、3~4問がひとまとまりになっている長文読解系の問題では重要なポイントです。1~2問目にこだわりすぎて、それ以降の問題に着手できなければ確実に失点してしまいます。
満点を取りにいく検査ではないので、数問のミスは許容することが大切です。一度出た答えは疑わず、次の問題に時間を使うことを最優先にして進めると良いでしょう。
全ての計算を電卓に頼らない
Webテスト形式の計数では電卓が使えますが、暗算で済む簡単な計算量の問題も出題されます。こうした問題に対して電卓を使っていると、タイムロスに繋がります。
自分の計算力と相談して、どの程度の計算量を超えていたら電卓を使うのか決めておくようにしましょう。
特に、四則逆算は1秒のタイムロスも避けたいシビアな時間設定になっています。暗算し始めてから電卓で解く計算量だったと気付いても、計算をやり直す時間はありません。
数字の桁数や単位など、暗算と電卓を使い分ける基準を明確にしておくと効率的です。
玉手箱の時間感覚に慣れるには模試がおすすめ!
おすすめの模試サービス
- ・ 大人塾
- ・ キャリタス模試
- ・ WEBテスト対策模試
適性検査の模試サービスは、検査の種類を絞っていないことも多いです。その中で、玉手箱に特化した内容の模試を提供しているのが上記のサービスです。
大人塾は、計数の図表問題に特化した模試を手軽に受けることができます。会員登録や料金も不要で、結果もすぐに確認できます。
結果のページでは、正答数をもとにした所感・アドバイスなどを受けられるのが特徴です。検査がどんなものなのかを軽く確認しておきたい人は、こちらから試してみるのがおすすめです。
キャリタス模試では年間4回、玉手箱の模試を実施しています。問題数はコンパクトですが、全国の平均点や自身のランキングを確認できるのが最大の魅力です。
通年で受検すれば数値で成長を実感できるため、継続的なモチベーションにも繋がるでしょう。
WEBテスト対策模試は、言語・計数・英語の全ての問題を練習できる網羅性の高い模試サービスです。1回のみ受検できるコースに加え、期間内なら2回受検できるコースも用意されています。
受検後は正答率と解説を確認でき、すぐに改善を図ることができます。プレミアムコースでは、1回目と2回目で異なる問題に挑戦できるため、様々な問題の経験を積みたい方にうってつけです。
模試の結果は悪くてもいい?
玉手箱の模試を受けて、思っていたより結果が悪くても気にする必要はありません。特に、まだ練習をほとんどしていない段階で受ける模試なら、結果が悪くなるのは当然です。
模試を受ける目的は、現状の実力や課題を見つけることです。練習の方向性を固めるために活用できれば、それだけでも十分な収穫といえます。
また、初回の模試で結果が悪いのは、単に形式に慣れていなかっただけという可能性もあります。「本番で焦ることがなくなった」と前向きに捉えることが大切です。

玉手箱は時間を意識して練習しよう
玉手箱の練習では、時間の意識が欠かせません。各科目で時間を取られがちな行程を理解し、なるべく短時間で済ませられるように改善することが重要です。
解答する際も1問にこだわりすぎず、「問題を飛ばす」という選択肢を持っておきましょう。選択問題であることを利用して、「適当に選ぶ」「2択までは絞る」などの戦略をとるのも有効です。
玉手箱で一番もったいないのは、間違えることではなく時間切れになることです。全ての問題に解答し切ることを第一に、できるだけ高い点数を目指しましょう。


.webp)


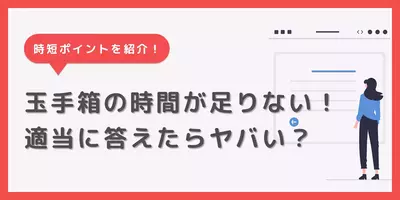
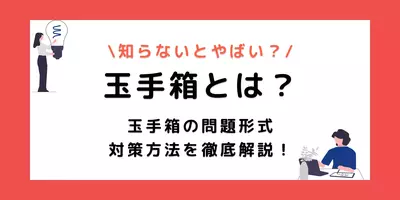
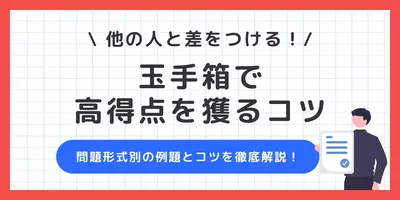
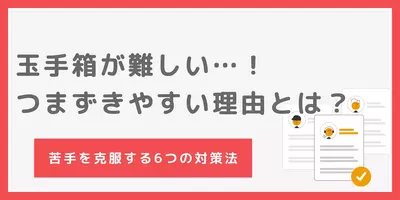
.webp)