玉手箱の言語は、能力検査の中でも特に出題頻度が高い問題です。長文読解をメインにした独特の形式なため、基本や対策を知らないと選考突破は難しいでしょう。
この記事では、押さえておくべき言語の基本情報から、今すぐできる簡単なコツを紹介します。
さらに、問題ごとの対策や長文読解のポイントも例題付きで解説しています。今から勉強を始める人でも、言語の対策方法を掴めるでしょう。
言語問題の知っておきたい基礎知識
言語問題の出題傾向
| 論理的読解(GAB形式) | 8長文32問/15分 |
| 趣旨判定(IMAGES形式) | 8長文32問/10分 |
| 趣旨把握 | 10長文10問/12分 |
玉手箱の言語は、「論理的読解」「趣旨判定」「趣旨把握」の3種類に分けられます。Webテストの場合は、この中から1種類だけが出題されます。一方、テストセンターの場合は必ず論理的読解だけが出題されます。
論理的読解と趣旨判定は、1つの長文に対して4問を解く形式です。長文は8個出題されるため、合計の問題数は32問です。
趣旨把握は1つの長文ごとに1問ずつ解いていく形式になっています。長文は10問出題され、合計の問題数は10問です。
いずれも制限時間が短めであり、ゆっくり解ける問題はありません。素早い処理能力が求められます。
難易度はおかしい?
玉手箱は適性検査の中でも難易度が高いとされており、「言語の難易度はおかしい」と感じる人もいるでしょう。
しかし、問題の内容自体は中学~高校レベルの学力で十分に解けるものになっています。
玉手箱が難しすぎると感じる原因の多くは、時間不足です。1問を1分程度やそれ以下で解かなければいけない焦りから、ミスが起きやすいのです。
そのため、解答速度に慣れていれば、問題自体の難易度が高いと感じることはないでしょう。
企業によっては実施しないこともある
言語は性格検査と並び、実施している企業が特に多い問題です。しかし、中には言語を出題せず、計数や英語の能力のみを重視する企業もあります。
企業ごとの出題内容は、事前に調査をしていればある程度把握することが可能です。もし、志望企業で言語が出題されないようであれば、他の問題の対策に時間を割いた方が良いでしょう。
ただし、実際に何が出題されるのかは受けてみるまでわかりません。言語は比較的対策しやすい分野であるため、念のため全ての問題の対策をしておくと安心です。
.webp)
長文読解系の問題しか出ない
玉手箱の言語では、どの問題でも長文読解をする内容のみが出題されます。そのため、長文の速読力が最も重要になってきます。
長文の文字数は600~1000字と幅があります。これは学校で使う原稿用紙の約2枚分にあたる量です。この長さの文章を、長くとも1分程度で読み取らなければなりません。
一方で、単語や熟語の意味・用法といった知識を問う問題は出題されません。多少わからない語句があっても、前後の文章から推察することができるでしょう。
趣旨把握は特に時間が厳しい
言語問題の中でも、趣旨把握は特に時間が厳しく設定されています。
言語問題の中で最も文章量の多い長文が提示されるため、まず読み取りに時間がかかります。
その上、選択肢の文章も全て長文に関する内容になっているため、長文を飛ばし読みして時短するのは難しいでしょう。
また、問題数が少なく、1問ごとの配点が高いです。1つでも解くのが間に合わないだけで、全体の点数に響いてしまいます。Webテスト形式では趣旨把握を出題される可能性があるため、対策は必ず行いましょう。
得点は6~7割が目標
玉手箱のボーダーラインは企業によって異なりますが、一般的には5~6割の企業が多いです。
言語は玉手箱の中でも点数を取りやすいため、6~7割を目標とするのが良いでしょう。言語でボーダーよりも高い点数を取れていれば、他の分野の点数を補える可能性が出てきます。
ただし、商社や大手コンサルなど倍率の高い企業では、もっと高い点数が求められます。言語を含めて全体で8~9割が取れなければ、足切りされてしまう可能性が高いです。
また、どの企業でも偏った得点は評価されにくいので、言語以外も平均的に伸ばせるように対策することは必須です。
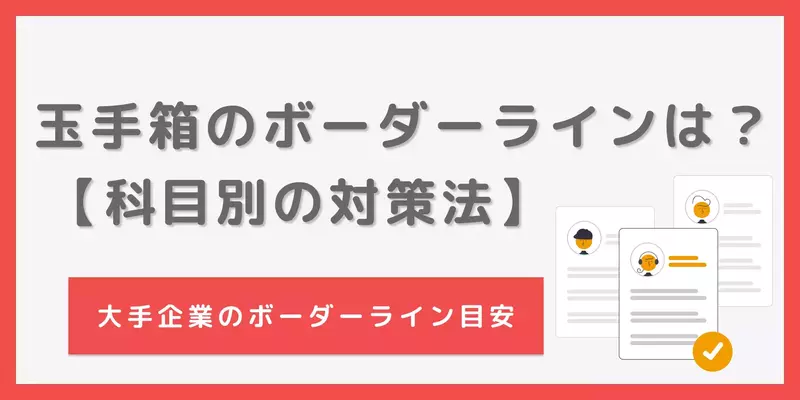
【簡単】玉手箱の言語問題を解くコツ

最初に問題文と選択肢を読んでおく
長文を読む前に問題文と選択肢を確認し、「何が問われているのか」を把握しておくようにしましょう。
長文には問題と無関係な文章も多く含まれるため、最初に読むと効率が悪くなります。問題を先に読んでおけば、無関係そうな文章を飛ばすことが可能です。
そのため、長文を読むというより問題に関係している文章を探すという感覚で読むのがいいでしょう。
長文の要点を探す
言語問題の長文を読む際は、要点と関連する記述を探していくとスムーズに進められます。
問題文でもよく取り上げられるのは「筆者の主張」や「長文の趣旨」です。これらの内容は、冒頭や結論を読めばわかることが多いです。
また、「しかし」「つまり」「一方で」など、論理が切り替わる接続詞に着目するのもおすすめです。こうした接続詞の後には、筆者が伝えたい主張や趣旨が続く傾向にあります。
長文の要点を見つけられたら、その前後の文章も問題を解くヒントになります。「何と比べられているか」「どんな論理による主張か」を確認すれば、より明確な根拠を持って解答できます。
正答率にこだわりすぎない
玉手箱の問題は制限時間が厳しいため、1問をじっくり解いている時間はありません。
玉手箱は満点を狙うような検査ではなく、6割以上の点数が取れれば合格圏内に入ることができます。そのため、数問のミスは起こるものとして解いていくことが重要です。
全ての問題で正答しようとすると、その後の問題を解く時間がなくなり、最終的に大きく点数を落としかねません。
多少迷っても、最初に「これだろう」と思った解答はそのままにしておき、次の問題へ進むようにしましょう。
わからなくても適当に選ぶ
玉手箱では、正解の数だけを測定しており、間違えた問題の数は測定されません。そのため、わからない問題でも適当に答えた方が正答率は上がる可能性があります。
言語問題の選択肢は3択または4択です。趣旨判定だけが4択ですが、こちらは明らかに間違っている選択肢が1つ含まれていることも多いです。そのため、最低限絞り込んでおけば、適当に答えたとしても3~4割は正解する見込みがあります。
一番もったいないのは、時間切れで無解答となってしまうことです。「〇秒前になったら適当に答えて飛ばす」といったルールを決めておくと、迷わずに判断できるでしょう。
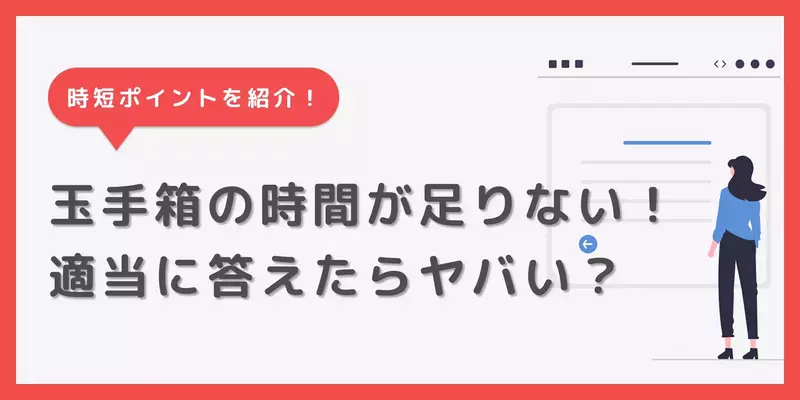
玉手箱の言語の例題と対策法
論理的読解はキーワードの前後がヒントになる
次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。
現代社会において、「移動」という概念は大きく変容しつつある。かつて人々の移動は、主に物理的な場所の変更を意味していた。しかし、インターネットの普及により、私たちは物理的な移動を伴わずに、異なる文化や社会と接触できるようになった。この「仮想的な移動」は、従来の移動概念を根本的に覆すものである。
興味深いのは、この仮想的な移動の増加が、実際の物理的な移動にも影響を与えていることだ。たとえば、海外旅行の形態が変化している。以前の旅行者は、現地で初めて異文化に触れ、それを「発見」していった。しかし現在では、インターネットで事前に詳細な情報を得た上で旅行に出かける。そのため、旅行者の多くは「予習済み」の体験を確認するような旅をしている。
一方で、このような仮想的な移動の普及は、新たな問題も生んでいる。情報技術の発達により、私たちは世界中の出来事をリアルタイムで知ることができる。しかし、それは必ずしも深い理解や共感につながっているわけではない。むしろ、安易な理解や偏見を助長する可能性すらある。実際の体験を伴わない知識は、ときとして表面的な理解にとどまってしまうのだ。
【選択肢(共通)】
A: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。
B: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。
C: 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。
【設問】
(1)現代の海外旅行者は、インターネットで得た知識をもとに、その正誤を確かめるような旅をする傾向がある。
(2)仮想的な移動の普及により、物理的な移動の必要性はなくなった。
(3)インターネットを通じた異文化理解は、偏見をなくすことにつながっている。
(4)情報技術の発達により、人々は世界の出来事をリアルタイムで知ることができるようになった。
(1)解答: A
2段落目で、現代の旅行者は「インターネットで事前に詳細な情報を得た上で旅行に出かける」「『予習済み』の体験を確認するような旅をしている」と明確に述べられている。設問文は正しい。
(2)解答: B
本文では、仮想的な移動が増加していることは述べられているが、物理的な移動がなくなったとは述べていない。むしろ、仮想的な移動が物理的な移動に影響を与えているという記述があり、両者が共存していることが示唆されている。設問文は間違い。
(3)解答: C
3段落目では、仮想的な移動が「安易な理解や偏見を助長する可能性すらある」と述べているが、実際に偏見をなくしているかどうかについては言及されていない。設問文の正誤は判断できない。
(4)解答: A
3段落目で「情報技術の発達により、私たちは世界中の出来事をリアルタイムで知ることができる」と明確に述べられている。設問文は正しい。
論理的読解では、長文についての問題文に対して「正しい」「間違っている」「判断できない」のどれかを選びます。テストセンターで必ず出題されるので、言語の中でも特に目にする機会は多いでしょう。
この問題は、本文の表現を言い換えたり、要約しなければ答えられない内容が多いことが特徴です。一度で長文を理解し切れていないと、何度も読み返さなければなりません。
対策として、まず「本文を読まなくても答えられる」ような問題は省いて考えることが大切です。
常識的に考えて、明らかに正しいか間違っているものはその時点で解答が決まります。これによって、見なければならない内容を減らすことができます。
次に、問題文から特徴的なキーワードを見つけておき、本文で使われている箇所を探すと良いでしょう。
独特な言い回しや固有名詞は、本文中の表現をそのまま抜き出している可能性が高いです。その前後の文章を読めば、問われている内容の正誤を判断できるでしょう。
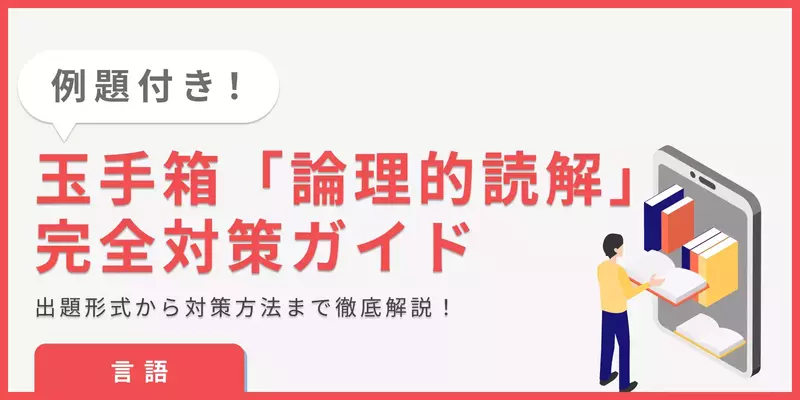
趣旨判定は筆者の主張を見つける
次の文章を読み、設問文についてそれぞれA・B・Cのいずれであるか判断して答えなさい。なお、設問文には、AとCに該当するものが必ず1つ以上含まれています。
【面接での質問に向き合う姿勢】
就職活動の面接では、答えにくい質問が投げかけられることがある。「あなたの人生において最も大切なものは何ですか」といった、シンプルながら深い答えを求められる質問だ。このような場合、すぐに答えるのは避け、いったんその質問の意図を考えるべきだ。
即答してしまうと、質問の背景にある面接官の意図を汲み取れない可能性がある。逆に、質問の背景を探るために「この質問はどのような状況を想定しているのでしょうか」といった逆質問をするのは有効だ。たとえば、「家族との時間を優先したいと考える一方で、仕事上の大きなプロジェクトにも関わりたい場合、どのような選択をするか」といった具体的な状況を引き出すことができるだろう。
このような逆質問は、対話を深めるきっかけとなり、面接官に対して「考える力」や「柔軟な対応力」をアピールする機会にもなる。また、面接官はこうした対話の中で学生の価値観や思考の柔軟性を見ている。
質問の意図がつかめないときや、答えに詰まったときには、曖昧な解答で終わらせるのではなく、逆質問をして条件を具体的に絞りながら対話を続けていくことが重要だ。それが、よりよい印象を与えるコツでもある。
【選択肢】
A: 筆者が一番訴えたいこと(趣旨)が述べられている。
B: 本文に書かれているが、一番訴えたいことではない。
C: この本文とは関係ないことが書かれている。
【設問】
(1)面接で逆質問を活用することで対話を深めることが重要である。
(2)面接では、即答が求められる場合があるため、素早い判断力を鍛える必要がある。
(3)面接での逆質問は、面接官が学生の人間性や柔軟さを評価するために重要な手段である。
(4)逆質問を使うことで面接官に良い印象を与えることができる。
(1)解答: A
3段落目で、面接官との対話を深めるために、こちらから逆に質問をすることをすすめている。また、4段落目で、「逆質問をして対話を続けていくことが重要だ」と強調している。設問文は本文の趣旨。
(2)解答: C
本文では即答を避ける重要性について述べられているため、「即答が求められる場合がある」という内容は本文とは関係ない。
(3)解答: B
3段落目で、面接官が逆質問などを通した対話の中で学生の価値観や思考の柔軟性を見ていることが述べられている。しかし、これは本文の主張の補足的な内容である。
(4)解答: B
4段落目で、逆質問を用いて対話を続けることがより良い印象を与えるコツであると述べられているが、趣旨は面接官との対話を深めることの重要性であり、逆質問を使うだけで良い印象を与えられるわけではないため、趣旨ではない。
趣旨判定は、長文に関する問題文が、本文の趣旨に合っているかを3択で答えます。
論理的読解とは異なり、そもそも問題文の内容に本文で触れていないケースがあるのが難しい点です。正しい内容に見えても、本文にない記述は趣旨に合っているとはいえません。
そのため、問題文自体を軽く要約してから長文を読み始めるのが対策になります。読んでみて一度も記述が出てこなかった問題は「本文とは関係ない」と答えられます。
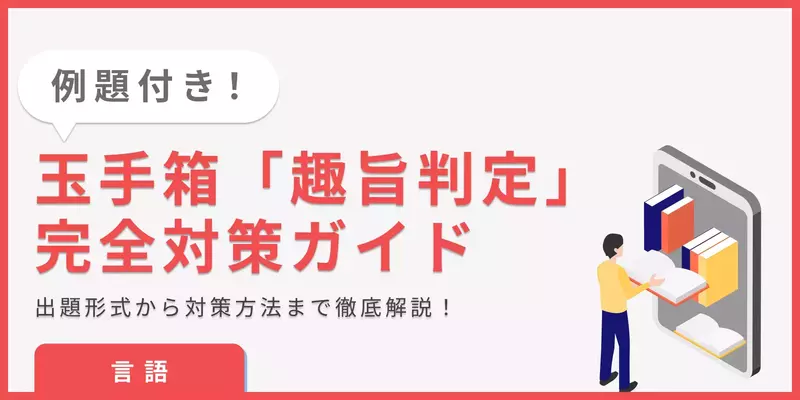
趣旨把握は重要なキーワードを探す
以下の文章を読んで後の問いに答えなさい。
ペットを飼っている人なら、誰しも感じることがあるだろう……「この子は私の言葉の意味が分かっているのではないか」という瞬間を。少し話は異なるが、育てている農作物に明るい音楽を聞かせてやると、聞かせなかったものより大きな実がなったという事例もある。私たちの世界では、このような“動植物の人間的側面”がかい間見える瞬間が多々ある。 感情や意識といったものは科学的に人間特有のものとされている。そういった行為や思考を人間ではないものに当てはめることを「擬人主義(anthropomorphism)」と呼ぶ。
古くから「動物や植物に感情があるかどうか」という議論は度々行われていた。しかしこの議論が「動植物が人間性を持つことの証明」のための研究に繋がることはほとんどなかった。この問いについては「実験者の主観が反映されすぎる」という見解が幅を効かせており、科学的信頼性を担保しにくい分野として捉えられていたからだ。そこにはデカルトの「動物は考える能力のない野蛮な存在」という考えなどに代表されるような、欧米的な「人間中心主義(anthropocentrism)」が今でも根強い影響を及ぼしていると言えるだろう。 近年では多くの学者の学術調査により、仮借勘定を忘れないコウモリや知恵の伝承を行うネズミなどが発見され、“人間的な営み”を示唆する動物の行動事例が少なからず確認されている。こうした事実は、今まで無視されてきた動物における“感情や意識の存在”を十分に示唆している。人間の価値基準に固執していたら絶対に見えなかった、紛れもない事実だ。ただ、これらは「動植物が人間性を持つ」決定的な証拠とは言い切れない。それを証明するには、まだまだ研究が必要である。
日本人は一般的に「擬人主義に抵抗の少ない民族」として認知されている。たとえば、日本の二次創作文化の中では『ヘタリア』といった作品に見られるような、「擬人化」という表現方法が市民権を得ている。無機物を人物化して描くこの表現は、原義とは少々異なるベクトルだが、「人ではないものを人と同様に捉える」という観点では大いに共通する。 なぜ、日本人は欧米で馴染みにくかった「擬人主義」をすんなり許容できているのだろうか。それは、日本に「八百万の神信仰」の文化が根付いているからだと推測される。「八百万の神信仰」では、基本的に“万物に神が宿る”というスタンスを取っている。要するに、海や山などの抽象度の高い自然や、キツネやたぬきなどの動物、稲や粟などの農作物にまで、神様の化身や使いと捉えて崇拝するのだ。神は一般的に“人の形をしていて意思のある存在”だったため、古来より動植物に神を見出してきた日本人にとって、それと近似した「擬人主義」は、ごく自然に受け入れられる概念なのだろう。
【問題】
次の文章を読んで、筆者の訴えに最も近いものを選択肢の中から一つ選びなさい。
- A. 動植物にも人間的な感情が存在する。
- B. 動物が人間的な振る舞いを見せるのは、偶然の産物にすぎない。
- C. 日本で擬人主義が受け入れられているのは、古くからの信仰に由来する。
- D. 擬人化は日本人のアイデンティティを色濃く反映した、日本固有の表現方法である。
解答: C
本文中に『なぜ、日本人は欧米で馴染みにくかった「擬人主義」をすんなり許容できているのだろうか。それは、日本に「八百万の神信仰」の文化が根付いているからだと推測される』とあることから、正解はCの『日本で擬人主義が受け入れられているのは、古くからの信仰に由来する』です。
趣旨把握は、長文についての4つの選択肢から、趣旨に最も近いものを選ぶ問題です。
選択肢はどれもそれらしい内容になっていることが多く、しっかり長文を読み込まなければ答えられません。
趣旨把握の場合、問題文を全て把握してから長文を読むのは逆に時間がかかります。最初に特徴的なキーワードだけを確認しておき、本文中で見つけた時に改めて問題文を読む方法がおすすめです。
言語の中でも特に時間が不足しやすい問題なので、解き方はしっかり覚えておきましょう。
玉手箱の言語のおすすめ勉強法
出題パターンを覚える
言語を勉強する時には、最初に出題内容のパターンを覚えることがおすすめです。
選択肢のタイプや制限時間が全て異なるので、それぞれに合った解き方で進めなければ高得点は取れません。
玉手箱の問題は、検査が始まった時点でどの内容なのか判別することが可能です。出題内容ごとの問題数や時間を覚えておけば、「1問何秒で解いていくのか」「どう解いていくべきか」が瞬時にわかります。
単に暗記をするだけでも有効な対策になるので、時間がない人も必ずやっておきましょう。
長文を読む時間を測る
言語問題は、長文読解の速さで時間の余裕が大きく変わります。読む時間を測り、解答を考える時間がどれだけ残るのか確認してみましょう。
目安としては、600文字の長文の要点を読み取るのに30~40秒程度で済めば十分です。解答に必要な内容を素早く読み取ることができれば、答えを精査する余裕も生まれます。
また、実際の問題では長文の途中で解答を済ませられることもあります。測った時間は「最長でかかる秒数」として考えましょう。
対策アプリなら短時間でもOK

玉手箱の対策アプリを使えば、移動中や空き時間にスマホで勉強を進められます。
基本的には、玉手箱専用のアプリを使うのが一番正確な対策になります。しかし、長文読解系の問題があれば、SPIの対策アプリも役に立つでしょう。
まとまった時間がなくても着実に点を伸ばせるのが、対策アプリの最大のメリットです。
ただし、アプリだけの勉強で本番に臨むのは危険です。あくまで補助的な役割として考え、その他の勉強方法も併用するようにしましょう。
.webp)
対策本の利用がおすすめ
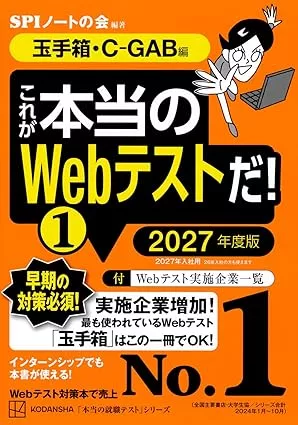
玉手箱の勉強には、対策本や問題集を使うのが最も無難です。言語以外にも計数・英語・性格まで解説しているものが多いので、1冊で玉手箱対策を完結させられます。
対策本には、解説重視・問題数重視・模擬試験重視など、それぞれ特徴があります。今の学力や好きな勉強スタイルに合わせて選ぶと良いでしょう。
長文に慣れて言語問題で高得点を狙おう
玉手箱の言語は、ほとんどの実施企業で出題される問題です。解答に高度な知識は求められないため、対策すれば着実に点数を伸ばしていけるでしょう。
言語問題では、長文読解に慣れているかどうかが最大のポイントになります。事前に様々な長文を読み、速読に慣れておくことが大切です。
さらに、出題内容ごとのコツを理解すれば、よりスムーズに解いていくことができます。見る機会の多い論理的読解をはじめとして、3種類の問題をしっかり仕上げておきましょう。
.webp)

.webp)


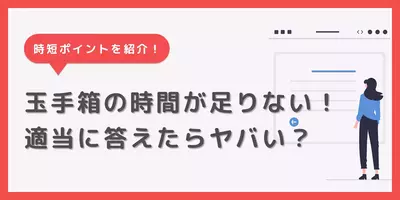
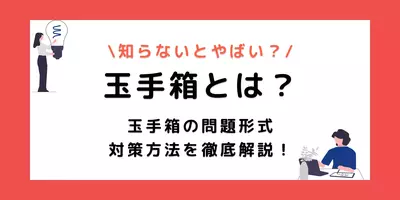
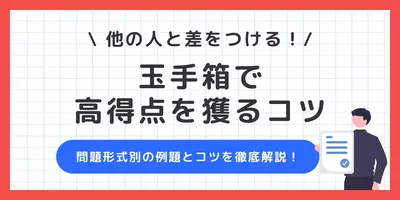
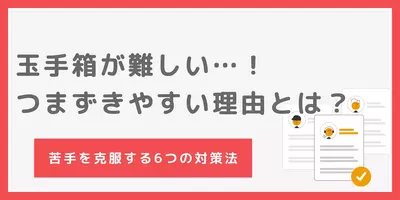
.webp)