玉手箱の言語で出題される「論理的読解」は、長文読解系の問題です。問題文の正誤を判断する必要があり、ただ読むだけでなく「論理的な思考力」も問われます。
この記事では論理的読解の基本とあわせて、解答・解説付きの例題を紹介します。
後半では長文の速読力を身に付けるためにおすすめの対策法や、解答のコツなども解説しています。
目次
玉手箱の言語問題「論理的読解」とは?
論理的読解では、600字程度の長文を読んで4つの問いに答えます。全部で8個の長文が出題され、問題数は32問となっています。
長文に関する問題文が正しいかどうかを判断する内容で、選択肢は「正しい」 「間違っている」 「判断できない」の3つで固定です。解答には明確な根拠があり、推測や感覚で答えるような問題はありません。
制限時間は15分と短めで、1問あたり30秒程度しか割り振ることができません。じっくり読むよりも、素早く要点だけを掴む力が重要になります。
論理的読解|例題と解答・解説
例題1
次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。
知識の伝達手段としての「書物」は、デジタル技術の台頭により、その存在意義を問われている。しかし、書物の本質的な価値を理解するためには、それが単なる情報伝達の手段ではなく、人類の思考様式そのものを形作ってきた媒体であることを認識する必要がある。
書物という形態は、人間の思考に独特の時間性をもたらした。文字を追って左から右へ、あるいは上から下へと読み進めていく行為は、論理的思考の基盤となる直線的な時間認識を強化する。これは、口承文化における循環的な時間認識とは本質的に異なる。音声による伝達は、その場限りの一回性を持ち、反復可能であっても完全な同一性は保証されない。一方、書物は同一の内容を何度でも参照することを可能にし、それによって批判的思考や分析的な読解を促進した。
また、書物は「沈黙の文化」を生み出した。音声による伝達が必然的に他者との関係性を前提とするのに対し、書物を介した知識の獲得は個人的な営みとなる。この変化は、近代的な個人の誕生と密接に結びついている。読書という行為を通じて、人々は他者から独立した思考空間を確保し、自己と対話する術を身につけた。これは、デカルトに代表される近代的な主体性の確立にも大きな影響を与えたとされる。
ただし、こうした書物の特質は、必ずしもデジタルメディアと対立するものではない。むしろ、現代のデジタル技術は書物が築いた思考様式を前提としながら、新たな可能性を模索していると見るべきだろう。確かにデジタル技術は、ハイパーテキストのような非線形的な読解を可能にし、また社会的な読書体験を提供することで、書物がもたらした「個」の文化に一定の変更を迫っている。しかし、そこで起きているのは書物の否定ではなく、書物文化の新たな展開だと理解すべきである。
【選択肢】
A: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。
B: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。
C: 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。
(1)デジタル技術は、書物がもたらした直線的な読解方法を完全に無効化している。
(2)書物の社会的影響力は、グローバル化の進展により急速に低下している。
(3)書物による知識伝達の特性は、近代的な個人の主体性の形成と密接に関連している。
(4)口承文化における知識伝達は、完全な同一性を持って反復される。
(1)
答え: B
最終段落では、デジタル技術が書物の思考様式を「否定」するのではなく、「新たな可能性を模索している」と述べられている。むしろ、ハイパーテキストなどによって読解方法に変更を迫っているものの、完全に無効化しているわけではない。設問文は間違い。
(2)
答え: C
本文では、書物の社会的影響力やグローバル化による変化について直接的な言及はない。デジタル技術との関係は述べられているものの、グローバル化が書物の影響力に与える具体的な影響については何も述べられていない。設問文の正誤は判断できない。
(3)
答え: A
3段落目で、書物による個人的な知識獲得が「近代的な個人の誕生と密接に結びついている」と述べられ、さらに「デカルトに代表される近代的な主体性の確立にも大きな影響を与えた」と明確に指摘されている。近代的な個人の主体性形成と書物の知識伝達特性の深い関連性が示されている。設問文は正しい。
(4)
答え:B
2段落目で「音声による伝達は、その場限りの一回性を持ち、反復可能であっても完全な同一性は保証されない」と明確に述べられている。設問文はこれと矛盾する。
例題2
次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。
深海は地球上で最も過酷な環境の一つであり、高い水圧、低温、そして光が届かない暗闇の中で、驚くべき生命が存在している。深海生物は、極限環境に適応するための特殊な生理機能や生態を持っている。例えば、マリアナ海溝の深度約11,000メートルに生息するハダカカメノテは、通常の生物では考えられない高い水圧に耐えられる特殊なタンパク質を持っている。
深海生物の多くは、光合成ができないため、化学合成細菌に依存している。深海の熱水噴出孔周辺では、硫化水素や二酸化炭素などの無機物質を利用する化学合成細菌が、生態系の基盤を形成している。これらの細菌は、周囲の極限環境で生きる他の生物に栄養を供給し、複雑な食物連鎖を支えているのである。水深2,000メートル以深の深海域では、捕食者と被食者の関係が陸上や浅海域とは大きく異なる生態系が形成されている。
近年の深海探査技術の発展により、これまで知られていなかった新種の生物が次々と発見されている。自律型海中ロボット(AUV)や有人潜水艇の進歩は、人類が深海の生態系を理解する上で大きなブレイクスルーとなっている。科学者たちは、深海生物の遺伝子解析や生態調査を通じて、地球上の生命の多様性と適応力の驚くべき可能性を明らかにしつつある。
【選択肢】
A: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。
B: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。
C: 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。
(1)深海生物の生態系は、光合成を主な栄養源としている。
(2)深海探査技術の発展は、未知の深海生物の発見に大きく貢献している。
(3)深海生物の遺伝子解析により、地球外生命の存在可能性について新たな知見が得られている。
(4)深海の熱水噴出孔周辺の生態系は、無機物質を利用する化学合成細菌によって支えられている。
(1)
答え:B
本文の第2段落で、「深海生物の多くは、光合成ができないため、化学合成細菌に依存している」と述べられており、深海生態系が光合成を主な栄養源としているというのは明らかに間違いである。設問文は間違い。
(2)
答え:A
第3段落で、「近年の深海探査技術の発展により、これまで知られていなかった新種の生物が次々と発見されている」と明確に述べられており、深海探査技術が未知の深海生物の発見に大きく貢献していることが示されている。設問文は正しい。
(3)
答え:C
本文の第3段落では、深海生物の遺伝子解析について「地球上の生命の多様性と適応力の驚くべき可能性を明らかにしつつある」と述べられているが、地球外生命の存在可能性については何ら言及されていない。設問文の正誤は判断できない。
(4)
答え:A
第2段落で、「深海の熱水噴出孔周辺では、硫化水素や二酸化炭素などの無機物質を利用する化学合成細菌が、生態系の基盤を形成している」と述べられており、設問文は正しい。
論理的読解|速読のための対策法
ニュースや本を読む習慣をつける
・ ネットニュース
・ 本
・ 新聞
・ 教科書
・ 論文
論理的読解では様々なテーマの長文が出題されます。ビジネスや社会問題・時事系のテーマが用いられやすいですが、それ以外の内容が出る可能性もあります。
ネットニュースや本では様々な内容の長文を読むことができるため、読み取り速度を伸ばすための練習に使えるでしょう。何時間も根を詰めて読む必要はなく、毎日暇な時間に見る程度であっても十分な対策になります。
その際、興味や知識がある分野よりは、普段触れないようなテーマの文章を読む方が効果的です。本番で出題される長文のほとんどは馴染みのない内容なので、似たような感覚で読むことができます。
適当な長文を要約してみる
出題される長文を一言一句まで把握する必要はありません。大まかな話の流れと要所の記述だけ拾うことができれば、問題に答えられます。
その練習として、様々な文章を素早く要約する意識で読んでみることがおすすめです。どんなテーマの文章でも要点をすぐに掴めるようになれば、本番で見慣れないテーマが出題されても問題なく理解することができます。
練習用の文章は、100~200字程度以上であれば何でも構いません。100~200字は、600字程度の長文の1段落分に相当するため、段落ごとの要約という形で活かせます。
600字を1分で読めるのが理想
論理的読解で出題される600字程度の文章は、読むのに1分半~2分程度かけるのが一般的な文章量です。しかし、玉手箱では問題ごとに時間制限があり、じっくり読む余裕はありません。
そのため、普通のペースよりも早めの、1分で読み切れることを目標に対策を進めましょう。
実際の問題では、長文を最初から最後まで読むような解き方はほとんどしません。しかし、「最長でも1分で読める」という状態になっていれば、多少要約に手こずっても時間内に解き切ることができます。
読み取り速度に自信があると、本番で緊張しにくくなることも期待できるでしょう。
論理的読解|解くコツは「問題文の先読み」
問題文に関する内容を長文から探す
論理的読解は長文を読み取る問題ですが、長文から読み始めると余計な時間がかかってしまいます。まずは問題文を読み、「長文から何を読み取ればいいのか」を探しておきましょう。
選択肢は毎回固定なので、読む必要はありません。問題文で何が問われているのかだけに目を通しておくと、それに関連する内容を探すという読み方ができます。
普通に一通り読んでから考えるよりも効率的に解答できるため、時間が不足しやすい玉手箱向けの解き方です。
「間違っている」時も根拠が必要
・ 問題文と一致する記述あり→「正しい」
・ 問題文と相反する記述だけ→「間違っている」
・ どちらの記述もない→「判断できない」
「論理的に正しい」という点に注目して、一致する記述だけを探しがちです。しかし、「間違っている」が答えの場合でも明確な根拠となる記述が必要です。
ただ一致する記述がないだけでは、「間違っている」 「判断できない」のどちらが正解か断定できません。根拠がないのに答えを決めつけてしまうのは、本番で焦っていると起こりやすい判断ミスです。
問題文と一致する記述があれば「正しい」、反対・矛盾する記述があれば「間違っている」という判断基準は徹底しましょう。その上で、一切言及されていない場合だけ「判断できない」を選ぶべきです。
一般常識で判断できる問題もある
論理的読解では、筆者の考えではなく「文章から論理的に考えて」正しいかどうかを答えます。そのため、そもそも一般常識で考えればわかるような問題は、長文を読まずとも正解できる可能性があります。
当然ですが、常識や知識だけを頼りに解くのは安定した方法とはいえません。しかし、「じっくり解いて時間が足りない」よりは、「一部を軽く飛ばして間に合う」方が大切です。
問題を解いていて、時間が足りないと感じるようであれば、自分の常識や知識をもとに判断しても良いということを覚えておきましょう。
解答時間の半分以上は読解にかけてOK
論理的読解は32問を15分で解きます。単純計算では1問30秒程度ですが、実際は「8個の長文を15分」という形式です。つまり、長文1つにつき2分弱というのが正しい表現でしょう。
1問あたりでペース配分を考えるよりも、長文1つごとに読解と思考に時間を割り振る意識が大切です。
問題文を読み、探すべき記述を把握していれば、解答を考える時間はそれほど必要ありません。合計で1分近くは読解に割いても問題ないと考えましょう。

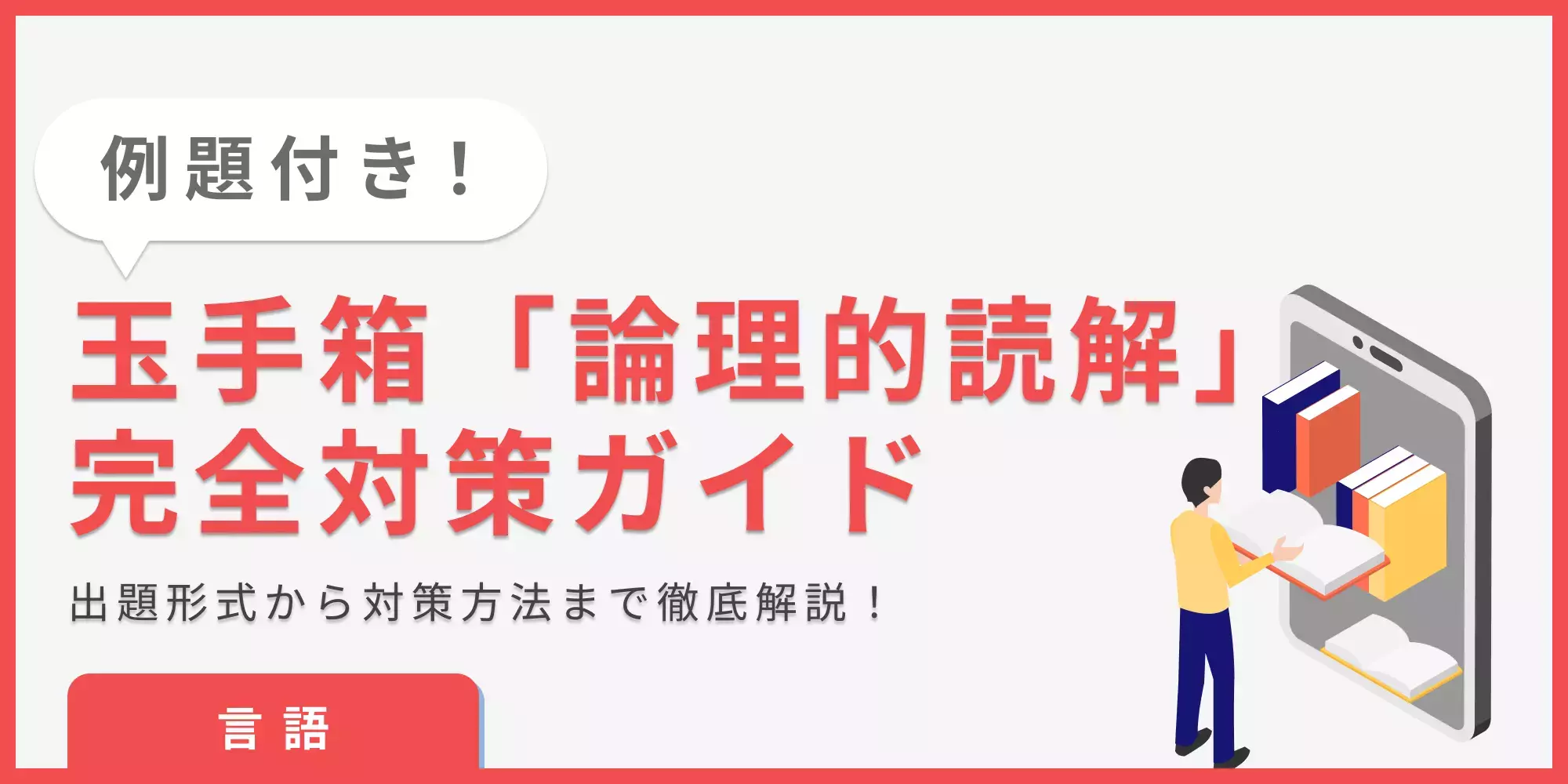


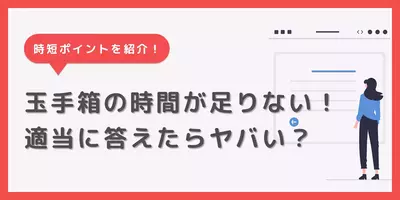
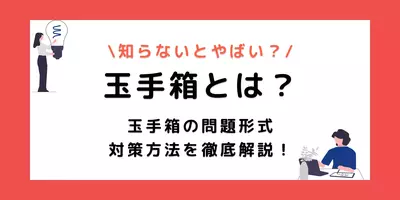
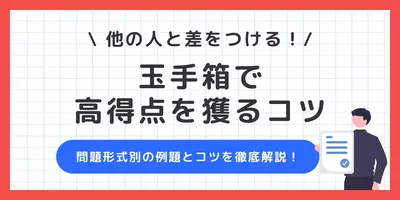
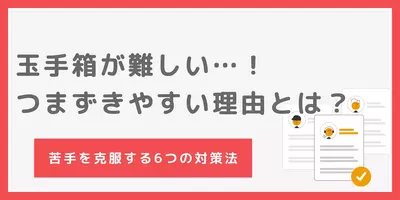
.webp)