就活ではSPIに次いで受ける機会の多い玉手箱には、従来型・GAB・C-GAB・C-GAB plus・Web-GAB・IMAGESと様々な種類が存在します。
どれも玉手箱の一種といえますが、出題内容や受検場所に違いがあります。特にGABやC-GABは、名称が似ていることから混乱しやすくなっています。制限時間や難易度にも違いがあり、違いに合った対策が必要になります。
本記事では、特に使われることの多い玉手箱・GAB・C-GABの違いを徹底解説しています。それぞれの特徴を理解し、問題演習を効率よく進めましょう。
目次
玉手箱とGABの違いとは?
| 形式 | 受検場所 | 解答方法 |
| 玉手箱(従来型) | 自由 | PC |
| GAB | 企業指定の会場 | マークシート |
| C-GAB | テストセンター | PC |
GABは企業で受検する
GABの大きな特徴の一つは、企業を実際に訪れて受検することです。受検会場としては、企業のオフィスだけでなく、企業が用意した貸会議室などが指定される場合もあります。
企業でGABを受検する際は、リクルートスーツの着用がおすすめです。採用担当者が試験監督を務めることが多いため、面接と同様のフォーマルな服装が求められます。
GABは紙のマークシートに解答する
GABでは、紙の問題冊子とマークシートを使用して解答を行います。初めから問題の全体像を確認できるので、時間配分を決めやすい形式です。
また、解答用の筆記用具やメモは、当日に貸し出されるものだけが使用可能です。電卓も使用禁止となっているので、身分証明書以外の持ち物は必要ありません。
GABは各分野の出題内容が決まっている
GABは各分野の出題内容が固定されていることも特徴です。玉手箱は各分野2〜3種類から1種類が企業側に選ばれて出題されるのに対し、GABの能力検査では、計数で図表の読み取り、言語で論理的読解のみが出題されます。英語の出題はありません。
そのため、自分の志望企業がGABを実施している場合は対策がしやすく、形式に十分慣れてから本番の試験を受検することができます。
.webp)
GABとC-GABの違いとは?
- ・ C-GABでは英語の出題あり
- ・ C-GABの方が制限時間が短い
- ・ GABとC-GABの難易度は同じ
C-GABでは英語の出題あり
C-GABの出題範囲には英語が含まれており、計数・言語・英語の全3分野から出題されます。一方、GABとWeb-GABでは英語は出題されません。
英語分野では論理的読解が出題され、8つの英語長文に対して3問ずつ答えていくことになります。制限時間は10分のため、長文1つを1分程度で解答する必要があります。
言語と計数に比べると出題頻度は低い分野ですが、英語も実施される企業では高い英語力が求められることが多いです。出題の可能性がある場合は、十分な対策が必要でしょう。
C-GABの方が制限時間が短い
C-GABは、全体の試験時間がGABより短くなっています。全体の試験時間としては、GABは2分野(計数・言語)の能力検査と性格検査で90分、C-GABは3分野(計数・言語・英語)の能力検査で40分と設定されています。
1問あたりの時間に大きな違いはないため、極端にシビアになるわけではありません。しかし、全く同じペースでは解けないので、両方の時間設定で問題練習をするのは必須といえます。
GABとC-GABの難易度は同じ
GABとC-GABは問題の難易度に大きな差はなく、計数・言語分野の出題内容も共通しています。そのため、GABとC-GABは基本的に同じように対策すれば問題ありません。
ただし、英語の出題の有無や制限時間の違いはあるため、「全く同じもの」と捉えて臨むのは危険です。
特に、どちらか片方の対策で時間配分に慣れている人ほど、もう片方の本番で時間配分のミスをしやすいため、注意しましょう。
.webp)
3つの適性検査は予約の有無で見分ける!
・ 受検用のURL
→玉手箱
・ 場所と日時の予約用URL
→C-GAB
・
場所と日時が指定されている
→GAB
※その他の適性検査の可能性もあります。
玉手箱・GAB・C-GABのうち、どれが実施されるのかを見分ける際は、企業から届いた受検案内を手掛かりにしましょう。
玉手箱は受検場所と時間が自由なため、アクセスするとそのまま受検画面に切り替わるURLが送られてきます。
一方、GAB・C-GABは企業や企業指定の会場、テストセンターで受検するため、日時や場所を予約するためのURLが送られてきます。予約の際に選択できる場所によって、GABかC-GABかの見分けも可能です。
企業から受検案内やURLが送られてきた際は、すぐに一度アクセスして確認しましょう。予約が必要な場合、いち早く手続きを行わないと希望の時間に受検できない可能性もあります。
玉手箱とGABとC-GABに関するQ&A

それぞれの合格ラインは?
一般的な合格ラインとして、玉手箱は6〜7割、GAB・C-GABは6割程度と言われています。ただし、大手企業の選考突破のためには、玉手箱で8割、GAB・C-GABで7割以上必要とされています。
適性検査の各企業の合格ラインが公表されることはほとんどなく、年度や応募者数などによっても異なります。これらの指標はあくまでも目安と考え、まずは6割程度を目標に対策すると良いでしょう。
.webp)
3つとも検査結果の使い回しは可能?
結果の使い回しは、テストセンターで受検するC-GABのみ可能となっています。ただし、「C-GABの検査結果をGABの結果として使い回す」といったことはできません。あくまでC-GABを何度も受ける手間を省くための制度です。
C-GABは出題内容が1種類に固定されていることから、ピンポイントな対策で高得点を狙いやすい形式です。こうして一度高得点を取ることができれば、他の企業でも同じ結果を提出できるため、選考を有利に進められるでしょう。
玉手箱とGABに関しては、人の目による監視が無い・マークシートのため管理が難しいといった理由から、使い回しには対応していません。
SPIとは別物?
SPIと玉手箱の各種形式は全くの別物です。性格特性や基礎的な知的能力を測る点では同じですが、問題の出題内容に大きな違いがあります。
SPIでは長文や図形問題に加えて、語句の意味などを問うシンプルな語彙力問題や、短めの文章から計算を行う問題などが出題されます。玉手箱と比べて出題範囲が非常に広いことが特徴です。
一方、玉手箱やGAB・C-GABでは、狭い出題範囲を深く理解しておくことが求められます。「広く浅く」の対策を求められるSPIとは大きな違いです。
SPIと玉手箱は、どちらも就活において特に受検する可能性が高い適性検査です。玉手箱だけでなく、SPIの対策も欠かさないようにしましょう。
SPIと玉手箱はどちらが難しい?
SPIは様々な適性検査の中では中間的な難易度であり、特段難しい問題は出題されません。中学・高校レベルの問題が中心で、定型的な問題が多いです。
一方で玉手箱は、論理的思考や問題解決能力を問うことを目的としています。中学・高校レベルの知識で解ける点は同じですが、やや応用的な内容も出るため、対策不足だとボロボロになりやすいでしょう。
特に、従来型の玉手箱は企業によって出題内容の組み合わせが異なるため、対策が難しい傾向にあります。
また、SPIは各設問ごとに制限時間が設けられているのに対し、玉手箱は分野単位で制限時間が設定されています。そのため、時間配分を誤ると、後半の問題に手をつけられないまま終了してしまうこともあります。
このように、出題内容や時間管理の難しさから、玉手箱はSPIに比べて難易度が高いといえるでしょう。
玉手箱とGABとC-GABには大きな違いがある!
玉手箱・GAB・C-GABは、どれも総合職向けの適性検査として多くの企業で使われています。決して簡単な検査ではないため、それぞれの違いを正しく理解し、それに応じた対策を講じることが必要不可欠です。
また、就活では玉手箱以外の適性検査も受検する機会があります。特に、SPIは玉手箱以上の採用率を誇る適性検査であり、こちらも対策は必須です。
自分の志望企業がどの適性検査を実施しているかを早めに調べておき、自分に必要な対策を早期に始めましょう。


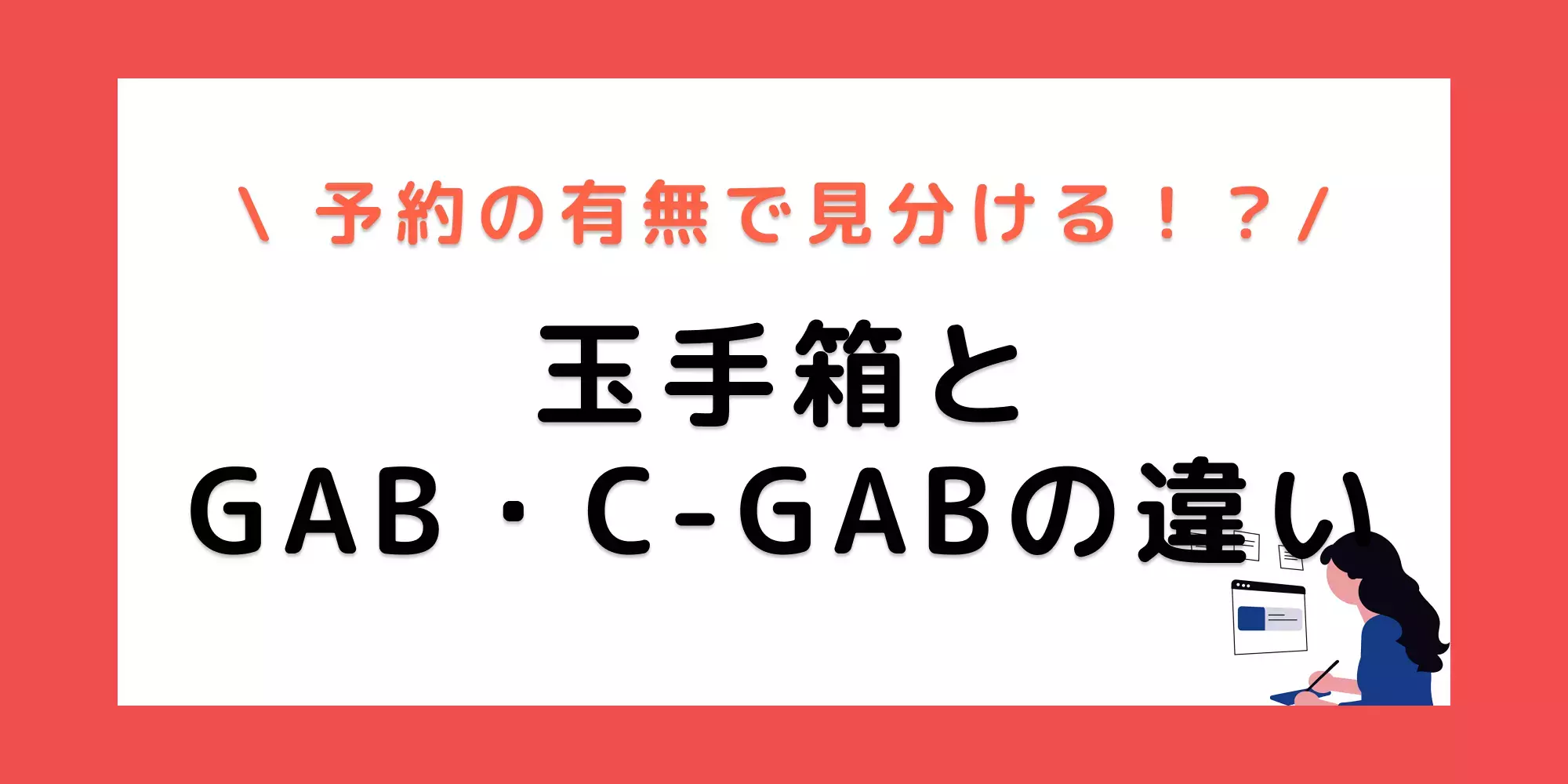


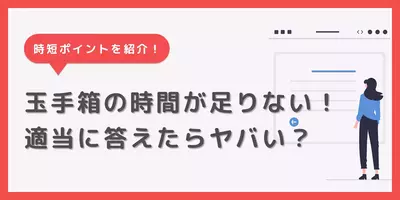
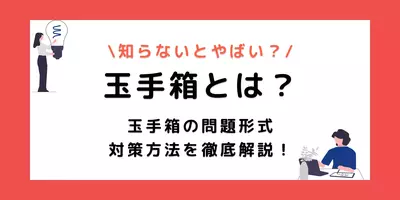
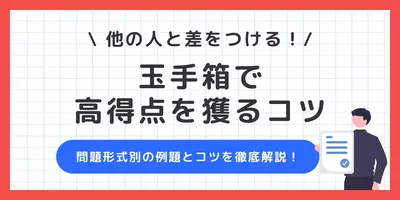
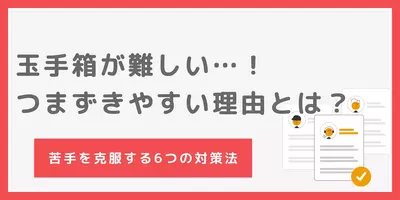
.webp)