玉手箱は多くの企業のWebテストで導入されている適性検査ですが、実は「監視型」と呼ばれる形式が存在します。
監視型では、カメラや画面操作の監視を通じて受検者の不正を防ぐ仕組みが採用されており、従来の玉手箱とは受検環境や注意点が大きく異なります。
形式を正しく把握しておかないと、思わぬトラブルに発展することも。本記事では、監視型玉手箱の概要や見分け方、受検前に確認すべきポイントについて詳しく解説します。
目次
玉手箱は監視型で実施される場合もある!
- 玉手箱(従来型): 自宅
- C-GAB: テストセンター(監視あり)
- C-GAB plus: 自宅(監視あり)
玉手箱は日本SHL社が提供する適性検査で、選考フローのひとつとして広く採用されています。
従来型の玉手箱はいつでもどこでも受検可能なWebテストですが、玉手箱の中にはC-GABやC-GAB plusといった監視型で実施されるものも存在しています。
従来型と監視型には様々な違いが存在します。形式の違いや見分け方などをあらかじめ頭に入れておくことで効率よく対策しましょう。
試験監督が巡回するC-GAB
C-GABは、テストセンターや企業の会場で受検する適性検査の一種で、試験監督が会場内を巡回しながら受検者を監視する形式が取られます。これは、カンニングや不正行為を防ぐための措置で、受検者の手元や周囲の様子までしっかりと確認されます。
受検中は私語やスマートフォンの使用は禁止されており、会場のルールに厳しく従う必要があります。紙や電卓の持ち込みにも制限があり、必要な場合は会場で貸し出しされる備品のみを使用する形になります。
このように、C-GABは試験監督によるリアルタイムの人的監視が行われることが特徴で、他のWebテスト形式と比べて、緊張感のある雰囲気の中で行われます。
AIと人間によって監視されるC-GAB plus
C-GAB plusは、Web上で受検する形式の適性検査ですが、AIと人間の両方による監視が行われるオンライン監視型テストです。試験中はWebカメラを常時オンにして受検状況が記録・監視されます。
AIは、視線の動き、周囲の環境の変化などをリアルタイムで検出し、不正の兆候があると判断された場合は人間の監督者が確認・対応する仕組みです。また、試験前には顔写真付きの身分証明書を使った本人確認が行われるなど、セキュリティは非常に厳格になっています。
監視型は自宅受検でもテストセンターでの試験と同等の厳しさがあるため、静かな環境を整え、ルールをきちんと守る準備が必要です。カンニングが疑われないよう部屋の中に余計なものは置かず、PCの性能や通信環境の確認も事前に行っておきましょう。
玉手箱の監視型の見分け方
- ・ 受検日時の予約を求められるか
- ・ URLが「e-exams」か
- ・ カメラの使用を求められるか
- ・ 電卓が使用可能か
- ・ 自分の姿が受検中に画面表示されるか
予約制かどうか
玉手箱が監視型で実施される場合、受検日時を予約する必要があります。そのため、企業から受検予約の案内が送られてきた場合、それは監視型の玉手箱である可能性が高いと認識しておきましょう。
予約を忘れると受検自体ができなくなってしまうため、忘れずに予約するようにしましょう。特に、就活の期間中は他の企業の面接や説明会などの日程が被ってしまうこともあるため、スケジュールは確実に把握しておくようにしましょう。

URLで見分ける
Webテストの受検にあたっては、まず企業から送られてくるメールに記載された専用のURLにアクセスし、そこから試験を受ける流れになります。
この時、テスト形式によってURLの内容が異なるため、URLを見れば試験の種類を見分ける手がかりになることもあります。
玉手箱では、日時予約の案内がなく、受検用URLに「e-exams」という文字が含まれていれば、監視のない通常型のテストである可能性が高いです。
C-GAB plusはカメラの使用を求められる
Webテストの場合、受検者の許可なくカメラで監視することはできません。そのため、受検時にカメラの使用を許可するように指示がある場合、監視型の試験である可能性が高いです。
監視型の玉手箱では、AIや試験官が不正行為を監視するため、パソコンのカメラを使って受検の様子をチェックします。
この点は、監視の有無を判断する上で非常に重要なポイントとなりますので、把握しておきましょう。
監視型は電卓が使用できない
監視型の試験では、ほとんどの場合、電卓の使用が禁止されています。そのため、試験案内で電卓の使用が許可されている場合、監視型ではない可能性が高いです。
従来型の玉手箱は電卓の使用に関する制限はありませんが、C-GABではペンと計算用紙のみが使用可能であり、C-GAB plusではペンと計算用紙すらも使用禁止となっています。
計算用紙すら使えないとなると、問題を解くのがかなり難しくなります。計数問題は自分が受検する形式の電卓の使用可否に合わせて対策するようにしましょう。

C-GAB plusは受検姿が画面に表示される
AI監視では受検中に自分の顔がリアルタイムで画面上に表示されます。
画面の片隅に自分の姿が映っていることで、常に見られている意識が生まれ、緊張感が高まる受検形式です。通常の玉手箱ではこのような表示はなく、画面には問題と回答欄しか表示されません。
もし受検中に自分の顔が表示される仕様になっていれば、それは監視型であると確定してよいでしょう。自分の受検姿が画面表示される場合は周囲に映り込むものにも注意が必要です。電卓やスマホなど使用が禁止されているものが映り込まないように注意しましょう。
玉手箱の従来型と監視型では何が変わる?
- ・ 受検場所が違う
- ・ 制限時間が違う
- ・ 出題内容が違う
- ・ 結果の使い回しの可否が違う
受検場所の違い
従来型の玉手箱は、自宅や大学など、インターネット環境さえあればどこでも受検できるのが特徴です。自分の都合に合わせて好きな場所で受検することができます。その一方で、監視型の玉手箱は、受検場所に制限が出てきます。
C-GABは企業指定の会場やテストセンターでの受検が一般的です。一方、C-GAB plusでは自宅からの受検が可能ですが、カメラとマイクによる監視が行われるため、周囲に私物が少なく、静かな個室の環境が推奨されます。
ただし、自宅に適した環境がない場合は、外部のレンタルスペースなど、監視要件を満たす別の場所を利用するのもおすすめです。
このように、受検環境の自由度は従来型の方が高く、監視型はより厳格な管理下で行われる傾向にあります。
制限時間の違い
玉手箱の従来型は、企業ごとに出題形式や問題数の組み合わせが異なるため、制限時間にもばらつきがあります。そのため、余裕のある設定の企業もあれば、短時間で処理を求められる企業もあり、一概に何分とは言い切れません。
一方で、監視型のC-GABおよびC-GAB plusは、「例題を合わせて45分」と固定された制限時間で実施されるのが特徴です。
玉手箱は全体的に時間配分が高得点獲得のカギとなりますので、自分の受検する形式に合わせて時間配分の対策も行いましょう。
出題内容の違い
| 従来型 | 言語/非言語/英語分野から組み合わせによって様々 |
| C-GAB | 言語/英語分野では長文読解のみ |
| C-GAB plus | 非言語分野は図表の読み取りがほとんど |
受検形式によって出題内容も変化します。従来型は言語、非言語、英語分野から組み合わせによって様々であるのに対し、C-GABとC-GAB plusでは言語、英語分野では長文読解のみが出題され、非言語分野は電卓を使用できないことから、複雑な計算が必要ない図表の読み取りが出題されることが多いです。
出題内容が違えば対策も変わってくるため、効率よく対策するためにも自分の受検する形式はしっかりと把握しておきましょう。
結果の使い回しの可否の違い
玉手箱の従来型では、企業ごとに個別に試験が実施されるため、基本的に結果の使い回しはできません。その都度、各企業の指定した形式や内容に従って受検する必要があります。
一方、C-GABやC-GAB plusといった監視型のテストでは、試験結果の使い回しが可能なケースが多いのが特徴です。これは、試験中にカメラや試験官による厳重な監視が行われ、不正のリスクが抑えられているため、信頼性の高いスコアとして他企業でも共有・再利用できる仕組みが整っているからです。
監視型の玉手箱で不正を疑われる行動
- ・ 解答時間が早すぎる
- ・ タブを複数開いている
- ・ 机の上が散乱している
解答時間が早すぎる
監視型テストでは、AIや試験官が解答のスピードにも注目しています。あまりにも短時間で複雑な問題に正解し続けると、カンニングをしたと判断される可能性があります。
特にC-GAB plusのような遠隔監視型では、通常の平均的な解答時間とのズレを自動で検知するシステムが導入されている場合もあります。そのため、スピードを意識することは大切ですが、不自然なほど速いペースで進めると、かえって不正を疑われかねません。
しかし、通常通りに解答していれば不正として検知されることはないので安心して臨みましょう。
タブを複数開いている
Webブラウザで受検する形式の場合、受検中に他のタブを開く行為は非常にリスクが高いです。これは、問題の答えを検索したり、別の画面でメモや計算を行っていたりする行動とみなされる可能性があるためです。
C-GAB plusのような監視型では、画面操作も監視対象となっており、タブの切り替えや不自然なマウスの動きはログとして記録されることも考えられます。
不用意に別の画面を開くだけでも、試験中断や不正扱いにつながる恐れがあるので、試験画面以外は一切開かないようにしましょう。
机の上が散乱している
監視型の玉手箱では、机の上の状況も重要な監視対象となります。特にC-GAB plusのようにカメラ越しに受検環境がチェックされる形式では、机の上に資料、メモ、スマートフォンなどが置かれていると、それだけで不正の可能性を疑われることがあります。
たとえ使っていなくても、周囲に参考になりそうなものが映り込んでいれば、試験官やAIの判断で試験中止や結果の無効化につながるリスクがあるのです。
このため、試験前には机の上を完全に整理し、許可された筆記用具や機材以外は一切置かないようにしましょう。「何もない環境で受ける」のが、監視型テストでは基本のルールです。
監視型の玉手箱を受検するときの注意点

持ち物の事前確認をする
C-GABを受検する際は受検票と本人確認書類が必須です。会場では配布されるメモ用紙とペンのみが使用を許可されており、それ以外の私物の持ち込みは認められていません。携帯電話や電卓などはすべて、試験開始前に専用ロッカーに預ける必要があります。したがって、受検票と本人確認書類さえ持っていれば、他に特別な持ち物は必要ありません。
C-GAB plusの試験ではカメラを使って顔写真付きの本人確認書類を提示します。運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどをあらかじめ準備しておきましょう。確認がスムーズに進まないと、試験開始に遅れが生じる可能性があるため、事前の準備をしっかり整えておくことが大切です。
また、電卓が使用できないため、メモや計算用に筆記用具を自分で準備する必要があります。ただし、試験によっては禁止されていることもあるので、事前にガイドラインを確認して適切に備えましょう。
怪しまれる行動をしない
監視型の玉手箱では、学校の試験と同じように、公平性を保つために不正行為に対する監視が非常に厳しく行われます。そのため、カンニングを疑われるような行動は絶対に避けるべきです。
視線を頻繁に左右に動かす、机の下に手を入れる、タブやアプリを切り替える、解答スピードが異常に早いといった動作は、AIや試験官に不審と判断される可能性があります。
一度疑われると試験中断や結果の無効化につながるリスクもあるため、受検中はカメラの前で正面を向き、落ち着いた姿勢で取り組むことが大切です。普段通りに解くことを意識し、不自然な動きは控えましょう。
受検環境を整えておく
監視型では、受検中の周囲の環境も評価の対象になります。部屋の照明が暗かったり、後ろに人の気配があったり、机の上が散らかっていたりすると、不正防止の観点から問題視される可能性があります。
カメラに映る範囲を事前に確認し、壁を背にして座る、不要な物は片付けるなど、できる限りクリーンな環境を整えておきましょう。音声による指示やマイクの使用があるケースもあるため、静かな場所を選ぶことも大切です。

監視型かどうかは事前にしっかり確認しよう!
玉手箱を受検する際は、その形式が監視型か非監視型かを事前に確認することが非常に重要です。監視型は、カメラや試験官による監視のもと実施されるため、事前準備や受検環境に厳しいルールがあります。
試験の予約が必要か、カメラ使用の許可を求められるか、URLに特定の文字列(e-exams)が含まれているかどうかなどが判断材料として挙げられます。
形式によって使えるものや解答環境が大きく異なるため、案内メールの内容を細かくチェックしておくことがトラブル回避の第一歩です。自分が受検する形式に応じた準備をしっかり整えて、落ち着いて本番に臨みましょう。
.webp)

.webp)


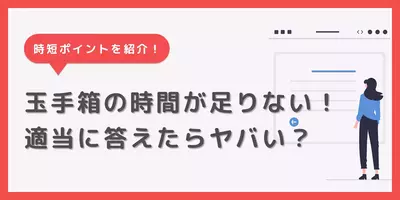
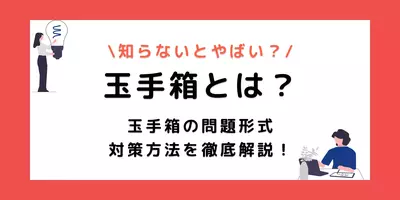
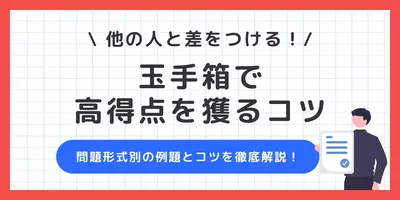
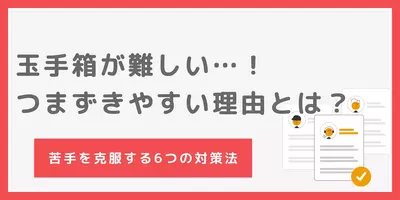
.webp)