玉手箱の英語は、出題頻度の低い科目です。しかし、出題される場合は「英語を重視する企業」という可能性が高く、なるべく高得点を取っておく必要があります。
今回は、英語問題の中でも「長文読解」についての基本や例題を紹介していきます。
読み取りに時間がかかる問題のため、「素早く読める」ようにする対策が必要です。就活中でも無理なくできる対策法や、意識するだけで一気に効率的になる解答のステップも見ておきましょう。
目次
玉手箱の英語問題「長文読解」とは?
玉手箱の英語で出題される「長文読解」は、200単語程度の英文を読んで質問に答える問題です。長文1つにつき3問ずつ出題され、全部で長文8個・24問を10分で解くことになります。1問あたりの時間は30秒以下であり、英語の基礎力に加えて速読力も試されます。
高校までの英語力があれば対応できるレベルですが、時間制限は厳しく、うろ覚えで対処するのは難しいでしょう。
問題文では、長文に関して「〇〇とは何か」 「正しいのはどれか」といった内容を問われます。問題文と選択肢も全て英語で表記されているので、長文以外の読み取りにも時間が必要です。
長文読解|例題と解答・解説
例題1
次の文章を読み、続く設問の解答を5つの選択肢の中から1つ選びなさい。
In the early 20th century, a remarkable movement began to challenge traditional gender roles in Japan. The ""New Woman"" or ""Atarashii Onna"" movement emerged as a powerful force for social transformation. Young women, often educated and from urban middle-class backgrounds, started rejecting conventional expectations of marriage, domesticity, and subservience.
These women cut their hair short, wore Western-style clothing, and pursued careers in writing, journalism, and education. Influential figures like Hiratsuka Raichō founded the first feminist magazine, ""Seitō"" (Blue Stocking), which became a platform for discussing women's rights, personal freedom, and societal change.
The movement faced significant resistance from conservative society. Many traditional families viewed these women as rebellious and threatening to established social norms. Despite facing criticism and social isolation, these women continued to push boundaries, demanding equal educational opportunities, workplace rights, and personal autonomy.
Their efforts laid the groundwork for future feminist movements in Japan. By challenging deeply ingrained cultural expectations, the ""New Woman"" movement demonstrated that social change is possible through individual courage and collective action.
【設問1】
What was the primary goal of the "New Woman" movement?
A: To promote Western fashion
B: To challenge traditional gender roles
C: To start a magazine
D: To encourage marriage
E: To support conservative social norms
【設問2】
Who founded the first feminist magazine in Japan?
A: A traditional family member
B: An urban middle-class woman
C: Hiratsuka Raichō
D: A Western journalist
E: A government official
【設問3】
How did the "New Woman" movement members typically express their independence?
A: By joining the government
B: By wearing traditional kimonos
C: By cutting their hair short and wearing Western clothing
D: By getting married early
E: By supporting conservative social norms
【設問1】
解答: B
設問文の意味は、「 『新しい女性』運動の主な目的は何でしたか?」
本文の最初の段落で、この運動が伝統的な性別役割に挑戦し、結婚、家事、従属的な期待を拒否したことが述べられている。正解は「To challenge traditional gender roles(伝統的な性別役割に挑戦する)」。
【設問2】
解答: C
設問文の意味は、「誰が日本で最初のフェミニスト雑誌を創刊しましたか?」
本文の第2段落で、「Hiratsuka Raichō」が最初のフェミニスト雑誌「青鞜」を創刊したと明確に述べられている。正解は「Hiratsuka Raichō」。
【設問3】
解答: C
設問文の意味は、「『新しい女性』運動のメンバーは、どのように独立性を表現しましたか?」
本文の第2段落に、彼女たちが髪を短く切り、西洋風の服を着て、キャリアを追求したことが記されている。正解は「By cutting their hair short and wearing Western clothing(髪を短く切り、西洋風の服を着る)」。
例題2
次の文章を読み、続く設問の解答を5つの選択肢の中から1つ選びなさい。
The concept of ""slow living"" has emerged as a powerful countermovement to the fast-paced, hyper-connected modern lifestyle. Originating in Europe during the late 1980s, this philosophy encourages individuals to consciously slow down and appreciate life's simple moments. Unlike traditional time management approaches, slow living is not about productivity, but about quality of experience and mindful engagement with daily activities.
Proponents argue that constant digital connectivity and rapid technological changes have fragmented human attention and increased stress levels. By deliberately choosing to do fewer things, but doing them with more depth and intention, practitioners of slow living seek to reclaim their time and mental well-being. This might involve preparing home-cooked meals, spending time in nature, reading physical books, or engaging in meaningful conversations without digital interruptions.
The movement has gained particular traction in countries like Italy, where the ""Slow Food"" philosophy originated, emphasizing local food production, traditional cooking methods, and community connections. From urban professionals to rural communities, people are increasingly questioning the value of constant busyness and seeking more balanced, intentional lifestyles.
【設問1】
Where did the "slow living" concept originally emerge?
A: The United States
B: Japan
C: Italy
D: Europe in the late 1980s
E: Australia
【設問2】
What is the primary goal of slow living according to the text?
A: Increasing productivity
B: Improving digital connectivity
C: Appreciating life's simple moments
D: Gaining more technological skills
E: Reducing work hours
【設問3】
How do practitioners of slow living typically approach daily activities?
A: By multitasking extensively
B: By doing fewer things with more depth and intention
C: By increasing digital connectivity
D: By working longer hours
E: By avoiding social interactions
【設問1】
解答: D
設問文の意味は、「 『スロー・リビング』の概念は最初どこで生まれましたか?」
本文の最初の段落に、この概念は「1980年代後半のヨーロッパ」で生まれたと明確に述べられている。正解は「Europe in the late 1980s(1980年代後半のヨーロッパ)」。
【設問2】
解答: C
設問文の意味は、「本文によると、スロー・リビングの主な目的は何ですか?」
本文では、この哲学が生活の簡単な瞬間を appreciateし、経験の質に焦点を当てることが強調されている。正解は「Appreciating life's simple moments(生活の簡単な瞬間を appreciate する)」。
【設問3】
解答: B
設問文の意味は、「スロー・リビングの実践者は、日常の活動をどのように行いますか?」
本文の第2段落に、「fewer things, but doing them with more depth and intention」(より少ないことを、より深さと意図を持って行う)というアプローチが述べられている。正解は「By doing fewer things with more depth and intention(より少ないことを、より深さと意図を持って行う)」。
長文読解|暗記以外の対策はある?
英語のニュースやSNSなどに目を通す
・ 英語のニュース
・ 海外のSNSの投稿
・ 英語系の試験や検定の過去問
英単語帳などを使った丸暗記をしなくても、長文読解の対策は可能です。英語のニュースやSNSなど、ネットですぐに読めるような英文を使って読解の練習をしてみましょう。
これらの英文は、専門性が高いものでなければ、理解しやすい語彙で書かれていることが多いです。内容もランダムなので、本番と近い感覚で英文を読むことができます。
わからない単語や言い回しがあれば、コピーしてすぐに検索できる点もメリットです。ただ暗記するよりも、実際に文章として読み、自分から調べた方が早く定着します。
ただし、SNSは公的な機関など、ある程度しっかりした文章を投稿しているアカウントだけを参考にするようにしましょう。個人のSNSは正しい文法で書かれていないことも多く、接続詞が省略されていたりします。
英文の基本構造だけでも押さえる
・ 主語+動詞で1セット
・ 段落の冒頭で結論が述べられやすい
・ 文末は時間や場所などの補足情報
・ 接続詞で流れが変わったりまとめに入ることが多い
英文では、各段落の最初に結論を述べる傾向があります。日本語でも「結論から始める」ということは珍しくありませんが、英文の方がより顕著です。
また、文頭に名詞が来ていれば、そこから大まかに「何についての記述をしている段落なのか」といったことを推測できます。問題文や選択肢と関連する語句が行頭にあれば、その段落だけを読むといったことも可能です。
その他にも、「時間や場所は文末で述べられやすい」 「固有名詞は頭文字が大文字になる」といった基本構造を押さえておくと、必要な記述を一気に探しやすくなるでしょう。
中学レベルまでの英語は知らないと厳しい
ここまで述べたように、暗記なしでも読解に慣れ、効率的な読み方を押さえることは可能です。しかし、中学レベルまでの基礎的な英語力がなければ、5割を超えることさえ厳しいといえます。
これらの対策は、あくまで「高校や大学受験の知識はうろ覚え」という状態から高得点を狙うための手段です。そもそも「英文がまったく理解できない」レベルでは、暗記を避けて高得点を取るのは現実的ではありません。
ただ、中学レベルまでの英語は簡単なので、復習すればすぐに思い出すことができるでしょう。基礎的な英語のテキストを読んだり、基本の語彙を暗記するだけでも、大きく伸ばせる可能性があります。
英語を出題する企業は、就活生の英語力をかなり重視していると考えるべきです。他の科目で補うことは難しいので、直前であってもできるだけ基礎の英語力を鍛え直しておくことをおすすめします。
長文読解|効率的な4ステップの解き方
- ① 長文と問題文は読解に同じだけ時間をかける
- ② 先に問題文と選択肢を読む
- ③ 問題に関する記述だけを探す
- ④ 読む時は行頭の主語に注目する
時間配分は長文2:問題文2:解答1が目安
長文読解の基本として、「長文1つにつき1分15秒」という時間設定を理解しておきましょう。長文1個に対して問題は3問なので「1問につき25秒」と捉えることもできます。
長文読解では、この短い制限時間を、読解と解答に上手く配分しなければなりません。
注意しなければならないのは、長文だけでなく問題文を読むことも必要になるという点です。これを知らずに「長文読解と解答に半分ずつ」と配分すると、問題文を理解するための時間が不足してしまいます。
そのため、1問につき「長文読解に10秒」 「問題文の理解に10秒」 「解答に5秒」という比率でペース配分をするのがおすすめです。
問題文と選択肢を先読みする
問題に取り掛かる時は、先に問題文と選択肢を読んでおくとスムーズに解答を進められます。
長文を全部読んでいると時間が不足するので、読み取りの際は「問題文と関連する文章」だけを読むことが重要です。問題文と選択肢から特徴的な語句を確認しておき、関連する記述を探しましょう。
特に、何かの固有名詞について問われている問題は探すのも簡単です。固有名詞の頭文字は大文字になっているため、長文の中でも見つけやすいでしょう。
行頭に注目して記述を探す
長文を読む時は、行頭で「主語は何なのか」を目印にすると効率的になります。英語の基本構造は「主語+動詞」であり、問題文で問われるのも「何か・誰か」についての内容が多いです。
主語の後にも文章は続きますが、そもそも主語が問題と関係なければ読む必要はありません。行頭だけに注目し、問題と関連のある語句を探していきましょう。
また、段落の最初はテーマとなる語句が使われやすい箇所です。段落ごとの冒頭で「何についての段落か」を確認してから読むのも良い方法です。
問いのパターンに注意して答える
- ① 「正しいもの・間違っているもの」を答える問題
→ 問題文に「true」「false」などが含まれる - ② 「〇〇とは何か」を答える問題
→ 問題文が「What」から始まる - ③ 「どうやって〇〇するか」「どれだけの数・量の〇〇か」
→ 問題文が「How」から始まる
長文読解で問われる内容にはいくつかパターンが決まっています。まず全パターンで頻出の言い回しとして、「According to~(長文によると)」 「statement(選択肢)」 「true(正しい)」 「false(間違っている)」の4つがあります。
正確な意味は異なりますが、問題で使われる際のニュアンスとして、上記のような覚え方をした方が理解がしやすいです。この4つの語句を押さえた上で、よくある3つのパターンを見ていきましょう。
まず、「正しいもの・間違っているもの」を問われる問題では、問題文に「true・false」などが含まれます。長文の中から、完全に一致する記述や、正反対の記述を探すことが必要になります。
2パターン目の「〇〇とは何か・何をするものか」という問題は、問題文が「What」から始まることが特徴です。こちらも完全一致の記述がある場合が多く、比較的答えやすい内容でしょう。
最後に、「どうやって〇〇するか」を問われる問題は「How」から始まります。例外として「How much」から始まっている場合は、「どれだけの〇〇か」といった量や値段を問われていると考えましょう。
こちらは名詞+動詞の組み合わせを長文中から探す必要があるため、問題文で趣旨となる名詞を見つけておくことが重要です。

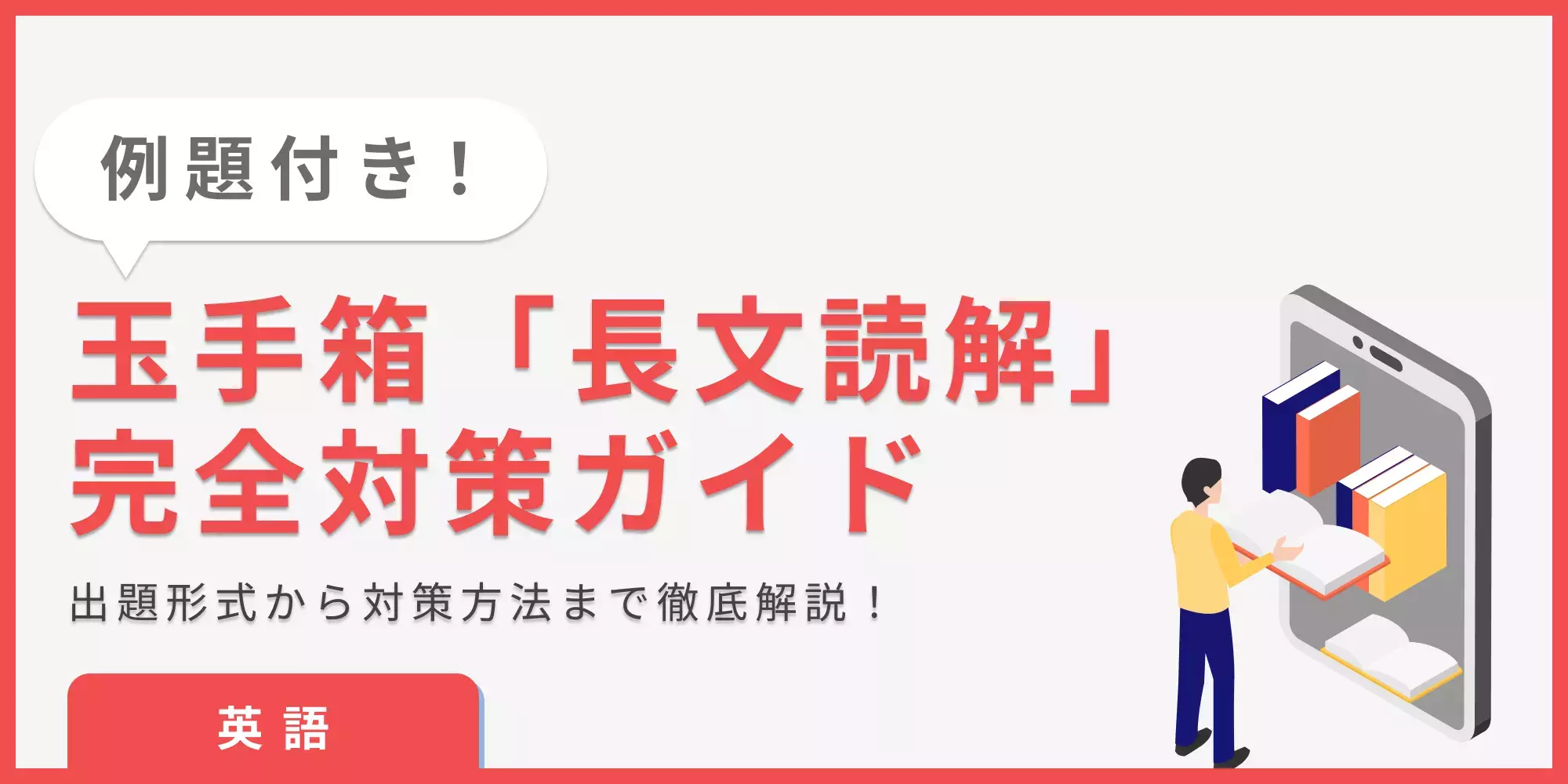


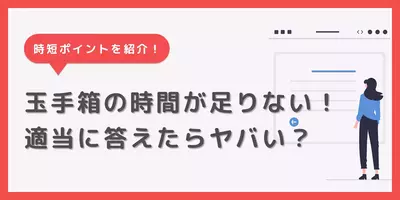
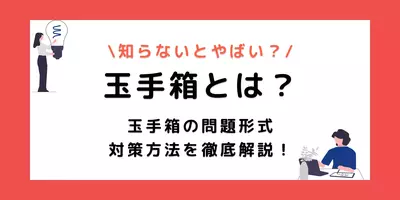
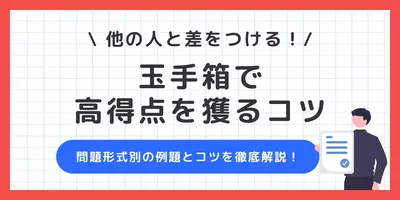
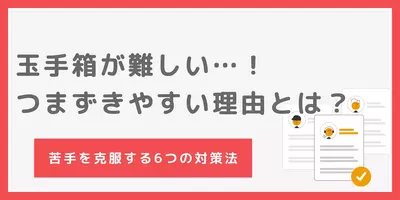
.webp)