
【適性検査CABとは】IT系必見!全科目の例題付きで対策法を解説 | SPI対策問題集
CABはパソコンに関する業務の適性を測るための検査で、IT系を中心に様々な企業で採用されています。SPIなどの適性検査とは問題が大きく異なり、しっかり対策しなければほとんど解けない可能性もある内容です。
この記事では、CABの科目と受検形式・実施企業例などの基本を紹介します。さらに、全科目の練習問題付きで対策法も解説しているので、早くから対策を始めたい方はぜひ参考にしてください。
目次
IT系で頻出の適性検査「CAB」とは?
数的処理能力を試される問題が出る
| 科目 | CAB | Web-CAB |
| 暗算 | 50問/10分 | 5問/9分 |
| 法則性 | 40問/15分 | 30問/12分 |
| 命令表 | 50問/20分 | 36問/15分 |
| 暗号 | 39問/20分 | 30問/16分 |
| 性格検査 | 68問/30分 | 68問/30分 |
CABは能力検査と性格検査に分かれており、能力検査は「暗算・法則性・命令表・暗号」の4科目です。
どの科目も他の適性検査における「非言語」や「計数」に近い内容で、数的処理の能力を問われるものになっています。
単純な計算問題は暗算のみで、その他の3科目では論理的な思考力や観察力も必要になります。数学とは異なる考え方が求められるので、「理系だから問題ない」「数学は得意」と考えていても対策は必須です。
CABは比較的メジャーな適性検査であり、対策方法も充実しています。志望企業で実施されることがわかったら、すぐに対策を始めましょう。
IT系を中心にメーカーやインフラ系でも実施
- アイシン・インフォテックス
- カプコン
- 東京ガスiネット
- 富士通
- 旭化成
- 東急
CABは主にIT系の企業で実施されることが多い適性検査です。その他にも、メーカーやインフラ系の企業でも実施事例があります。
プログラマーやSEといった特定のポジションでのみ実施されるというケースも多く、その分だけ重要度は高めといえます。
また、SPIや玉手箱など他の適性検査と複合して実施する企業もあります。この場合、数的能力はある程度重視しつつ、総合的な能力も測りたいという狙いが予想できるでしょう。
会場受検のCABと自宅受検のWeb-CABがある
- CABはペーパーテスト、Web-CABはWebテスト
- CABの方が制限時間と問題数が若干多め
- Web-CABの方が実施されやすい
CABは受検形式によって名称が異なります。ただ「CAB」とだけ表記されるのは会場でマークシートを使って解答する形式を指します。
一方、自宅のパソコンを使ってWeb上で受けるものを「Web-CAB」と呼び、こちらの方が実施されやすい傾向にあります。
CABもWeb-CABも、出題内容自体に大きな差はありません。CABの方が少しだけ制限時間が長く、問題数もその分だけ多いという程度です。
そのため、CABもWeb-CABも共通の対策で対応できます。対策本や練習サイトについても、「CAB」と表記されていればWeb-CABにも活かせる内容と判断できるでしょう。
適性検査の中でも難易度は高め
CABの問題は、様々な適性検査の中でも難易度が高めです。暗記や感覚で解ける問題がほとんどなく、どれも知識を付けた上でしっかり考えて答えを導く必要があります。
ただし、「練習してもわからない」というレベルの難易度の問題は出題されません。対策を行えば苦戦はしない内容になっているので、継続的な勉強で差がつく適性検査といえます。
また、CABの実施企業はそもそも倍率が高い人気企業であることも多いです。そのため、難しい問題であっても高い正答率を出すことが求められます。
目安として、7割程度の得点が取れれば、多くの企業を安定して突破できるでしょう。
【科目別】CABの例題
暗算の例題
【例題】
546-292+150=
<選択肢>
- 504
- 404
- 354
- 654
- 1054
引用:一般常識一問一答.com
暗算は、簡単な四則演算を行う問題です。選択肢から合っているものを選ぶだけなので、四捨五入や端数の切り捨てでざっくり計算するのがポイントです。
また、大きな数字や小数点・分数が含まれる問題もあります。その場合は計算しやすい桁に直すなどの操作で、一度シンプルな数字に置き換えると素早く計算できます。
Web-CABでは暗算のかわりに「四則逆算」という問題が出題されます。こちらは既に成立している式の中にある、空欄に当てはまる値を答える問題です。
基本的には暗算と同じ計算問題ですが、「空欄を片方の辺に残す」などの式の変形も求められます。計算が複雑になりやすい分、電卓が使用可能なため、総合的な難易度に大きな違いはないでしょう。
法則性の例題
【例題】
?に推測される図形をA~Eから選びなさい。
引用:一般常識一問一答.com
法則性は、図の並びから変形・回転・移動・拡縮といった変化のパターンを見つける問題です。その場で考えるよりも「頻出パターンのどれに当てはまるか」を見た方が正解しやすい内容になっています。
図の並びは特に法則性のない変化も含む場合があり、どれがパターンに従った変化なのかを見極めることが重要です。
例題のような丸や三角といった図形の他に、折れ線を使った問題もあります。こちらは一部分の回転や移動といった変化のパターンはある一方、拡縮はほとんど使われません。図形と折れ線の2パターンについて、変化の種類を把握しておきましょう。
命令表の例題
【例題】
命令表に記載された命令を上から順番に実施する。
この結果として得られる図形群は選択肢A~Dのうちのどれか。
特定の記号(命令)を通過した図形がどう変化するのかを見て、最終的に得られる図形を答える問題です。反転や回転といった図形単体の操作に加え、入れ替えや他の命令の変更といった命令もあります。
法則性の問題に近いですが、こちらは変化の内容を推測する必要がありません。命令の内容や、組み合わせた時の挙動を冷静に考えれば正解できる問題です。
問題文には独特な図形が何個も並ぶので、集中していないと頭に中々入ってきません。全体を一気に把握するのではなく、1つ1つの命令や図形を理解していくことが重要になります。
暗号の例題
【例題】
正方形の中の図形が円形の暗号にしたがって、下図のように変化している。
(1)空欄となっている図形にふさわしいものは選択肢A~Eのうちのどれか。
(2)空欄となっている図形にふさわしいものは選択肢A~Eのうちのどれか。
(3)空欄となっている図形にふさわしいものは選択肢A~Eのうちのどれか。
暗号は、矢印や記号を通過した図形が最終的にどう変化するのかを答える内容です。最初に提示される変化の法則から、それぞれの記号の意味を絞り込んでいくことがポイントになります。
全て暗記しながら進めるのは厳しいので、記号ごとに図形がどのように変化したかを余白に書き出して考えてみましょう。それぞれの操作が整理できれば、法則性や命令表の問題と似た感覚で解くことができます。
図形の変化パターンは拡縮や回転・色の反転や全く異なる図形への変化などがあります。いずれもその図形だけに影響するものであり、複数の図形と組み合わさるようなことはありません。
目標は7割!CAB対策の進め方
CABの出題企業は人気企業であることが多く、合格の目安となるボーダーラインも高めの傾向にあります。安定して突破するためには、7割以上の得点が必要になるでしょう。ここからは、高得点を狙うCAB対策の進め方を5つの段階に分けて解説します。
①自分に合う対策本を1冊用意する
②出題傾向を理解する
③科目ごとの解答ペースを覚える
④苦手科目から伸ばす
⑤性格検査のために自己分析も忘れない
①自分に合う対策本を1冊用意する
CAB対策の第一歩は、使う対策本を1冊に絞ることです。良い成績を取りたいからといって何冊も対策本を買っても、効率的な勉強はできません。解説のスタイルや問題数などが自分に合ったものを1冊だけ選び、集中して使い込むことが重要です。
CABは出題科目が固定されているため、収録されている問題に大きな幅はありません。「問題と解答を見開きで読める」「問題数が多い」などの点に注目して、使いやすそうなものを選びましょう。
また、なるべく発行年度が新しい対策本を使うことがおすすめです。最新の出題傾向に対応しているため、より本番に近い形式の問題を解くことができます。中古で安く済ませたい場合でも、1~2年程度前までのものに限定しましょう。
②出題傾向を理解する
対策本を用意できたら、まずは問題を一通り解いてみましょう。ここでは正答率は参考程度に捉え、「問題に触れておく」という点を重視するべきです。
本番と全く同じ問題数まで解く必要はなく、出題傾向を理解するために数問解けば良いでしょう。さらに、大まかに「難しかった問題」「解き方もわからなかった問題」などをメモしておくと、今後の対策も進めやすくなります。
特に、法則性と暗号は初見だと解けないことも多い問題です。この段階で全くわからない問題があっても気にせずに、課題が絞り込めたことをポジティブに捉えましょう。
③科目ごとの解答ペースを覚える
- 暗算:12秒(CAB)/25秒(Web-CAB)
- 法則性:20~25秒
- 命令表:20~25秒
- 暗号:25~30秒
- 性格検査:25秒
科目1つ1つの対策に移る前に、まず科目別の時間配分を覚えておきましょう。30秒以上かけられる問題がないシビアな時間設定になっているため、適切な解答ペースを知らないとまず解き終えることができません。
CABの問題は全て選択式であり、未解答で終わるよりも当てずっぽうで答えておいた方が正解する可能性があります。そのため、科目ごとの細かな知識よりも、それぞれの時間配分を優先して覚えた方が得点に繋がりやすいです。
こうした時間の感覚は、体感で覚えられるのがベストです。検査中に時間を確認することはできますが、問題から目を離すこと自体がタイムロスといえるでしょう。
「そろそろ〇秒経つから適当に答えて進もう」と判断できるようになれば、安定したペースで解答を続けられます。
④苦手科目から伸ばす
ここまでの基本を押さえたら、次は科目別の対策に移ります。最初は苦手科目から取り組み、最後に残った期間で他の科目を仕上げるのがおすすめです。
取り組みやすい得意科目から始めてしまうと、苦手科目が苦手なまま残ってしまう可能性があります。得意科目で高得点を取っていても、苦手科目がボロボロだと良い評価は得られないでしょう。
また、CAB対策は誰でも完璧に仕上げられるわけではありません。ほとんどの人は、忙しいスケジュールの合間にできる限りの勉強だけして臨むことになります。そのため、苦手科目だけでも潰しておき、他の科目は「余裕があれば対策する」と考えておきましょう。
⑤性格検査のために自己分析も忘れない
性格検査も忘れずに対策しておきましょう。能力検査ほど長期間の対策は必要ありませんが、最低限の自己分析はしておくべきです。
自己分析で得た結果は、性格検査だけでなく面接などにも活かせます。面接からCABという順序で実施される場合は、面接対策の段階で性格検査を見越した自己分析をしてみると良いでしょう。
性格検査で重要となるのは、一貫した回答です。自分を良く見せられる答えではなく、素直な答えを最後まで続けることが重要になります。自己分析で「自分はどんな性格なのか」を掴んでおけば、本番で迷いなく自分らしい回答を選べるでしょう。
CABの練習方法3選
対策本を使うのが基本!

出典:Amazon
CAB対策の基本は対策本です。解説のボリュームが充実しているので、1冊だけで対策を完結させられます。
問題の基本から練習問題まで流れで確認でき、「何から始めればいいのかわからない」と悩むことがありません。ただ対策本を1週するだけでも十分に力をつけられるでしょう。
ただし、対策本を使った練習はまとまった時間がないと取り組みにくいというデメリットもあります。他の練習手段を補助として使うことも検討してみましょう。
無料の練習問題サイト
無料でCABの練習問題に挑戦できるWebサイトを使えば、外出中でも隙間時間に対策を進められます。
中でも、キャリアワールドは自動生成の問題を実戦形式で解くことができるため、繰り返しの学習にもおすすめです。手書きのメモ機能も付いており、本番に近い感覚で解答できるでしょう。
CABでは1問あたりにそれほど時間がかからないので、まとまった時間がなくてもWebサイトで手軽に練習できます。暇な時間にスマホからアクセスして、少しずつ試してみるだけでも得点に繋がります。
専用のスマホアプリもおすすめ

出典:App Store
CAB対策に特化したスマホアプリは、見やすさや操作性が高いため快適に対策できるのが魅力です。CABは他の適性検査ではあまりみられない問題も多いので、専用のアプリを選ぶようにしましょう。
CAB(WEB-CAB) 一問一答では、CABの問題を全て無料で解くことができます。暗算がCAB形式の「四則演算」とWeb-CAB形式の「四則逆算」に分かれており、どちらにも対応可能な点が特徴です。
知っておきたいCABの豆知識
GABやSPIとは別物
CABはGAB・SPIと同じ「適性検査」の一種ですが、どれも全くの別物です。性格検査が行われる点は共通していますが、能力検査の内容は大きく異なります。
GABやSPIを含む、多くの適性検査では「言語」「非言語(計数)」「英語」が出題されることが多いです。総合的な能力を測ることを重視しており、主に総合職向けに実施される傾向にあります。
一方、CABでは「非言語」にあたる問題しか出題されないので、言語や英語の能力は測られません。こうした点から、数的能力を求められるIT系の企業で実施されることが多いのです。
過去の実施状況は調べられる
志望企業が過去に何の適性検査を実施していたのかは、ネット上で調べることができます。「企業名 CAB」や「企業名 適性検査」と検索すれば、就活サイトなどで過去の応募者の体験談が確認できるでしょう。
ただし、こうしたネット上の情報が必ずしも正しいとは限りません。虚偽の情報が含まれているおそれや、情報が古い可能性もあります。しかし、最新に近い日付で、多くの人が同様のことを書き込んでいれば、信憑性は高いと判断できます。
なるべく複数サイトで情報の擦り合わせをして、正誤を確かめましょう。対策する適性検査を間違えると勉強時間が無駄になってしまうので、慎重に見定めることが重要です。
CABではIT系のポテンシャルを測るだけ
CABはIT系の企業での実施が多いですが、プログラミングやシステム面での知識などは求められません。これは、CABが「技能習得のポテンシャル」を測る適性検査であるためです。
新卒の場合、ほとんどの学生は専門知識が不足した状態で入社することになります。入社後に必要な技能を学んでいく時になって、IT系に向いていないことが発覚するのは就活生と企業の両方にとって避けたい事態です。
募集要項として最低限の技能が求められる場合もありますが、少なくともCABの問題で問われることはありません。
難易度の高いCABは早めに対策を始めよう
CABは適性検査の中でも難易度が高めで、合格水準も厳しい傾向にあります。IT系は能力重視であることも多いので、高得点を取っておいて損はありません。
また、CAB対策は一夜漬けや詰め込みでは十分な成果に繋がりません。コツコツと勉強を続けて知識を定着させることで、初めて力になります。
早い段階からCAB対策を始め、志望企業の選考突破を目指しましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen













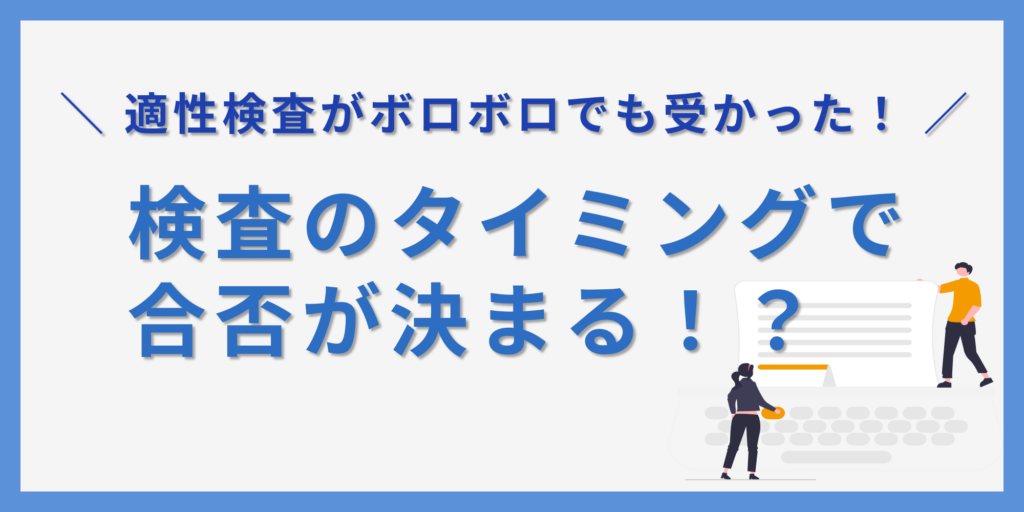 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?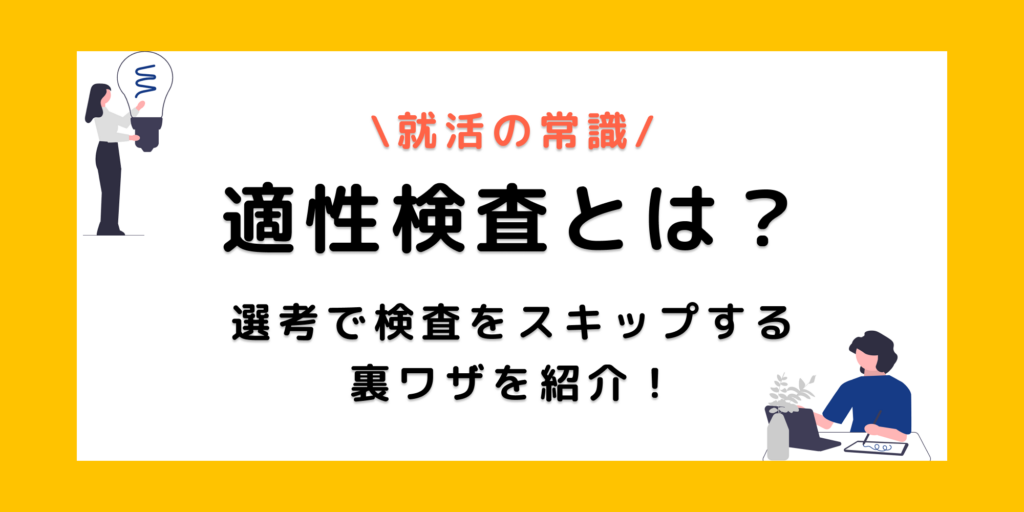 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!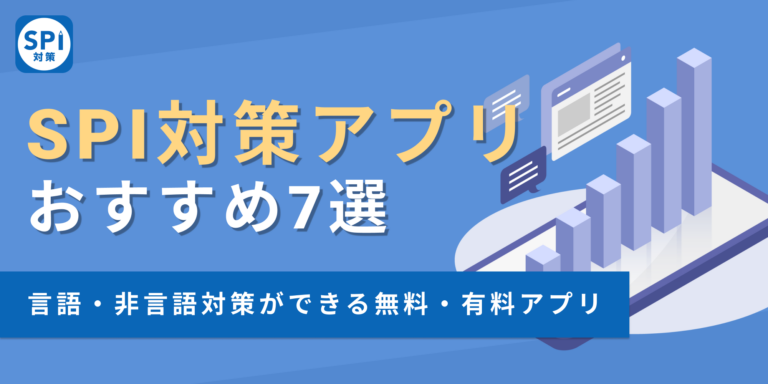 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ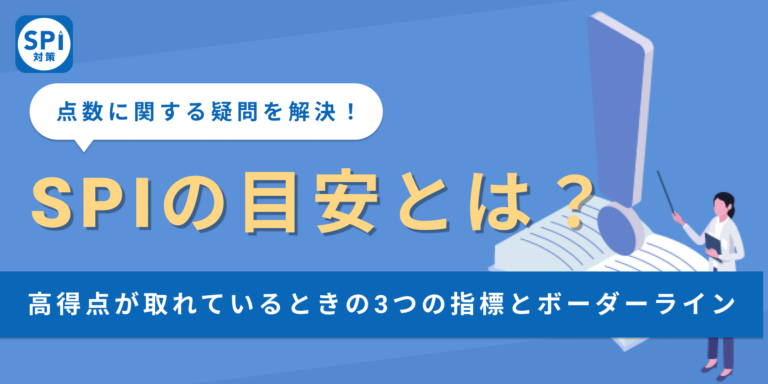 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点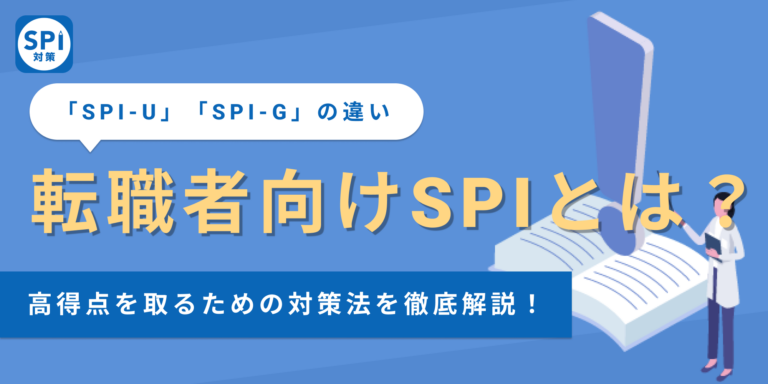 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説