
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!? | SPI対策問題集
SPIなどの適性検査で思うように解けず、「もう終わった…」と感じたことはないでしょうか。
しかし、実はそのような状態でも内定を勝ち取った人はたくさんいます。検査の実施タイミングや、企業が重視するポイント次第で結果は変わるのです。
本記事では、適性検査がボロボロだったのに受かった人たちの体験談をはじめとして、合否が分かれるポイントや「失敗しても大丈夫」なタイミングなどを紹介していきます。
2回目以降のSPIで挽回するために最速で仕上げる対策法も解説しているので、前向きに対策を進めていきましょう。
目次
適性検査がボロボロだった人の体験談
受かった人の体験談
「SPIで全然手ごたえがなかったけど、なぜか次の選考に進めた」という声は意外と多いです。ある就活生は非言語問題が全滅状態で、「多分落ちた」と感じながらも、なぜか通過しています。
能力検査がボロボロだったのにもかかわらず通過できたのは、企業が性格検査をメインに見ていた可能性が高いです。
つまり、言語や非言語のスコアは参考程度に、面接での印象や人柄を評価されたということです。
落ちてしまった人の体験談
ボロボロでも受かった人とは反対に、「ボロボロだったせいで落ちた…」という例もあります。SPIにノー勉で挑む学生もいますが、全く対策をせずに受かるほど甘くはありません。
自分にとっては難しくても、しっかり対策してきたライバルにとってはそれほど難しくないという可能性が高いでしょう。大きな差が開き、選考で不利になることは避けられません。
結果がボロボロだったからといって必ず落ちるわけではないですが、最低限の勉強は必要です。志望度の高い企業であれば、手は抜かずに対策しておきましょう。
ボロボロでも受かる人と落ちる人の違いは何?
- 足切りラインが低かった
- 実はそこまで低いスコアではなかった
- 性格重視の企業だった
企業の合格基準(足切りライン)が低かった
企業によっては、SPIのスコアを重視しないところもあります。
特に中小企業や専門職では、学力テストよりも人物評価を優先することもあり、「とにかく最低限ができていればOK」と考える企業も少なくありません。
つまり、適性検査の結果が悪くても面接や書類の内容でカバーできる可能性があります。
大手企業ほどSPIを重視する傾向がありますが、すべての企業がそうではないので、1回の失敗で諦める必要はないのです。
実はそこまで低いスコアではなかった
「全然できなかった」と思っていても、実際には平均点を下回っていなかったケースもあります。
例えば、SPIは相対評価なので、受検者全体の中で見ると意外と正答率が高く、そこまで悪い結果ではないこともあるのです。
得意な分野で点数を稼げば、全体の評価が底上げされる仕組みです。「ボロボロだった」という思い込みだけで落ちたと決めつけず、まずは冷静にほかの部分も振り返ってみると良いでしょう。
企業が性格検査を重視していた
SPIには学力問題だけでなく、性格検査も含まれています。中には、この性格検査を重視している企業も多くあります。
人柄や価値観が社風と合っていれば、多少学力試験のスコアが低くても合格できることがあるのです。
例えば、協調性や責任感、柔軟性などが求められる職場では、数値ではなく性格の傾向を優先することもあります。
だからこそ、SPIの勉強だけでなく、自分の考え方や行動の一貫性も見直しておくと安心です。
履歴書・エントリーシートの内容が魅力的だった
SPIの点数が不安でも、エントリーシートや履歴書の内容がしっかりしていればカバーできることがあります。
例えば、採用担当者の印象に残る具体的なエピソードを書いた場合や、志望動機が採用担当者の心を打った場合、企業側が「この人と面接で話してみたい」と思ってくれる可能性があるのです。
選考は総合評価なので、どこかひとつの項目が弱くても、他の強みで挽回することは十分に可能です。
逆に、内容が薄くて印象に残らないと、SPIの点数で判断されてしまうこともあるため、書類作成は丁寧に行いましょう。
実は面接後の適性検査なら失敗しても大丈夫!
選考や一次面接前の適性検査は足切りに使われがち
エントリーしてすぐにSPIを受けさせる企業は、その結果で応募者をふるいにかけている可能性があります。つまり、SPIが面接より前にある場合、それが「足切り」として機能しているケースが多いのです。
特に大手企業やエントリー数が多い企業では、選考を効率化するためにSPIの点数で自動的にふるい落とすことがあります。
そのため、スコアが低すぎると、どれだけ履歴書や志望動機が良くても選考に進めないという結果になりやすいです。
SPIを受けるタイミングが早ければ早いほど、対策しておく必要があります。
面接後の適性検査なら参考程度!
一方で、一次面接や最終面接のあとに実施される適性検査は、そこまで結果を重視しないことが多いです。
すでに人柄や志望動機、ビジネスマナーなどが評価されたあとに受けるので、企業側は「最終確認」のような形でSPIを使っている場合があります。
例えば、数値的に問題があっても「面接の印象が良く、人柄が社風に合っていたからOK」と判断されることもよくあります。
つまり、面接後のSPIはあくまで参考材料であって、結果だけで不合格になることはあまりありません。だからこそ、面接にしっかり集中することが大切なのです。
結果に落ち込まずポジティブに挑戦するのが重要
適性検査がうまくいかなかったからといって、自分のすべてが否定されたわけではありません。
就活はいわば企業とのお見合いです。1つの企業のSPIがダメだったとしても、別の会社では評価されることもあります。
「あの企業とはご縁がなかった」と前向きにとらえ、自分に合う会社を探し続けることが大切です。
不安になるのは当然ですが、落ち込んだ分だけ成長できるチャンスもあることを覚えておきましょう。
適性検査の得点を最速で伸ばす方法
参考書は赤本1冊だけに絞る

出典:Amazon
- 初めてSPIの勉強をする
- 幅広く出題範囲を勉強したい
- SPIを受検するまで時間がある
SPI対策用の参考書はたくさんありますが、あれもこれもと手を出すと逆に混乱してしまいます。おすすめは、赤本などの定番問題集をひとつに絞って、それを徹底的にやり込むことです。
繰り返し解くことでパターンを覚え、回答のスピードも上がっていきます。初めは間違えても大丈夫です。
大切なのはひとつの問題集を何周もすることで出題傾向をインプットし、本番で焦らず取り組めるようになることです。
間違えた問題・苦手分野を重点的に解き直す
全体をまんべんなく解くのではなく、自分が間違えた問題や苦手な単元に時間をかけるほうがスコアアップにつながります。
間違えた問題は、ノートやアプリでまとめて管理しておくと、復習しやすくなります。
同じミスを繰り返さないようにするためには、原因を理解し、納得するまで練習することが大事です。
苦手分野を把握して対策することで、限られた時間の中で正答率を高められます。無理に完璧を目指さず、まずは「できなかったところ」を重点的に攻略していきましょう。
時間内に解き終えるようにスピードアップ
SPIは時間との勝負です。時間切れで本来答えられた問題を落とすのはもったいないので、時間配分を意識しましょう。もちろん時間配分を意識するのは、問題を解くのに慣れてからで構いません。
例えば、タイマーで測りながら1問1分以内で解くプレッシャーを感じながら勉強をすると、自然とスピード感が身についてきます。分からない問題に時間をかけすぎず、あえて飛ばす判断も大切です。
慣れてくれば、問題の優先順位を見極めて効率的に解けるようになるでしょう。
嘘を付かず等身大のあなたで勝負しよう!
適性検査を受ける際は取り繕わず、等身大のあなたで挑みましょう。
SPIには学力検査に加えて性格検査が含まれており、「こう答えたほうが印象がいいかも」と自分を大きく見せてしまいがちです。
しかし、無理に自分を偽るのは逆効果です。企業は回答の一貫性やあなたの素直な価値観を見ています。
例えば、「ひとりで作業するのが得意」と思っているのに、「集団で行動するのが好き」と答えると、矛盾が生じてしまいます。こうしたズレが積み重なると、「嘘の回答をしている」と判定されることもあるのです。
自分自身の等身大の姿をアピールすることで、企業とあなたの相性がうまくいく可能性が高くなります。
合わない会社に無理に入るより、自分に合った場所で活躍できたほうが長く働けます。だからこそ、性格検査では嘘をつかず、自分の考えや行動パターンに素直に向き合ってみみましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen














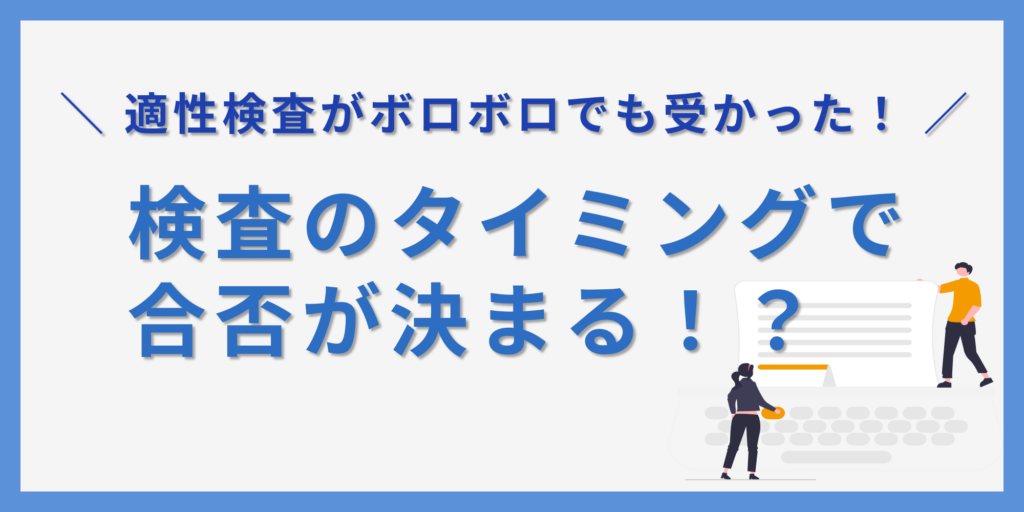 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?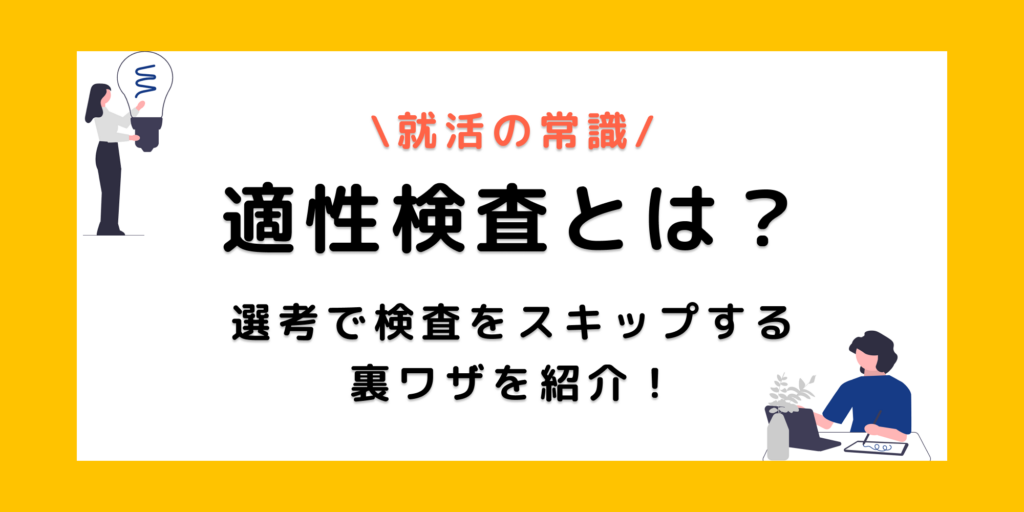 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!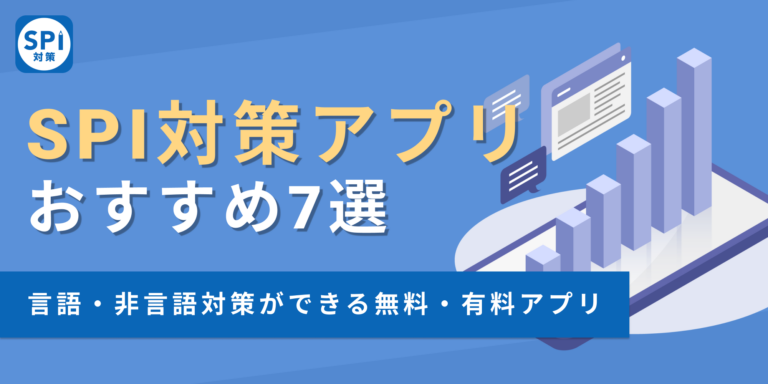 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ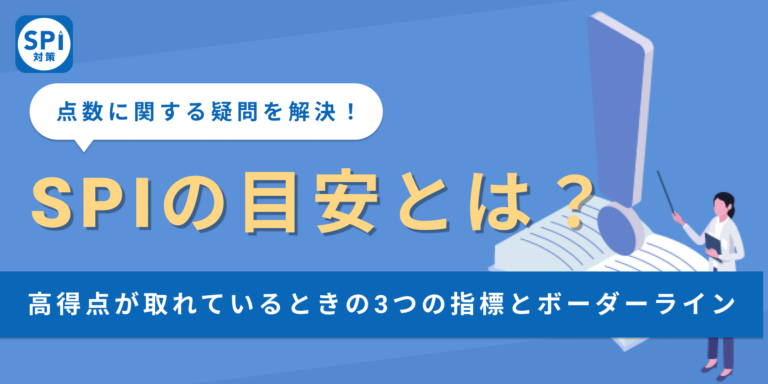 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点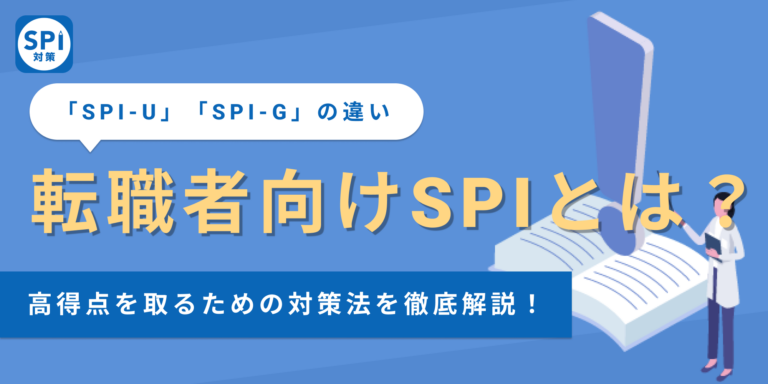 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説