
SPIの足切りラインは何割?【人気企業を受ける人は必ず読んで!】 | SPI対策問題集
SPIには足切りラインが存在しています。これは、どれだけ面接やエントリーシートが良くても、SPIで一定の点数を取れていなければ、それだけで選考から外れてしまうという厳しい基準です。
特に大手や人気企業では、他の応募者と比べて相対的に高い得点が求められる傾向があります。
本記事では、足切りラインの目安や、確実に回避するためのポイントをわかりやすく解説します。
目次
SPIで足切りされることはある!
- どの企業でも6割以上はとっておいた方が良い
- 大手や人気企業は7割以上がマスト
- 転職者向けのSPIはラインが低くなる
6割を下回っていると切られやすい
どの企業を受けるにしても、SPIでは最低でも6割以上の得点を確保しましょう。6割未満では、たとえ他の選考で好成績を収めていても、足切りされてしまう可能性が高くなります。
SPIを初めて受ける就活生は、問題形式に慣れるだけでも時間がかかるため、事前の対策は欠かせません。市販の問題集や模試を活用して、実践力を高めておくことが大切です。
また、同じ6割でもギリギリではリスクがあるため、7割以上をゴールに対策を進めるのをおすすめします。余裕を持って対策を始めることで、SPIを通過する確率を高めましょう。
人気企業では7割以上が必要
JALやパナソニックといった大手の人気企業を志望する場合、SPIでの合格ラインは7割以上が一般的とされています。
人気の企業は応募者数も非常に多いため、適性検査での選別は厳しくなりがちです。
SPIでの得点が高ければ高いほど、面接などの次の選考段階に進むチャンスが広がります。逆に、7割を下回ってしまうと、書類や面接での評価が良くても足切りにされることがあるということです。
特に、外資系やコンサル・メーカーの人気職種では、SPIでの高得点獲得が事実上の通過条件となっていることもあります。
志望する企業が大手や人気企業であるほど、徹底的な準備を心がけましょう。
足切り基準は公開されない
企業の設けている足切りの基準は、公開されないことが一般的です。選考を通過した人の情報から、大まかなボーダーラインがわかっているだけに過ぎません。
こうした情報が必ず正しいという保証はない上に、年度によって足切りラインが変わる可能性もあります。
そのため、「この企業なら〇割取れるようにしておけば安心」といった思い込みは危険です。足切りギリギリで超えるのではなく、なるべく高い点数を取れるようにしておく必要があります。
企業が足切りをしているか判断する目安
- 志望者の数が多い人気企業
- 選考の中に適性検査が複数回実施される
- 特定の科目の点数に着目している
志望者が多いか
SPIによる足切りが最も明確に行われるのが、応募者数の多い人気企業です。
大手商社・外資系・有名メーカー・金融機関などは毎年膨大なエントリーがあるため、書類選考や面接の前にSPIで人数をある程度絞ることが一般的です。
たとえ履歴書やESの内容が優れていても、SPIで足切りの基準を下回ると不合格になることがあります。企業側にとっては、効率よく優秀な人材を見極める手段として、SPIは非常に便利なのです。
人気企業を志望する人は、SPIが選考の中で形式的に行われるのではなく、実質的に合否を左右するステップであるということを意識して対策を行いましょう。
適性検査を複数回実施しているか
SPIを含む適性検査が複数回行われる企業では、それぞれの検査に明確な目的があります。
例えば、1回目のSPIで応募者を絞り込み、2回目以降の検査で適性や職種配属を判断するというパターンが多いです。
このような企業は、単に学力や基礎能力を見るだけでなく、より精度の高い人物評価を行うために段階的に検査を活用しています。
1回目はSPI、2回目はGABやCABなど他の適性検査を組み合わせることもあります。
こうした企業は、面接などでの印象だけではなく、テスト結果などの数値データをもとに能力面も評価しています。
したがって、1回通ったからといって油断せず、2回目以降も万全の準備が必要です。
特定の科目が重視されそうか
SPIでの足切りは、単に総合得点だけでなく、特定の科目のスコアに注目して行われるケースもあります。
例えば、営業職や総合職では言語問題のスコアを、理系や技術職では非言語を重視するなど、職種に応じた科目別の基準を設けている企業も少なくありません。
そのため、全体の得点で見ると7割を取っていても、特定の科目が極端に低いと落とされるリスクがあります。これは企業に、実務で必要なスキルが不足していると見なされてしまうためです。
SPI対策では、得意分野で点数を稼ぐのではなく、苦手分野をなくして全科目まんべんなく解けるようにしておくことが合格の近道となります。
SPIの得点について正しく理解しよう
- 自分の点数を確認することができない
- 評価は相対的に行われる
- 性格検査は点数で評価されない
自分の得点は確認できない
SPIは、試験終了後にスコアが表示されることはなく、自分の得点を知ることができません。
これはテストセンター形式でもWebテストでも共通しており、受検者には結果が一切開示されない仕組みになっています。
そのため、「できた感覚があるのに落ちた」または「自信がなかったけど通過した」といったケースも少なくありません。
SPIは、あくまで企業が合否の参考にするためのものであり、受検者向けのスコア通知は行われない方針です。
試験後の自分の手応えに一喜一憂するよりも、正確さとスピードの両方を意識して演習を行い、いつでも高得点を出せるような実力をつけましょう。
テストセンターは出題内容から推測できる
SPIのテストセンター方式では、単純な正答数だけでは評価が決まりません。
問題ごとに難易度が調整される「適応型」の出題形式を採用しており、受検者の回答に応じて問題のレベルが変化します。
つまり、最初の方の問題でミスが続くと簡単な問題が出される一方、正答率が高いと難易度が上がっていくということです。
そのため、難しい問題が出るほど、それまでの正答率が高いことが推測できます。高得点の目安となる問題にも正解できていれば、かなり高い評価になるでしょう。
最終的な判断基準は「志望者内の偏差値」
SPIの評価は、絶対的な基準があるわけではなく、「志望者全体の中でどれだけ優れているか」という相対的な観点で行われます。
つまり、ある程度得点できていても、他の受検者のレベルが高ければ選考に通らない可能性もあるのです。
企業は、志望者全員の検査結果から偏差値を割り出して判断します。単に「上位〇%」を通過基準にしていた場合、得点だけでは通過の可否を判断できないでしょう。
人気企業や大手では、特に厳しい足切りラインや通過基準を定めていることが多いです。基礎問題は確実に点数を取り、ケアレスミスを最小限に抑えることが重要です。
足切りされないための基本対策

1問1分を目安に解く
SPIは時間との勝負です。問題ごとに時間制限は設けられていないものの、全体で見ると1問につき1分程度で解くペースが求められます。
特に非言語分野は、1問あたりの情報量が多く、時間がかかりがちです。
1分以内に問題を解いていくには、事前に設問のパターンに慣れておく必要があります。問題を見た瞬間に解法を思い出すことができるのが理想的です。
時間を測りながら演習する癖をつけ、自然と1分以内に解答できる感覚を体に染み込ませましょう。
問題文を隅々まで読まない
SPIは限られた時間の中で解答しなければならないため、問題文を細かく読み解いている時間はありません。
特に言語分野では、問題の長文を読むことに時間をかけてしまうと、設問を考えている途中で時間切れになる恐れがあります。
まずは設問や選択肢に目を通して、何が問われているのかを把握してから、必要な箇所だけを効率よく読み取ることが大切です。
文章全体の構造や要点を大まかに捉えながら、設問に関係する部分だけを重点的に読み取ることでl、時間を節約しつつ正確に解答できるようになります。
限られた時間を有効に使うためには、問題の読み取り方にも工夫が求められます。
わからない問題は適当に答える
SPIでは、たとえ不正解でも減点されることはなく、「誤答率」は評価に影響しません。
つまり、わからない問題をマークした結果、その解答が不正解だったとしてもマイナス評価にはならないのです。
そのため、わからない問題を無解答のままにしてしまうのは非常にもったいないです。
一点の差が足切りのラインとなることもあります。少しでも得点を重ねるためにも、わからない問題も適当で良いので必ず解答するようにしましょう。
【非言語対策】足切りは暗記で回避できる
基本の公式は必ず押さえておこう
- 確率=起こるパターン数÷全てのパターン数
- 割合=比べる数÷全体の数
- 速度=距離÷時間
非言語では、基礎的な公式を覚えていれば簡単に解ける問題が多く出題されます。中でも、「確率」「割合」「速度」の3つは頻出で、公式を使うと大幅に時短できるものが多いです。
まずはこれらの公式を暗記して、実際の問題を解く中で使ってみましょう。実践してみることで、公式の正しい使い方を理解することができます。
また、公式を変形して用いる問題も多いです。例えば「速度と時間」から「距離」を求める場合は、「距離=速度×時間」として計算する必要があります。
公式を丸暗記するというよりは、それぞれの関係を覚える方が応用が利きやすいでしょう。
解き方のパターンは決まっている
非言語の問題は、種類によって解き方のパターンが決まっています。問題を読んで毎回解き方を考えるよりも、「問題を見て解き方を思い出す」という方が楽に解けます。
数学の問題とは異なる形式なので、最初に解く時には不慣れに感じるかもしれません。しかし、何度か繰り返していれば見慣れたような問題ばかりだと気付くはずです。
そのため、苦手な問題があっても、解き方を暗記してしまえば簡単に対処できるようになります。数学や計算に苦手意識がある人には、こうした対策が有効です。
文章問題が多い点に注意
SPIの非言語では、式だけを解く単純な計算問題は出題されません。問題文から必要な数値を読み取る問題が多いため、速読力や読解力も試されます。
計算に関係のない記述は読み飛ばしながら、必要な数値を素早く拾っていくことが必要です。特に、「〇〇の行事」「〇〇のために」など、設定の説明的な文章を読んでいるとすぐに時間がなくなってしまいます。
基本的には、前提条件と数字の前後にのみ注目しておけば問題ありません。ただし、最終的に計算するものが何なのかは、しっかりと読んで確認しておきましょう。
【言語対策】語彙力を高めるのがカギ
ニュース記事を読むだけでも鍛えられる
言語では、語彙力や文章力といった鍛えにくい能力が試されます。
これらは日常的にどれだけ語句や文章に触れているかという積み重ねなので、勉強しようとしてもあまり手応えを感じられないでしょう。
そこで、ネットや新聞のニュース記事を読むように習慣付けることがおすすめです。特に、ビジネス系のニュースではやや堅めの表現も多いため、SPIの言語の出題傾向とマッチしています。
毎日軽くニュースを確認するだけでも十分に効果が見込めるので、「勉強」という感覚を持つことなく、継続しやすい点がメリットです。
知らない語句は調べる癖をつけよう

言語では、語句の正確な意味を把握していなければ解けないような問題が多く出題されます。見たことはあっても意味を知らない語句があると、出題された時に迷う原因になります。
そのため、意味がはっきりとわからない語句を見た時は、その都度調べるようにしましょう。
また、言語の頻出語句を確認してみるのも手っ取り早い方法です。こちらは自主的に調べるよりは印象に残りにくいですが、全体に目を通しておくことで「見たことがある語句」を大きく増やすことができます。
SPI最短突破3選パックでは、頻出語句の他にも解答テクニック集などの便利情報がコンパクトにまとめられています。無料でダウンロード可能なので、出題される語句の傾向を確認してみると良いでしょう。
長文を読む速さを測っておく
言語問題で一番つまづきやすいのが長文読解です。答えを考えるだけでなく、問題文を読むのにも時間を使わなければならないため、ペース配分が難しい問題になっています。
目安として、1000文字程度の長文の内容を30秒程度で把握しなければ、解答を終わらせるのは厳しいです。
自分が読み取りにかかる時間をタイマーで測り、適切なペースかどうか確認しておく必要があります。
長文は一言一句まで読み取らなければならないわけではありません。解答に必要な記述を探すだけで構わないため、文章の要点を見つけられるようにすると大きく時短できるでしょう。
SPIは知識があれば足切り回避も難しくない
SPIの学力検査には、企業ごとに定められた「足切りライン」があります。
これは、どれだけ他の選考要素が良くても、SPIで一定の点数に届かないと通過できないという基準です。
人気企業ではこのラインが高い傾向にあり、しっかり対策しておかないと思わぬところで落とされてしまう可能性もあります。
大切なのは、難しい問題にこだわらず、基礎的な問題を着実に解いて得点を重ねることです。
足切りは決して特別な壁ではなく、日頃の準備で確実に乗り越えることができます。安心して選考に進むためにも、SPI対策は苦手分野を重点的に早めかつ着実に進めるようにしましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen











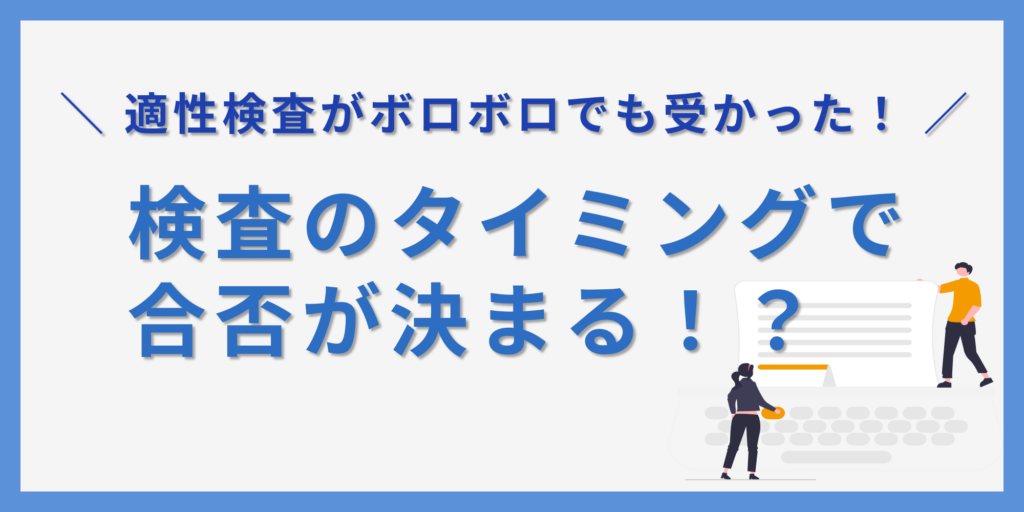 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?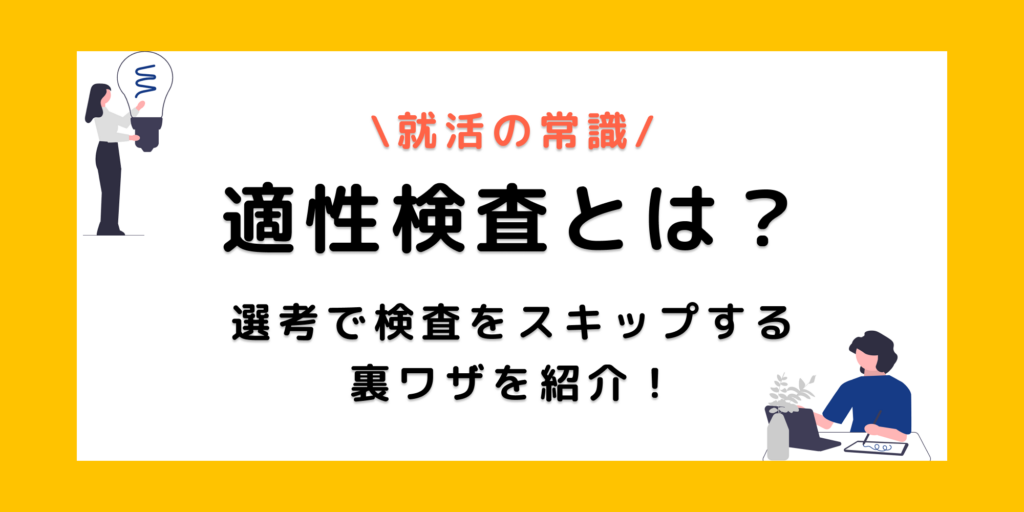 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!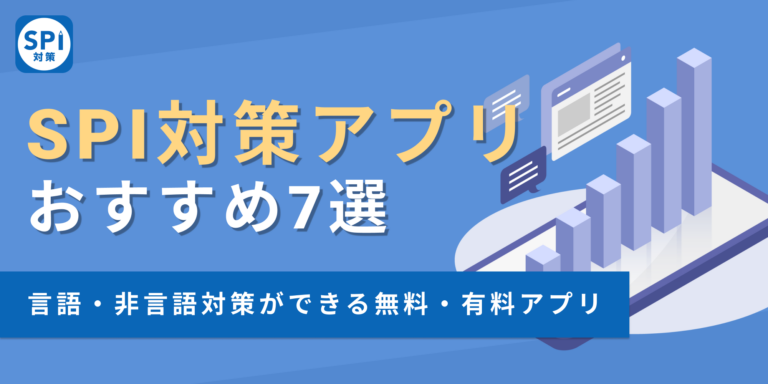 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ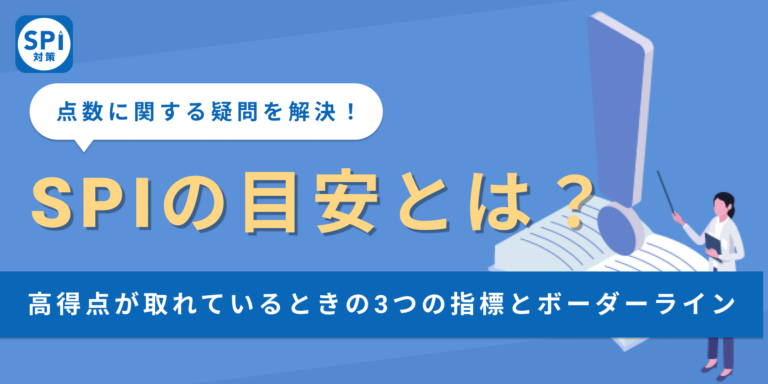 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点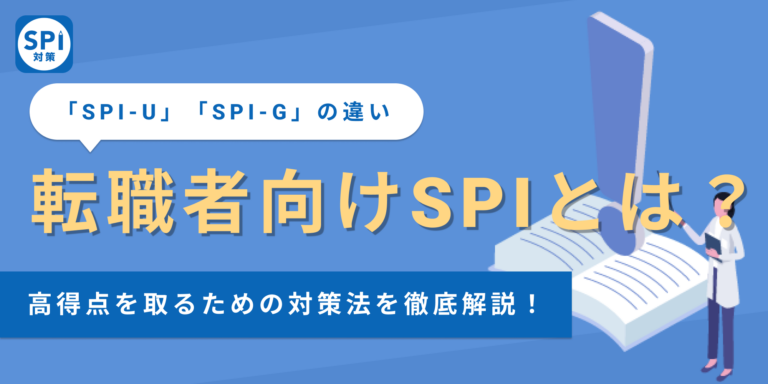 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説