
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 | SPI対策問題集
SPIとは、就活中に一度は受ける人が多い適性検査の一種です。基本はパソコンを使って受検するテストですが、形式によって受検方法に違いがあります。
この記事では、SPIの受検方法に関する基本や、現在主流のWebテスト・テストセンターの2形式の受検方法をステップに分けて解説していきます。
また、受検後の流れについても紹介しているので、これからSPIを受けることになる就活生の方はぜひ最後までご覧ください。
目次
SPIの受検方法は?

企業から指示されるのが一般的
SPIの受検は、選考中に決まります。企業からのメールで、「適性検査」という名目で受検案内が行われるケースが多いです。
SPI以外にも適性検査はありますが、具体的に「SPIを実施」と明言されることはありません。しかし、SPIは適性検査の中でも最大のシェアを占めているので、多くの企業ではSPIが実施されると考えて良いでしょう。
詳細な受検方法は受検案内に記載されているため、自分で調べる必要はほとんどありません。基本的には企業の指示通りに進めれば問題ないでしょう。
実施しない企業もある
SPIは多くの企業で実施される適性検査ですが、中にはSPIを実施しない企業もあります。就活では比較的メジャーなテストではあるものの、必須というわけではありません。
SPIは能力検査の点数などを基準に足切りして、応募者の人数を絞り込むために使われることが多いテストです。そのため、面接の前などの選考序盤で実施されやすい傾向にあります。
SPIの受検を求められないまま面接まで進んだ場合、そのまま適性検査は実施せず合否が決まる可能性が高いでしょう。
企業に応募せず受検することはできない
SPIは、企業から受検の指示を受けた場合にのみ受けられます。そのため、「応募前に受検しておく」「応募せずに練習として受ける」といったことはできません。
さらに、そもそもSPIを実施しない企業では、受検を希望しても実施されることはありません。SPIは選考の一環として一斉に行われるもので、個別の希望に合わせて実施されることはほとんどないからです。
また、SPIの受検は企業ごとに一度きりです。結果に自信がなくても受け直すことはできないため、一発で結果を出せるよう、事前にしっかり対策をしておく必要があります。
SPIの受検方法は4種類!
・Webテスト
・テストセンター
・ペーパーテスト
・インハウスCBT
SPIの受検方法は4種類あります。中でも、オンラインで受検できる「Webテスト」と、自分で会場を予約する「テストセンター」の2つが多く実施されています。
ただし、その他の形式でも実施される可能性はあるため、それぞれの受検方法や特徴を確認しておきましょう。
オンラインで受検するWebテスト
- 時間や場所を選ばず受検できる
- 受検案内のURLからすぐ開始できる
- 足切り用として使われることが多め
オンラインのWebテスト形式は、ネット環境とパソコンさえあればどこでも受検することができます。企業から送られてくるURLにアクセスするだけで受検できるので、SPIの中でも特に手軽な形式です。
また、受検する時間も自由なため、他のスケジュールの合間に無理なく済ませられます。ただし、何かトラブルがあった場合、すぐサポートを受けられるわけではない点に注意が必要です。
Webテストは企業側としても低コストで実施できることから、実施率は高い傾向にあります。一方で、不正を完全に防止できないため、足切りや最低限の確認といった用途で使われることが多い形式です。
会場で受検するテストセンター
- 会場のパソコンで受検する
- 会場と日時は自分で予約する必要あり
- 監視が厳重で結果の信頼度が高い
テストセンター形式では、全国に設けられた会場に行き、備え付けのパソコンを使って受検します。事前に会場と日時の予約が必要であり、Webテストと比べると手軽さには欠けます。
一方、本人確認や人の目による監視がある中で実施されるため、結果の信頼度は高いです。企業側にも重視されやすく、選考の中でも重要な判断材料として用いられる可能性があります。
ただし、会場と日時は自由に選べるわけではなく、「近くの会場がどこも満員」ということもあります。予約は完全に先着順なので、受検案内が来たらすぐに予約をしないと後々苦しいスケジュールになってしまうことがあるため、注意は必要です。
マークシート方式のペーパーテスト
- 問題用紙とマークシートを使って解答
- 企業が指定する会場に行く
- 実施するケースは少ない
ペーパーテストはマークシートと問題用紙を使って受検する形式です。こちらは企業の指定した会場・日時で受検しなければならないため、遠方から応募している場合は受検ハードルが高くなります。
また、同じ企業を志望する受検者だけが集まることになるので、プレッシャーも感じやすいでしょう。そもそも筆記の適性検査自体が珍しく、他の形式よりも結果が悪くなりやすい形式といえます。
実施コストや受検ハードルの高さから、近年ではペーパーテストはほとんど行われていません。それでも撤廃されたわけではなく、ごく一部の企業では実施されています。
企業へ行って受けるインハウスCBT
- 企業のオフィスなどで受検する
- 検査自体はテストセンターに近い
- 企業が直接監視するため信頼度は非常に高い
インハウスCBTでは、企業のオフィスなどに足を運び、用意されたパソコンで受検します。会場のパソコンを利用するという点で、テストセンターに近い形式です。
ただし、実際に企業へ行かなければならないので、「志望企業の人に見られている」という緊張感があります。日時も企業側に合わせる必要があり、スケジュール面での負担も大きいでしょう。
企業の担当者が監視している中で実施されるため、結果の信頼度はSPIの中でも特に高くなります。しかし、ペーパーテストと同様に実施コストが高いので、実施している企業は少数です。
オンラインでのSPI受検方法【3STEP】
①企業から送られてきた受検用URLを開く
②注意事項や検査内容を確認する
③好きな時間に検査を開始する
ここからは、オンラインで実施されるWebテスト形式を受検する場合の、SPIの流れを3ステップで紹介します。これからSPIを受ける予定の方は、こちらで検査全体のイメージを掴んでおきましょう。
①企業から送られてきた受検用URLを開く
オンラインで受けるWebテストの場合、企業から送られてくるメールに「受検用URL」が記載されています。また、受検期限も明記されているため、必ず確認しておきましょう。
URLを開いてもすぐに受検が始まるわけではないので、メールが届いたら一度開いておくことをおすすめします。開いたページから受検開始の画面まで進められるようであれば、Webテスト形式だと断定できます。
なお、実際に開始ボタンを押さなければ、そのままページを閉じても問題ありません。SPIは対策が必須の適性検査なので、Webテストに合わせた対策をしてから改めて検査に進むようにしましょう。
②注意事項や検査内容を確認する

引用:arorua.net
SPIのWebテストを受検する前には、必ず注意事項や検査内容に目を通しておきましょう。一般的な「カンニングの禁止」といったルールだけでなく、「一度開始したら途中で中断できない」「制限時間を過ぎると自動終了になる」といった大事なルールが存在します。
特に注意したいのは、無関係なソフトウェアやタブに関する不正です。SPIのWebテストではシステムでパソコンの挙動を監視しており、受検用のブラウザ以外にソフトウェアが起動していると必ず検知されます。
さらに、別のタブを何度も行き来したりしていても検知されるようになっています。そのため、Webテストのウィンドウ以外は全て消した状態で検査に臨むようにしましょう。
また、検査内容は詳しく確認することはできませんが、解答形式や制限時間などの基本的な情報はこの段階で把握できます。ここで疑問があれば、企業やサポートに問い合わせておくと安心です。
③好きな時間に検査を開始する
事前の確認が済んだら、都合の良い時間に検査を開始しましょう。Webテストは基本的にいつでも受検ができるので、企業側の都合などを考慮する必要はありません。
ただし、深夜や早朝やSPI側のサイトがメンテナンス状態になっている可能性があります。期限ギリギリで受けようとしている時には致命的なので、数日は余裕を持って受検することをおすすめします。
Webテストを一度開始したら、途中で中断したり、やり直したりすることはできません。長時間拘束されるようなテストではありませんが、1時間~1時間半は確保してから始めるようにしましょう。
また、推奨ブラウザやOSが指定されている場合もあり、古い環境だと動作が不安定になることもあります。余計なトラブルを避けるためにも、練習問題で動作確認を済ませておくと安心です。
テストセンターのSPI受検方法【4STEP】
①予約用URLから会場と日時を決める
②持ち込み必須・持ち込み不可の物をそれぞれ確認
③指定の時間にテスト会場へ行く
④試験監督の指示で検査を開始する
次に、テストセンター形式のSPIの受検方法を4ステップで紹介します。Webテストよりも注意するべきルールが多いため、しっかり確認しておく必要があります。
①予約用URLから会場と日時を決める

引用:arorua.net
テストセンター方式では、まず企業から「受検会場の予約URL」が送られてきます。会場と受検日時を自分で予約する必要があり、直前にやろうとしてもまず間に合いません。
テストセンター会場は全国に設けられていますが、人気の会場や時間帯は満員になってしまうこともあります。予約は先着順なので、メールが届いたらできるだけ早めに予約しておきましょう。
また、予約の際は会場までのアクセスも確認しておくべきです。一見近い会場でも、駅などからのアクセスが悪かったりする場合もあります。土地勘のない場所に会場がある場合は特に注意が必要です。
②持ち込み必須・持ち込み不可の物をそれぞれ確認
- 受検票
- 本人確認書類
※その他は持ち込み禁止
SPIのテストセンターを受検する時は、受検票と本人確認書類の提示が必須です。片方を忘れただけでも受検できなくなってしまうので、必ず用意した上でテストセンター会場へ向かいましょう。
受検票は予約をした画面を印刷したもので、自分で用意する必要があります。予約完了メールや、スマホのブラウザなどでは代用できません。
本人確認書類は、公的な機関が発行した顔写真付きの書類が求められます。主に、運転免許証やマイナンバーカードなどを提示することになるでしょう。
その他の物は基本的に持ち込み不可となっており、受検前にロッカーに預ける必要があります。腕時計やスマートフォンなど、つい身に着けてしまうものも忘れずに預けておきましょう。
アクセサリー類は、地味なものであれば注意されないかもしれませんが、不正とみなされるリスクもあるため控えた方が無難です。
③指定の時間にテスト会場へ行く
当日は遅刻すると受検できず、これまでの準備が無駄になってしまいます。必ず時間に余裕を持って移動しましょう。
公共交通機関を利用する場合は遅延や道に迷う可能性もあり、会場のビルに着いてからも試験室を探すのに時間がかかることがあります。30分ほど早めに到着する想定で行動すれば安心です。
会場に着いたら受付と本人確認を済ませ、荷物をロッカーに預けて開始を待ちます。
SPIテストセンターは全国の多くの企業が利用しており、同じ会場にいる人も受検企業が同じとは限りません。実際には、試験前に企業から案内された「受検ID」や「パスワード」を入力することで、どの企業の選考として受検するかがシステム上で管理されています。
そのため、他の受検者がどの企業を受けているかはわかりません。周囲を気にせず、自分の試験に集中することが大切です。
④試験監督の指示で検査を開始する
開始時間になったら、着席してSPIを開始します。使うパソコンやメモ用紙などは全て会場で用意されており、テストに集中できるようになっています。
受検用のページも開かれているはずですが、試験監督の指示があるまで絶対に操作はしないようにしましょう。不正扱いで失格になる可能性があります。
その他にも、検査中の私語や勝手な離席は厳禁とされています。中断して休憩を取ることも原則できません。ただし、急な体調不良や機材トラブルなどがあった場合は、検査の中断や再受検といった措置を受けられます。
こうした止むを得ないトラブルは、検査が終わってから申告しても取り合ってもらえない可能性が高いです。その場ですぐに試験監督へ報告し、追加の指示を待つようにしましょう。
SPIの受検後の流れは?

提出や報告の手続きは不要
SPIを受検した後に、自分で結果を提出したり、受検したことを報告する必要はありません。検査が完了した時点で自動的に結果は送信されているので、期限までに受けていれば選考結果を待つだけでOKです。
ただし、以前にテストセンターで受検したことがある場合、別企業でテストセンター受検を求められた時に以前の分の結果を提出することができます。この手続きをする場合のみ、自分で行わなければなりません。
SPIの結果は企業だけが確認できる
SPIを受検すると、自分の点数が気になるものですが、結果は受検者に通知されず、企業だけが確認できる仕組みになっています。
ただし、企業が結果を把握しているからといって、問い合わせたり面接で尋ねたりするのは避けましょう。結果が公開されないのには理由があり、それを聞き出そうとするのはマナー違反と受け取られる可能性があります。
自分で結果を推測する方法としては、出題内容を思い出して自己採点することが挙げられます。
また、テストセンター方式では正答率に応じて出題内容が変わるため、「難度の高い問題が出たかどうか」を目安にすることで、大まかな得点感覚をつかむこともできます。
その後の選考でも判断材料になる
SPIの結果は、その時の選考突破だけに影響するものではありません。書類審査や面接の時にも、必ず判断材料のひとつとして扱われます。
SPIを突破できても、ギリギリの点数だった場合には後々の選考に響く可能性が高いです。また、性格検査の結果も、「自社に合うか」「面接の印象と乖離はないか」といった点で参考にされるでしょう。
そのため、合格ラインに関わらず「なるべく高い点数を取っておく」ことが重要になります。
SPIの主な受検方法を押さえておこう
就活で受ける機会の多いSPIは、形式によって受検方法が異なります。中でも頻出のWebテストとテストセンター形式は、必ず受検までの流れを掴んでおきましょう。
また、SPIは期限に余裕を持って受検するようにしましょう。ギリギリで受けようとすると、思わぬトラブルで中断・再受検となって間に合わなくなる可能性もあります。「受けられずに落ちる」のは一番もったいない結果なので、絶対に避けるべきです。
特にルールが厳しいテストセンター形式の受検方法には注意し、余裕のあるスケジュールで落ち着いてSPIを受検しましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen














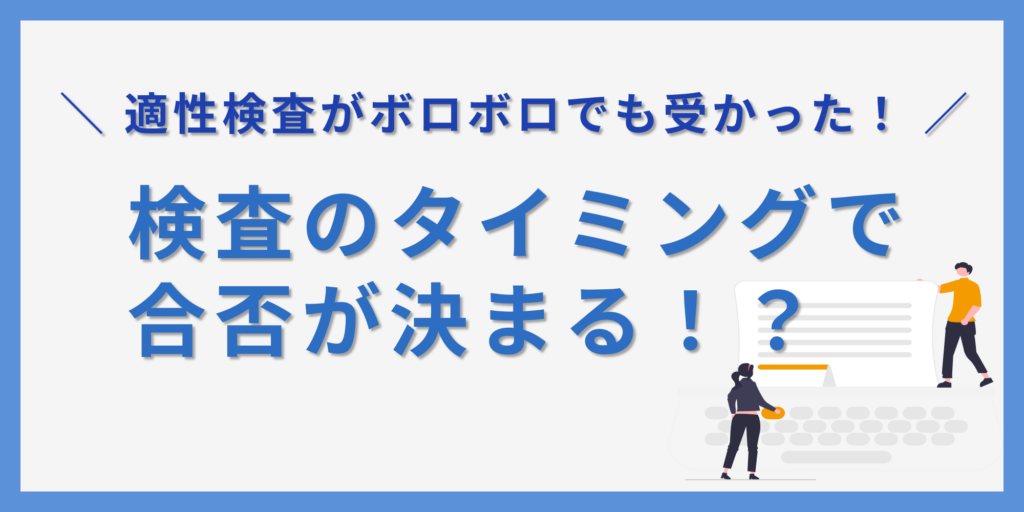 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?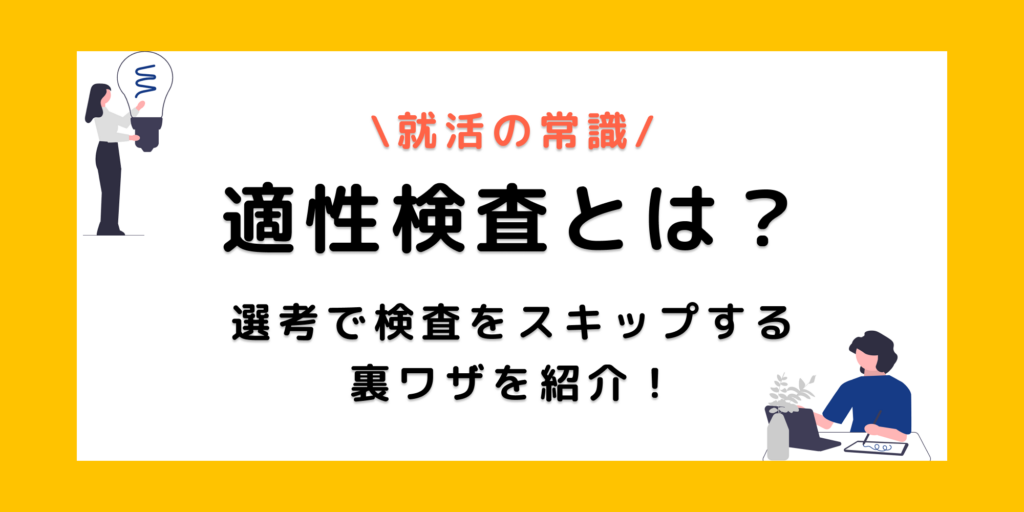 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!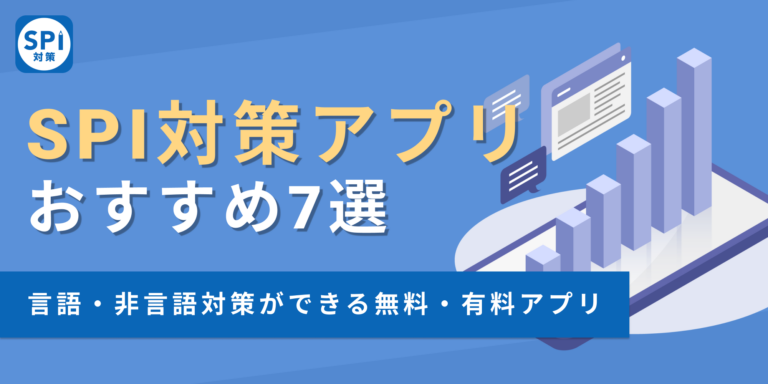 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ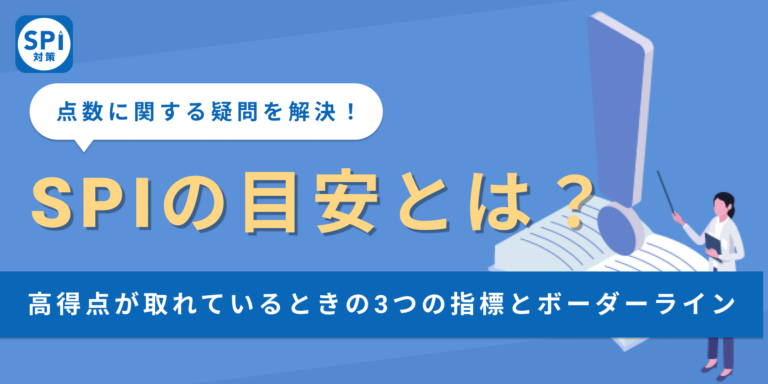 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点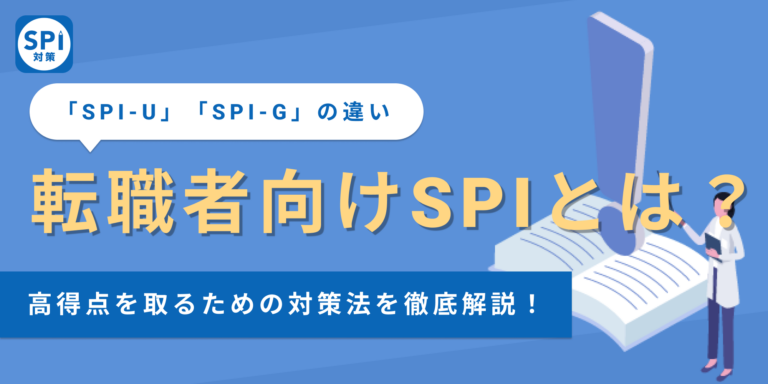 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説