
SPIの高得点の目安とは?評価が高い時の指標を解説【分野別】 | SPI対策問題集
SPIで高得点を狙うには、単に問題を解くだけではなく、出題形式や分野ごとの得点の目安を理解することが重要です。
しかし、言語・非言語・英語・構造的把握力の各分野で「どのくらいの点数が高得点にあたるのか」は、初めて受ける就活生には分かりにくいものです。
そこで、テストセンターでの評価方法や高得点の目安となる問題パターンを分野別に紹介します。模試や問題集を使った効果的な対策も解説しているので、高得点を狙って勉強する方はぜひ参考にしてください。
目次
SPIテストセンターの高得点目安となる指標とは?

SPIを受検した時に誰もが気になるのは、自分の成績で志望企業の選考に残れているかどうか。
しかし、SPIは受検者が自分の結果を知ることができないという難点があります。
そこで、上手く活用してほしいのが、SPIの「高得点目安となる指標」です。
その指標をしっかり理解していれば、自分の正答率がどれくらいなのかを簡単に予想することができます。
SPIテストセンターの仕組みについて
SPIの高得点目安となる指標を知る前に、SPIテストセンターの仕組みについて理解しておく必要があります。
まず、SPIテストセンターはWeb形式で行われる適性検査のことを指し、受検者の解答状況によって問題数や難易度が異なるのが特徴です。
つまり、受検者それぞれで異なる問題内容が出題されるため、単に点数を多く取れれば合格できるというわけではありません。
では、合格基準は何で判断されるのでしょうか?
その答えは、「偏差値」です。
SPIテストセンターでは、正答率が高ければ問題の難易度もどんどん上がっていくため、難しい問題を正解できればそれだけ受検者の最終的な偏差値も高く評価されるようになります。
これを踏まえ、SPIテストセンターの評価方法について詳しく見ていきましょう。
SPIテストセンターの評価方法とは?
SPIテストセンターの評価方法で偏差値を重視している理由は、能力の高い受検者を効率よく選定できるからです。
例えば、点数を基準にした場合は、ある一定以上の点数を獲得した受検者は何人でも合格できるようになります。
一方で、偏差値を基準にした場合は、受検者全体の「上位〇%」という割合で合格者が算出されるため、その年の受検者のレベルが高ければそれだけ能力が高い人材を引き抜けるようになるのです。
具体的には、20〜80の偏差値に応じて7段階のレベルで評価されます。以下は偏差値と問題の出現率を示した表になっています。
| 段階 | 得点 | 出現率 | 上位からの累計 |
| 7 | 70以上 | 2.3% | 2.3% |
| 6 | 62〜69.5 | 9.2% | 11.5% |
| 5 | 54〜61.5 | 23.0% | 34.5% |
| 4 | 46〜53.5 | 31.0% | 65.5% |
| 3 | 38〜45.5 | 23.0% | 88.5% |
| 2 | 30〜37.5 | 9.2% | 97.7% |
| 1 | 29.5以下 | 2.3% | 100.0% |
「言語」と「非言語」であれば、それぞれが7段階に分けられて評価されるため、合格基準はその数値の合計ということになります。イメージとしては以下のような形です。
企業によって求められる偏差値が異なるように、合格ラインも一定ではありません。
特に、一般的に名の知れた一流企業であれば、最低でも「言語」と「非言語」の合計は10ポイント以上必要になると言われています。求められる偏差値は60以上が目安です。
まずは、自分の志望企業がどれくらいの偏差値を必要としているのかを知り、それを目標にSPIの対策を進めるのが良いでしょう。
SPIテストセンターの高得点目安となる3つの指標
SPIテストセンターの問題を総合的に見て、高得点目安となる指標には、「チェックボックス」「複数タブ(4タブ)」「残り問題の時計の針」の3つがあります。
では、実際にこの3つがどのように高得点目安として関わってくるのか詳しくご説明します。
また、科目別の高得点目安についても下記で紹介しているので、そちらもぜひ参考にしてみてください。
チェックボックス
チェックボックスは、簡単に言えば複数選択式の問題のことです。
「この問題の答えとして正しいものを、以下の選択肢の中からすべて選びなさい」といった問題文で出題されます。
答えが複数あるタイプで、すべて合っていなければ正解にカウントされないという特徴があり、長文問題などに多く用いられます。
正答率が高ければチェックボックス形式の問題が出題される傾向にあるので、確認しながら問題を解き進めましょう。
複数タブ(4タブ)
複数タブは、1つの設問に対して複数の小問題が問われる形式のこと。
基本的な形式では2つの小問が出題されますが、正答率が良ければ4つのタブの問題が出現するようになります。

SPIでは、非言語の「表の読み取り問題」などで多く出題される傾向があります。
残り問題の時計の針
SPIテストセンターでは、パソコン画面から問題の進捗状況と残り時間を確認できる特徴があります。
高得点目安の指標となるのは、「残り問題の時計の針」。
SPIテストセンターは時間内に問題が解き終わらなかった場合は強制終了になり、次の問題へと切り替わります。
高得点を取得した場合は、強制終了するタイミングで残り問題の時計の針が9時〜10時であることが多く、それを指標にすることができます。
図で表すと下記のようなイメージです。

解答後は、時計の針がどのような形で止まっているかを確認してみましょう。
【SPI言語】高得点の目安
長文問題の出題数
言語問題において、高得点目安の1番のキーとなるのは長文問題の出題数です。平均的な出題数は1問ですが、正答率が高ければ2問目3問目が出題されます。
そのため、2問以上の長文が出題された場合は、確実に高得点が取れていると考えて問題ないでしょう。
長文問題の小問の出題形式
長文問題で高得点が取れているかを確認する方法は「空欄補充問題」と「内容一致問題」の2つあります。
空欄補充問題の形式
長文問題の小問には、空欄補充の問題が頻出されます。
高得点の目安となる指標は、選択肢が「語句抜き出し形式」になっていること。抜き出す文字数には指定があり、制限が曖昧なほど高得点の可能性が高いとされています。
◆選択肢の出題例
2. 〇〇字以内
3. 〇〇字程度
4. 字数指定なし
内容一致問題の形式
長文問題の中には、『本文の内容に合致する選択肢を解答してください』というような内容一致の問題があります。
高得点の目安となる指標は、この内容一致問題の選択肢が「チェックボックス形式」になっていること。
チェックボックス形式の問題は、当てはまるものをすべて正しく選択しなければ正解にはならないため、高い読解力が必要とされ、難易度は必然的に高くなります。
非言語テストの始まりが4タブ形式
言語テストの次に行われる科目は、「非言語テスト」です。
SPIでは、科目が変わってもそれまでの解答状況が引き継がれるため、正答率が高ければ必然的に難易度の高い問題が出題されます。
そのため、非言語テストで最初に出題される問題が「4タブ形式」であれば、必然的に言語テストが高得点を取れていたと判断できるのです。
【SPI非言語】高得点の目安
表の読み取り問題の形式
表の読み取り問題は複数の小問で構成されていることが多く、高得点が取れている場合は、難易度の高い「4タブ形式」で出題される傾向にあります。
通常は2タブの形式なので、4タブの問題が出てきたら正答率が高いと判断して問題ないでしょう。
推論の問題数
SPIのテスト問題の中で最も難易度が高いと言われている推論ですが、この問題数でも得点の目安を測ることができます。
推論の問題が多いということは、必然的に難易度の高い問題を与えられていることが予想できるため、高得点が取れていると判断できるでしょう。
また、一流企業の選考に通過できる基準として、「推論の問題数が全体の半数以上を占めている」ことが挙げられます。
逆を言えば、非言語問題で簡単な問題ばかり出題された場合は、得点があまり取れていないケースが多いので注意が必要です。
推論の出題形式
一般的に、推論の問題は4〜5つ程度の選択肢が与えられ、その中から適した解答を選びます。
中でも、正答率が高い場合に多く出題されるのは「チェックボックス形式」。
選んだものがすべて合っていなければ正解にはならないため、非常に難易度の高い問題です。
【SPI英語】高得点の目安
英語テストでの高得点の目安は、長文問題が4問以上出題されること。
英語の長文問題は基礎的な知識がなければ解くのは難しいため、早期の対策でどれだけ基礎固めができたかが重要になります。
そのため、長文問題が多く出題された場合は、高得点が取れていると判断して問題ないでしょう。
【SPI構造的把握力】高得点の目安
「構造的把握力」に関しては、高得点の目安となる指標はありません。理由は、この問題に限っては解答状況によって問題数や難易度が変化しないからです。
しかし、どの科目も同じように事前の対策を十分に行っておくことが大切なので、指標が分からないからと言って不安になることはありません。
問題集などで繰り返し問題を解き、しっかり学習を進めておきましょう。
SPIのボーダーラインとは?

SPIの合格に対する判断基準は、偏差値で決まります。明確な合格点数が決まっていないため、一概に「〇〇点以上取れば合格できる」とは言えません。
しかし、一般的には正答率が6〜7割以上であれば、大多数の企業の選考に通過できると言われています。
SPI対策を行う際には7割以上の正答率を目指して、取り組むのが良いでしょう。
SPIの企業別ボーダーライン
SPIのボーダーラインは企業ごとに異なり、競争率の高い企業であれば合格ラインの基準値も高く設定されます。
例えば、毎年多くの就活生から高い人気を誇る、三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅の5代商社。
このような一流企業は競争率が非常に高くなるため、効率よく就活生の選別を行うためにSPIを利用することがあります。
ちなみに、合格のボーダーラインは8〜9割。
高い能力が求められる金融系やコンサルティング系の業界も、同程度のボーダーラインであると言われています。
そのため、人気が高い総合商社や大手企業を目指している方は8割以上の正答率を目指し、念入りに対策を行う必要があるでしょう。
ボーダーラインを設定していない企業もある
SPIのボーダーラインは人気企業であるほど高くなるとご説明しましたが、逆にボーダーラインを設定しない企業も存在します。
それらの企業はいわゆる、「人物重視の採用」を行っているため、履歴書や実際の面接を通して自社との社風とマッチした人材を選出しているのだと考えられます。
しかし、ボーダーを設定していないからと言っても、SPIの結果が全く反映されないわけではありません。
例えば、最終選考まで残った2人の就活生のどちらかを選ぶ場合、最終的な決め手としてSPIの結果が参考にされることもあります。
SPIで高得点を取れているというのは、どこの企業においてもプラスの評価にしかならないため、ボーダーラインを設定していない企業でも事前の対策は必要になるでしょう。
SPIで高得点を取るためのポイント

志望企業の出題傾向をしっかり把握しておく
SPIで出題される問題の傾向は、業界や業種ごとに異なるのが特徴です。
そのため、まずは自分の志望企業ではどんな能力が求められているのかしっかり把握し、必要な対策を行いましょう。
就活では一度に複数の企業を並行して選考を受けることが基本ですが、中には異なる業界や業種の職種を受けている就活生の方もいます。
だからこそ、自分に必要な対策法をいち早く見つけ、出題傾向を理解しておくことが非常に大切です。
同じ問題集を2~3周解く
SPIの対策として最も有効的な手段は、同じ問題集を繰り返し解くこと。
一見すると、できるだけ多くの問題に触れた方が高得点が取れるのではと勘違いしてしまいそうですが、実はそうではありません。
人間の脳は同じことを繰り返すことで、記憶に強く刻むことができます。そのため、1つの問題集は必ず2〜3周は問くようにしましょう。
ただ、注意が必要なのは一度正解した問題を何度も解き続けること。非常に効率が悪いので、正解できなかった部分のみを繰り返し解き、1冊の問題集を完璧にできるようにしましょう。
模擬試験を受ける
問題集をひと通り解き終わったら、無料で受けられる模擬試験に挑戦してみるのがおすすめです。
本番に近い形で問題を解くことで、問題1問にかけられる時間の感覚などもつかめるため、残りの期間で自分が克服すべき課題を明確に把握できるようになります。
また、テストの雰囲気に慣れることも大切です。いきなり本番を迎えてしまうと、緊張に飲まれて本来の実力が発揮できないケースも考えられます。
そうした不安を解消するためにも、自分の志望企業のSPIを受検する前に必ず1度は実践形式のテストを受けておくことがおすすめです。
SPI対策模試では、無料で模擬試験を受けることができます。最短5分の簡単設定で、まずは自分の実力を確かめてみましょう。
高得点の目安を知れば受検後も動きやすい!
SPIテストセンターの結果は、通常では確認できません。しかし、高得点の目安となる問題を知っていれば、良い得点が取れたかどうか推測することができます。
SPIの受検から合否の発表まではある程度の日数がかかり、その間に「他の企業を考えるべきか」「次の段階の選考に備えるべきか」を考えなければなりません。
高得点を取れた可能性が高いとわかれば、面接などの対策に振り切ることもできるでしょう。忙しいスケジュールに余裕を持たせることにも繋がります。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen














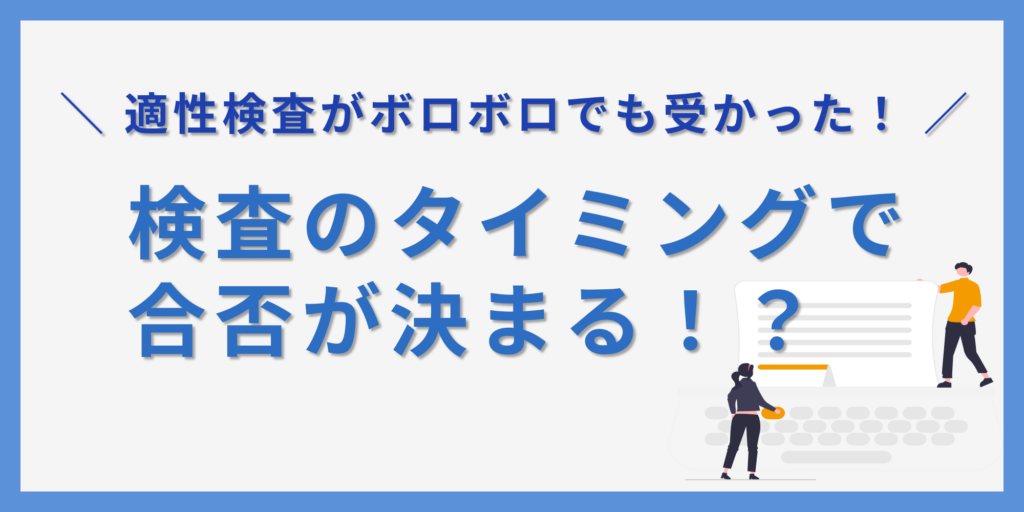 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?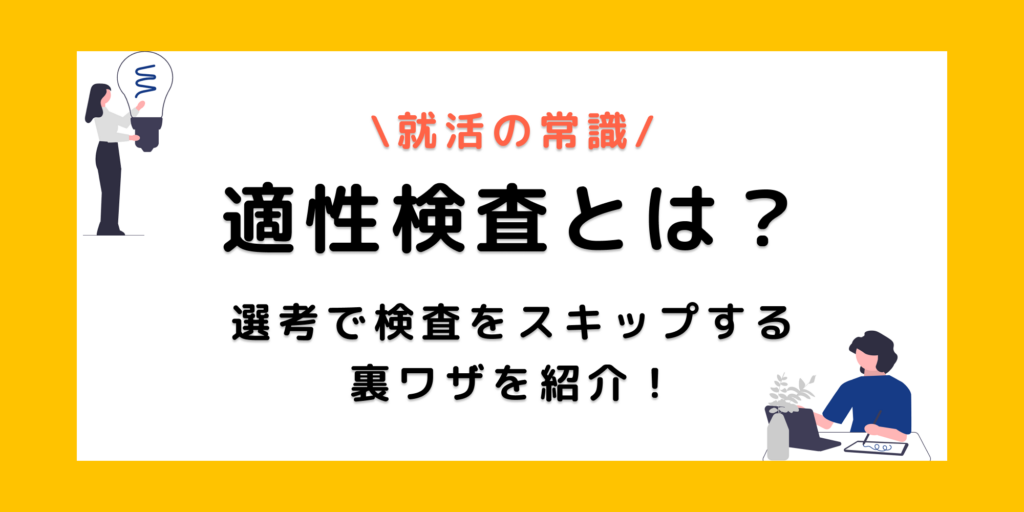 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!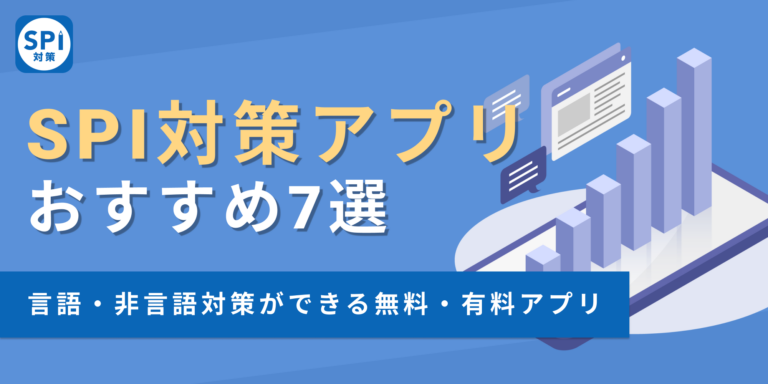 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ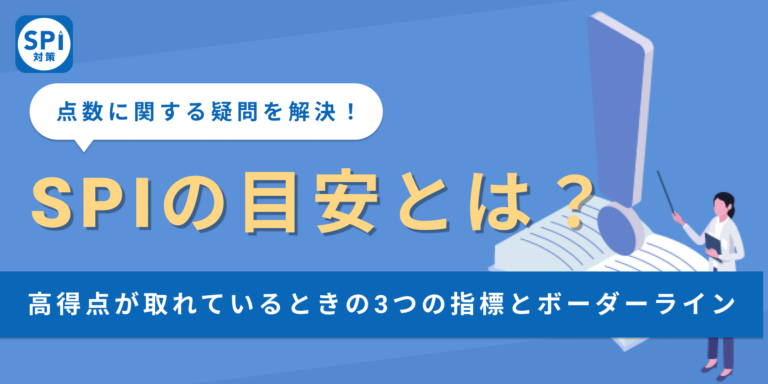 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点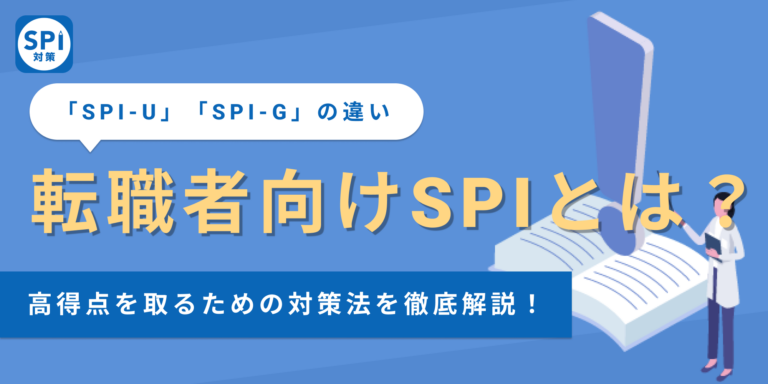 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説