
【SPI構造的把握力検査とは?】出題パターンから対策法まで徹底解説! | SPI対策問題集
SPIテストの中でも特に難易度が高いとされるのが「構造的把握力検査」です。与えられた情報を整理し、論理的に結論を導き出す力を測る内容になっています。
実施企業は限られるものの、出題される時は重要度が高いことが予想されます。言語・非言語それぞれの問題に特徴があり、初めて受けると戸惑う受検者も多いでしょう。
この記事では、構造的把握力の出題形式や例題を紹介し、高得点を取るためのコツや効果的な対策方法を解説していきます。
目次
SPIの構造的把握力検査とは?
構造的把握力検査とは?

SPIの「構造的把握力検査」とは、物事の背後にある共通性や関係性を読み解く論理的思考力を測るものです。
構造的把握力検査は、テストセンター受検でのみ採用されています。
出題される問題は、題材を基に文章をグループ分けする「言語(国語)」、計算の文章問題をグループ分けする「非言語(数学)」の2パターンに分けられます。
どちらのパターンでも似ている文章をグループ分けする問題が出題されるという点は共通しており、主な違いは計算の有無だけです。
こうした問題を、20分のうちに20問解くことになります。
構造的把握力検査はSPIの他の分野と比べると、難易度がやや高く、問題数に対して制限時間も短いです。
苦戦する人も多いため、受検する可能性がある場合には徹底した対策が必要となるでしょう。
SPIの「能力検査」との違いは?
構造的把握力検査は、SPIの「能力検査」に含まれる科目の1つです。
他の能力検査との違いは、テストセンター受検でしか採用されていないという点と、企業が指定した場合のみ受検するという点です。
出題されるかどうかは企業ごとに異なるので、各企業の例年の傾向などを調べ、必要な情報をしっかりと確認しておきましょう。
また、テストセンター受検の特徴として、一度検査を受ければ、そこから1年間は複数の企業で解答を使い回しすることができます。
手応えのある結果を出せた場合には、使い回しも検討してみましょう。
構造的把握能力検査を実施している企業
構造的把握力検査は、総合商社、コンサルティングファーム、広告業界、不動産業界の企業で実施されることが多いです。
問題解決力や論理的思考力が重要となるような、難関企業で実施されやすいといえます。
ただし、これらの企業の選考にエントリーした場合でも、テストセンター受検でなければ、構造的把握能力検査は実施されないということを覚えておきましょう。
構造的把握能力検査を企業が実施する理由
問題解決能力を判断するため
企業が構造的把握力検査を実施する理由の一つに、問題が発生した際にしっかりと対処できる人材が欲しいからというものがあります。
先述したように構造的把握力は物事の背後にある共通性や関係性を読み解く力です。
この力が高ければ、未経験の問題に直面した際にも、過去に経験した問題との共通点を見つけて解決の糸口を掴むことができます。
また、複雑な問題に直面した場合でも、全体を俯瞰して「問題点はAとBだ」というように要点を掴むことが重要です。
構造的把握力検査で高い成績を収めると、高い問題解決力があることを期待されます。
ニーズを捉えて新しいアイデアを生み出す力を判断するため
多くの企業は時代の変化や顧客のニーズに対応した、他社とは差別化されたサービスを提供し続けていく必要があります。
構造的把握力が高い人材は、既存のサービスモデルの中から別のサービスモデルに転用できるポイントを見つけたり、さまざまな顧客のニーズや現状の課題を俯瞰し、分類・整理したりする能力に長けているといえます。
つまり、新しいサービスのアイデアやサービスの改善方法を発案する能力が高いということです。
企業は、こうした能力を持つ人材を求めて構造的把握力を実施しています。
人から合意形成を得る力を判断するため
構造的把握力は商談や会議において、相手から合意形成を得る場面でも役立ちます。
企業が構造的把握力を測るのは、この合意形成を得る力を判断するためでもあります。
構造的把握力が高いと、相手の話を整理して要点をまとめ、「要するに○○ということですね」と相手への理解を示したり、話を円滑に進めることができるでしょう。
また、「AさんとBさんの言っていることは○○という点では同じだ」というように複数の意見から共通点を見つけ出し、折衷案を編み出すことにも役立ちます。
つまり、構造的把握力は相手との交渉において、相手を納得させる能力と結びついているということです。
この能力はコンサルティング業界では特に求められる能力であり、その他にもさまざまな業界で役立てることができます。
構造的把握力検査の言語問題
言語の出題パターン
構造的把握力検査の言語問題は、提示された5つの文章を論理関係を根拠に、グループ分けするものです。
よく出題される論理関係のパターンは以下の7つです。
- 肯定⇔否定
- 意思⇔願望
- 実際に起きた事⇔仮定
- 推測⇔断定
- 順接⇔逆接
- 客観⇔主観
- 個人⇔集団
引用:就活の教科書
例題1
つぎのア〜オを、各問題の指示に従ってP(2つ)とQ(3つ)の2グループに分けるとする。
ア〜オの会話を、Xに対するYの応じ方によって、P(2つ)とQ(3つ)の2グループに分けるとする。
ア. X「私はRキャンプ場が好き。屋根付きのバーベキュー場があるから。」
Y「じゃあ、おいしいレストランがあるキャンプ場ではだめかしら。」
イ. X「私はSキャンプ場に行ってみたい。去年オープンしたばかりだから。」
Y「じゃあ、昔からあるキャンプ場ではだめかしら。」
ウ. X「私はTキャンプ場に毎年行ってるの。川遊びができる場所があるから。」
Y「じゃあ、川がないキャンプ場ではだめかしら。」
エ. X「私はUキャンプ場がいいわ。夜、カブトムシとクワガタがくる木があるから。」
Y「じゃあ、ホタルがいるキャンプ場ではだめかしら。」
オ. X「私はVキャンプ場に行きたい。富士山が見えるところにテントを張りたいから。」
Y「じゃあ、南アルプスが見えるキャンプ場ではだめかしら。」
このとき、Pに分類されるものはどれとどれか。A~Jの中からあてはまるものを1つ選びなさい。
<選択肢>
- アとイ
- アとウ
- アとエ
- アとオ
- イとウ
- イとエ
- イとオ
- ウとエ
- ウとオ
- エとオ
【解答・解説】
ア〜オの会話では、Xが好むキャンプ場に「似ている特徴を持つ」ものをYが提案している場合、そしてXの好みとは「正反対の特徴を持つ」ものをYが提案している場合の2通りの分類が存在しています。
前者に該当するものはア、エ、オ、と3つあるので、これらはグループQに分類されることが分かります。
後者に該当するのはイとウの2つであるため、これらが分類されるグループはPであり、正答は「E. イとウ 」となります。
例題2
次のア〜オを「文の構造」によってAグループ(2つ)、Bグループ(3つ)に分類する時、Aグループに分類されるものを2つ選びなさい。
ア. 大雪が降り、各地で道路が寸断された。
イ. 蒸し暑くなってきたので、そろそろ蚊の出る頃だ。
ウ. タブレット端末の出荷数量が急速に伸びたため、市場は飽和し始めた。
エ. あれだけ練習を重ねてきたのだから、絶対に優勝するはずだ。
オ. 近くに大型ショッピングセンターができたため、近隣地域の地価上昇現象が起きている。
引用:就活の教科書
【解答・解説】
答え:イとエ
この問題では、前半に対する後半の論理関係の違いに着目する必要があります。
どの文章も前半では「原因・根拠」を示しています。ア、ウ、オでは前半の「原因・根拠」に対して、後半では「実際に起きた結果」が述べられています。
これらの文章は3つで1つのグループを形成しているので、Bグループであることが分かります。
イとエでは前半の「原因・根拠」に対して、後半では「推測」が述べられています。
これらの文章は2つで1つのグループを形成しているため、Aグループであることが分かります。
よって、正答は「イとエ」となります。
構造的把握力検査の非言語問題
非言語問題は、計算の構造が似ている文章をグループ分けする問題が出題されます。
数学を扱った問題ですが、実際に計算結果の数値を答える問題ではありません。
あくまでも計算の過程が似ている文章の組み合わせが何かを答える問題です。
そのため、最後まで計算して正確な計算結果を求める必要はありません。
よく出題される問題パターンは以下の4種類です。
- 四則演算のどの計算法が求められているのか見抜く問題
- 割合の問題
- 確率の問題
- 組み合わせの問題
引用:就活の教科書
例題
つぎのア〜エのうち、問題の構造が似ているものの組み合わせを、A~Fのなかから1つ選びなさい。
ア. Sの蔵書の8割は文学書で、そのうちの3割が詩集である。詩集は蔵書全体の何割か。
イ. 共同経営者のTとUは3:2の出資額に応じて利益を分配している。Uの取り分は利益の何%か。
ウ. ある日、庭の草むしりをするのに、兄は2m四方、弟は1m四方の広さを担当した。兄の仕事量は弟の仕事量の何倍か。
ェ. 大学の3年生と4年生に家庭教師の経験の有無をたずねたところ、半数が「ある」と答え、4年生がその60%を占めた。家庭教師経験のある3年生は全体の何%か。
<選択肢>
- アとイ
- アとウ
- アとエ
- イとウ
- イとエ
- ウとエ
【解答・解説】
答え: C. アとエ
このような非言語の問題では、計算に含まれる要素と構造の共通点に着目する必要があります。
アとエには、文章中で「全体の中でAに分類されるものの割合」と「Aに分類されるものの中で、さらにBに分類されるものの割合」が示され、最終的に「Bに分類されるものが全体に占める割合」が問われるという構造が共通しています。
計算式で表すと、以下のような共通の構造を持っていることが分かります。
(全体の中でAに分類されるものの割合)×(Aに分類されるものの中で、さらにBに分類されるものの割合)=(Bに分類されるものが全体に占める割合)
よって、正答は「C. アとエ」となります。
構造的把握力検査を解くためのコツ
【言語】文章の前半と後半の論理関係を見極める
言語の問題では、文章の重要な要素は前半と後半に分けて配置されます。
まず前半の要素と後半の要素に着目し、論理関係を見極めることが大切です。
この論理関係の違いにより、文章はグループ分けされるため、この工程をスムーズに行えるようにすることで、素早い解答に繋がります。
構造的把握力検査では20分間で約20問を解くことになり、1問あたり1分以下の所要時間で解かなくてはいけません。
そのため、問題を解き始める際に最初にどこに注目するべきかをしっかりと頭に入れておくことをおすすめします。
そうすることで、効率的に解き進めることができます。
【非言語】頭の中で文章を計算式に変換する
非言語問題の文章はシンプルな構造になっています。
そのため、文章の内容を基に頭の中で計算式を立てることも難しくないでしょう。
足し算なのか、掛け算なのか、割合の問題なのか、確率の問題なのかということに注目して計算式を立てることで、各文章から導き出された計算式の構造の共通点と違いを効率的に把握することができます。
非言語の問題は計算結果を答えるものではないので、実際に数値を出す必要はありません。
「計算する問題」ではなく、あくまでも「計算式を立てて考える問題」であるので、そこをしっかりと意識して、素早い解答ができるようにしましょう。
【言語・非言語】問題のパターンを把握する
構造的把握力検査の問題は、言語・非言語問わず、ある程度出題パターンが決まっています。
言語では「意思⇔願望」「推測⇔断定」などのように各文章の前半と後半の論理関係の違いにいくつかの頻出パターンがあります。
また、非言語では「合わせて」「〇%」「その差は」などのように文章中の表現にパターンがあります。
頻出の問題パターンを把握しておき、実際に問題を解くときに「この問題はあのパターンだ」というように推測することで、解答の道筋が見え、より効率的な解答ができるでしょう。
構造把握検査で高得点を取るための対策法

対策本を繰り返し解いてコツをつかむ
先述した通り、構造的把握力検査はSPIの能力検査の中でも難易度が高いことで知られています。
構造的把握力検査のような問題は、ほとんどの人はあまり経験が無い種類の問題なので、高得点を狙うなら対策をして問題に慣れることが不可欠です。
そのため、最低でも対策本を一冊は購入して、一通り解き切るようにしましょう。
まずは時間が掛かっても良いので、最後まで問題を解けるようにしましょう。
そして、解いて、解答・解説を読んでまた解くという工程を地道に繰り返しましょう。
多くの問題解説を読んでコツを理解し、そのコツを意識して解く練習を繰り返すことで、効率の良い解き進め方が身に染みてきます。
また、練習を繰り返すことで自信がつき、本番に落ちついて臨めるようになるでしょう。
焦らず冷静に解き進められるようにすることも高得点に繋がります。
対策本には構造的把握力検査の内容が含まれていないものもあるので、よく確認してから購入するようにしましょう。
本番と同じ時間内で解く練習をする
構造的把握力検査は、SPIの他の科目ほど模擬試験が充実していません。
そのため、実際の試験に近い環境での練習としては、タイマーで時間を計って、試験1回分の問題(約20問)を本番の制限時間と同じ20分以内に解くという方法がおすすめです。
それを繰り返すことで、どのようにすれば効率的に解けるのか、どのようなスピード感で1問を解くべきなのかという感覚を掴んでいけます。
時間を計らずに問題を解く練習だけしていると、本番で時間が足りないということになりかねないので、必ず一度は時間を計って解いてみましょう。
また、通しでの練習の他にも、1問を1分以内に解くという練習をするのも効果的です。
構造的把握力検査以外の分野の対策もする
構造的把握力検査以外の言語・非言語分野の勉強も怠らないようにしましょう。
基礎能力を測るものであるため、たとえ構造的把握力検査の得点が良くても、他の分野の得点が一定の水準に達していないと落とされてしまう可能性があります。
特に、難関企業の選考を突破するためには、言語・非言語分野は8割以上が必要になることが多いです。
また、構造的把握力検査の前に他の分野を受検する場合には、他の分野の手応えが悪いと構造的把握力検査を受検するときにメンタルに響き、結果にも悪影響を与えてしまう可能性もあるでしょう。
全体で良い結果を出せるに越したことはないので、受検する分野は全てしっかりと対策することをおすすめします。
構造把握検査対策のおすすめの問題集
2027最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集

出典:Amazon
「構造的把握力」の他にも「言語分野」「非言語分野」「英語」、そして「能力検査」といった全ての分野の最新の頻出問題が網羅された一冊です。
解答・解説では「素早く確実に解ける解法」が紹介されているため、スピーディに解くコツをしっかりと掴みたいという方にもおすすめです。
2027年度版 SPI3 構造的把握力検査をひとつひとつわかりやすく。

出典:Amazon
構造的把握力検査の対策に特化した、数少ない問題集です。
問題が出題パターンごとに整理されており、着目すべきポイントもパターン別に解説されているので、一つ一つコツを掴みながら学習していくことが可能です。
構造的把握力を絶対に落としたくないという人はこちらを使って対策を進めるのがおすすめです。
構造的把握力が出ることがわかったらすぐに対策しよう
構造的把握力は一部の企業でしか出題されませんが、その分重要視されている可能性の高い科目です。
しかし、練習する機会が少ないため、高得点を狙うには時間をかけた対策が必要になります。
志望企業のSPIで構造的把握力が出ることがわかったら、対策本を中心とした対策を始めるようにしましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen







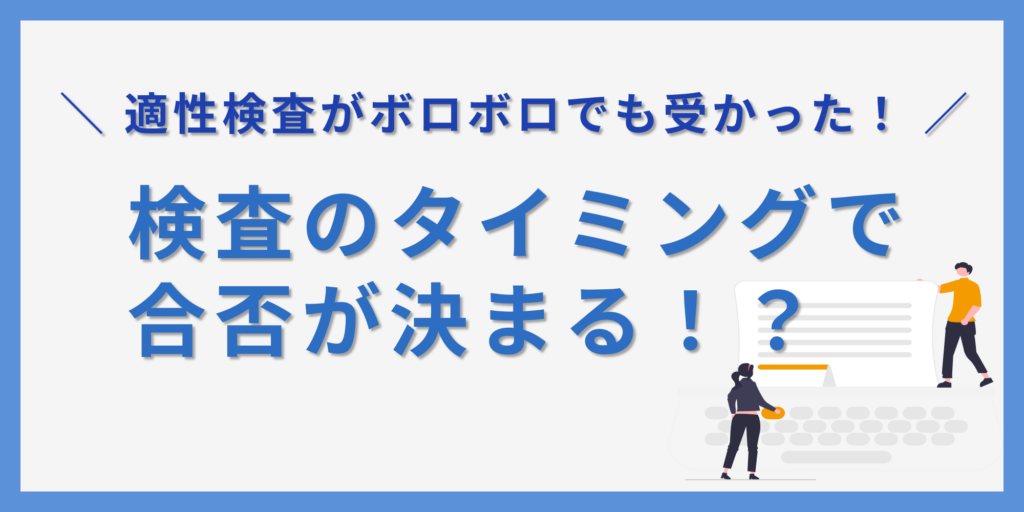 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?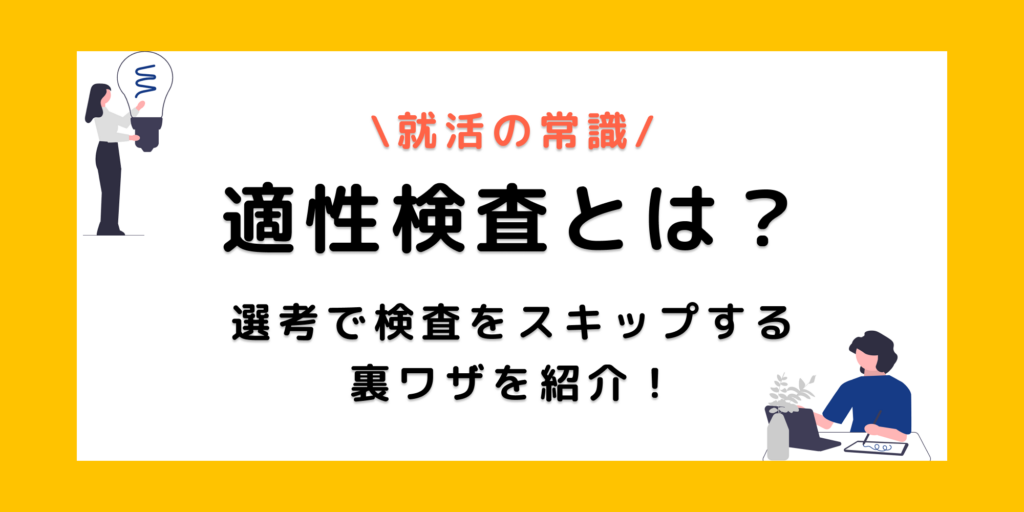 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!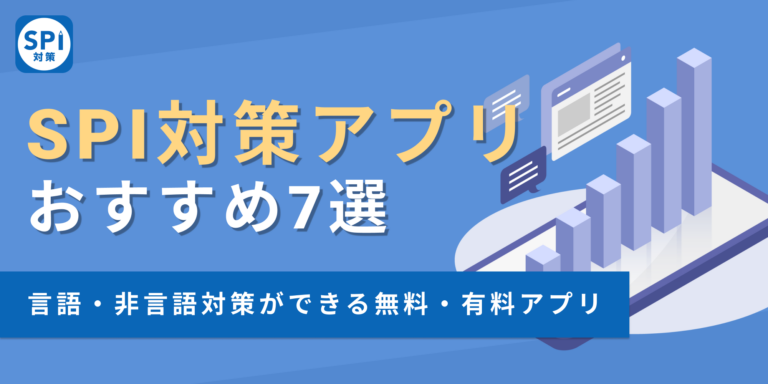 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ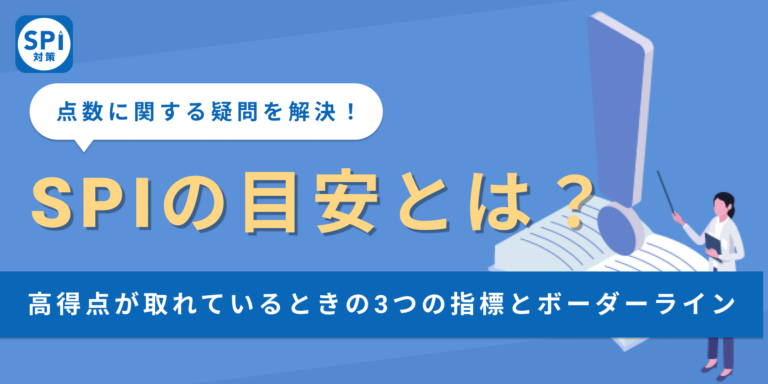 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点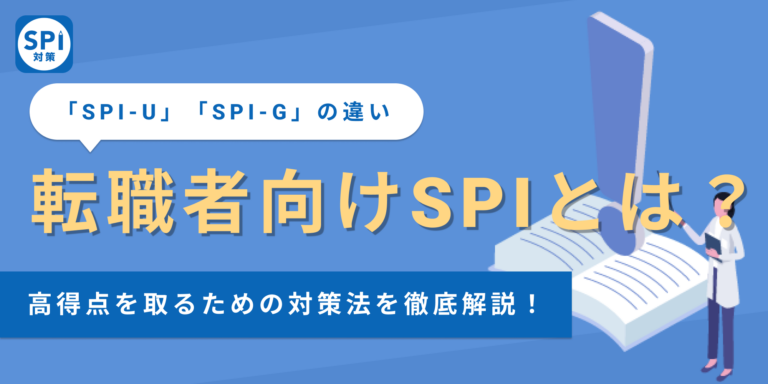 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説