
Webテストとは?頻出5形式を中心に受検の流れを解説【例題あり】 | SPI対策問題集
Webテストは応募者の職業への適性を測る「適性検査」の一種であり、就活を進める上で避けて通れないものです。
Webテスト対策を怠っていると、まず間違いなく不採用に終わってしまいます。しかし、「そもそもどんなテストなの?」「SPIと何が違うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
そこで、まずはWebテストの基本を説明し、押さえておきたい主要なWebテストの一覧を紹介していきます。実際に受検する時の流れもあわせて取り上げているので、本番が不安な方もぜひ参考にしてください。
目次
Webテストは「適性検査」の形式の1つ

能力と性格を測って自社への適性を確かめるテスト
Webテストは、受検者の能力と性格を測ることを目的としたテストです。企業はWebテストの結果を通じて、応募者が自社や業務へ適性があるかどうかを確かめています。
検査は、言語や非言語能力などを問われる「能力検査」と、性格や考え方に関する質問をする「性格検査」に分かれています。
このうち、テストの種類によって差が出やすいのは能力検査の内容です。言語・非言語の2科目が基本ですが、中には全く違う形式で出題する適性検査もあります。
また、同じ言語と非言語でも、問題の内容にはかなり幅があります。例えば、SPIでは1問10秒程度で解くような短い問題が多いのに対し、玉手箱では1問30秒~1分程度かけられるような長めの問題が多いです。
企業は自社で求められる能力に応じたWebテストを選んで実施するため、どの科目も重視されていると考えましょう。
受検しやすいため実施数が多い
Webテストは企業にとって手間が少なく、就活生も受ける時間を確保しやすい便利な形式です。送られてきたURLを開いて受検するだけなので、外出や持参物の用意が必要ありません。
そのため、他に現地会場などの受検形式があっても、Webテスト形式が選ばれやすい傾向にあります。
Webテスト形式かどうかは受検案内から簡単に判別できるため、「会場に行く必要があるのかわからない…」と悩むことはないでしょう。Webテストと並んで頻出のテストセンター形式の場合は、会場と日時を予約するよう伝えられるはずです。
足切り目的で使われる傾向
応募者が多い企業では、全員に面接や書類審査をしていると膨大な採用コストがかかってしまいます。そこで、一定の基準を下回る応募者を一斉に「足切り」し、詳しく審査するべき応募者を絞り込むことが多いです。
こうした足切りの判断のために広く使われているのがWebテストです。全国の応募者から効率的に有用な人材を絞り込めるため、人気企業では高い確率でWebテストを受けることになるでしょう。
ただし、足切り目的だからといって、通過した後の選考に一切影響がないわけではありません。能力の高さや性格の傾向は、その後の面接などでも判断材料のひとつとして扱われます。「最低限だけ取っておけばいい」という考えで臨むと、最終的な合否に響く可能性もあるでしょう。
主要なWebテスト一覧
| 検査の名前 | 特徴 |
| SPI | ・実施企業が最も多い
・言語・非言語・性格検査が必出 |
| 玉手箱 | ・出題科目が固定
・Webテスト形式は「Web-GAB」と呼ばれる |
| CAB | ・IT系での実施が多い
・非言語に特化した問題内容 |
| CUBIC | ・出題内容が細かくカスタマイズされる
・性格検査に独特の指標がある |
| ミキワメ | ・出題科目が固定
・性格検査のフィードバックが受けられる |
| TG-WEB | ・SPIを全体的に難しくしたような内容 |
| クレペリン検査 | ・1桁同士の足し算を繰り返して作業の適性を測る |
| TAP | ・科目や難易度の設定が幅広い |
| TAL | ・図形を配置して自分を表現する独特の問題が出る |
| BRIDGE | ・計数に特化した難しい内容 |
| SCOA | ・常識問題まで含まれる出題範囲の広さ |
| 3E-IP | ・構造把握に近い問題が多く出題 |
これらは、就活で目にすることが多いWebテストの一例です。この中でも、SPI・玉手箱・CAB・CUBIC・ミキワメは特に実施数が多いため、個別に特徴を解説していきます。
就活で最頻出の「SPI」
- 言語(語彙力問題・長文読解など)
- 非言語(計算・図表・文章問題など)
- 性格検査
- 英語・構造的把握力(一部企業が追加で出題)
SPIは、最も多く利用されている適性検査です。大手企業から中小企業まで幅広く導入されているため、新卒採用においては「まずSPIを突破できるかどうか」が一次関門となるでしょう。
出題科目は「言語」「非言語」「性格検査」の3つが基本です。言語分野では語彙や読解力、非言語分野では四則演算・割合・確率・速度算など、中学~高校レベルの基礎的な能力が問われます。
難易度は高くないものの、出題範囲が幅広いため対策を完璧にしにくい点が特徴のひとつです。
就活する上で、SPIを受検する機会は何度もあるでしょう。対策しておいて損はないテストといえます。
人気企業で頻出の「玉手箱(Web-GAB)」
- 言語(長文読解)
- 計数(図表の読み取り)
- 性格検査
玉手箱はSPIの次に実施数が多く、特に人気の高い大手企業で出題されやすい適性検査です。Web上で受検できる形式は「Web-GAB」とも呼ばれています。
出題科目は「言語」「計数」「性格検査」の3つで、問題の種類は固定です。言語は長文読解、計数は図表の読み取り問題が出題されます。
言語・計数の問題は時間がかかりやすく、時間制限は厳しめです。時間切れで大きく点数を落とす場合もあり、SPIよりも難しいと感じる人は多いでしょう。
IT系企業で多く実施されている「CAB」
- 暗算
- 法則性
- 命令表
- 暗号
- 性格検査
CABは非言語分野に特化した適性検査で、主にIT系企業で実施されています。プログラマーやSE志望の方は受検する機会も多いでしょう。
出題科目には単純な計算問題も含まれますが、多くは図形の変化を読み取る「命令表」「暗号」などの独特な問題です。数学の学力を問う問題とはやや異なるので、CABに集中した対策が必要になります。
非言語特化とはいえ、高い計算力は求められないため、数学が苦手な人でも高得点を狙うことが可能です。
出題方法の幅が広い「CUBIC」
- 言語(語句の意味・長文読解など)
- 数理(四則演算・データの読み取りなど)
- 図形(図形の分割・展開図など)
- 論理(推理など)
- 英語(語彙力・長文読解)
- 適性検査(性格検査)
CUBICは問題のカスタマイズ性が高く、企業によって様々な形式で出題されることが特徴です。重視する能力に合わせた問題が選ばれるため、どれも高得点を狙いにいきたいWebテストといえます。
基本的な問題内容はSPIなどの標準的な言語・非言語と類似しており、難易度は高くありません。しかし、幅広い出題範囲から何の問題が出るのかわからないため、難しいと感じることも多いです。
また、非言語にあたる問題が「数理」「論理」「図形」の3科目に分かれて出題されるため、出題数が多くなっています。非言語分野が苦手な方は、重点的な対策が必要になるでしょう。
導入企業が急増中の「ミキワメ」
- 言語(穴埋め・並び替え)
- 計数(図表の読み取り・推理・暗号)
- 性格検査
ミキワメは、近年導入企業が急増している比較的新しい適性検査です。SPIに近い内容ですが、性格検査のフィードバックを受けられるという点が異なります。
性格検査の回答から、行動特性やストレス耐性などを細かく分析し、所感を後日受け取ることができます。その時の選考だけでなく、他の企業に応募する際の自己分析の材料としても活かせるWebテストです。
ベンチャーや中小企業では、従来の適性検査からミキワメに乗り換えているケースがみられます。逆に、大企業では採用実績の多いSPIなどを引き続き実施するというケースが多いです。
Webテスト受検の流れ【4ステップ】
①受検用URLにアクセス
②受検環境や不正行為をチェック
③検査中は中断できないことが多い
④結果は確認できない
①企業から受検用URLが送られてくる
Webテストの受検が必要かどうかは、企業からの受検案内を見れば判断できます。Webテストが実施される場合、「受検用URL」「受検期限」などを記載していることが一般的です。
ただし、このURLは「テストセンターの予約用URL」という可能性もあります。URLを見ただけではどちらか判別することはできないので、受検案内が届いたらすぐにURLにアクセスしてみましょう。
URLを開いただけですぐにテストが始まるような適性検査はありません。必ずログイン画面や確認画面を経て開始されます。また、アクセスしたことは採用担当者には通知されないので、時間なども気にする必要はありません。
開いたページで開始画面まで進めるようであれば、Webテストだと断定できます。開始さえしなければ問題はないため、一度ページを閉じてしっかりと準備を行いましょう。
②受検環境や不正にあたる行為をチェック
Webテストの受検前にしなければならない準備は、テスト対策だけではありません。適性検査によって異なる「受検環境の要件」や、「不正行為の一覧」を必ずチェックしておきましょう。
見落としがちなのは「Webカメラ・マイク必須」「身分証の提示が必要」「スマホ使用禁止」などです。特に、不正行為の基準をわかっていないと思わぬ形で失格処分を下されるおそれもあるため、1つずつ慎重に確かめましょう。
また、休日や深夜帯は受検できないというWebテストもあるので、受検可能な時間についても確認しておくことをおすすめします。期限ギリギリに受けようとして、受付が終わっていた場合、そのまま未受検となってしまいます。
③検査を開始したら中断できないことが多い
準備が整ったらWebテストを開始しましょう。テスト中の離席や中断は認められていないケースが多いので、30分~1時間程度はパソコンの前を離れられません。予めスケジュールも空けておく必要があります。
また、テスト中のパソコンで余計なソフトウェアを起動していると、システムに不正として検知される可能性があります。ブラウザ以外は何も起動していない状態で検査を受けることが重要です。
もしも検査中にネット回線のトラブルなどで中断してしまった場合は、すぐにサポートへ連絡しましょう。やむをえない事情であることが認められれば、再開や再受検の案内を受けることができます。
④結果は確認できない
Webテストの受検後は、原則として自身の成績は確認できません。後で自己採点することは可能ですが、問題と解答まで全て覚えている必要があり、厳密なスコアを割り出すことは難しいでしょう。
しかし、普段の練習と手応えを比べ、「大体〇割は取れただろう」と推測することは可能です。
通しの練習を何度か行っていれば、手応えに対する得点の目安も大まかにわかっているはずです。また、最終的には企業の求める水準を超えているかどうかが合否を分けるので、厳密な得点はわかっていなくても問題ないでしょう。
Webテストについてよくある質問
どんな企業が実施してる?
Webテストは、業界や規模を問わず幅広い企業で実施されています。特に、大手企業や人気企業では応募者が多いため、効率的に応募者を絞り込む目的で実施されるケースも多いです。
業界によってある程度の傾向はあるものの、「〇〇業界だからこのテスト」といった確実な指標はありません。
志望企業の実施する適性検査が知りたい場合、過去の実施状況を調べてみると確実性が高いでしょう。就活サイトなどの口コミを参考に判断することが可能です。
ただし、就活サイトの情報が必ず正しいとは限りません。「多くの人が同じことを言っている」「複数サイトで同様の記述がある」などの点は必ず確認しましょう。
勉強は必要?
Webテストに勉強は必須です。大学受験のテストとは全く異なる内容であり、ノー勉で臨んで高得点を取るのは非常に厳しいでしょう。
問題自体は中学・高校レベルの知識で解けるようになっている適性検査がほとんどです。しかし、制限時間の短さから「わかるけど間に合わない」という状況になってしまいます。
出題範囲は基本的に決まっているので、勉強時間は10~20時間程度で最低限済ませられます。就活中でもコツコツ進めれば十分に届く勉強量なので、面倒でも勉強は行うようにしましょう。
ボーダーラインはどれくらい?
Webテストの合格ボーダーラインは、テストの種類と企業によって左右されます。例えば、代表的なWebテストであるSPIの場合、5~6割もあればほとんどの中小企業を通過できるとされています。
一方、大手企業や人気企業の場合、より優秀な人材を採用するために8~9割をボーダーにしていることもあります。
こうした合格基準は公開されていませんが、過去の受検者の体験談から推測することが可能です。似たような規模の企業はボーダーも似通っているケースが多いため、志望企業以外のボーダーの情報も参考になるでしょう。
会場に行かなくてもいいの?
Webテストは自宅のパソコンから受けられるため、会場に行く必要はありません。会場に行って受検しなければならないのは「テストセンター」や「ペーパーテスト」などの形式です。
テストセンターの場合は日時と会場の予約が求められ、ペーパーテストの場合は会場が指定されているはずです。受検用URLからそのまま検査を開始できる場合は、自宅で受けて問題ありません。
なお、Webテストはネット環境があれば自宅以外でも受けることができます。しかし、落ち着いて集中できる環境としては自宅が一番でしょう。
雰囲気を掴もう!Webテストの問題例
最後に、代表的なWebテストである「SPI」「玉手箱」「CAB」について、それぞれの問題例を紹介します。対策の第一歩として、問題の雰囲気だけでも掴んでおきましょう。
SPIの例題
【SPI・言語の例題】
最初に示された二語の関係を考えて、同じ関係のものを選びなさい。
なべ:ふた
ア 着物:帯
イ 薔薇:花
ウ 夢:うつつ
<選択肢>
- アだけ
- イだけ
- ウだけ
- アとイ
- アとウ
- イとウ
A.アだけ
【SPI・非言語の例題】
XとYが野球の試合を3回する。Xが勝つ確率、Yが勝つ確率、引き分けとなる確率は全て等しく1/3である。引き分けも試合数に数えるとする。Xが2回勝ち、1回負ける確率を求めよ。
<選択肢>
- 1/9
- 1/3
- 2/9
- 1/27
A.1/9
玉手箱の例題
【玉手箱・言語の例題】
次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。
火山岩と深成岩は、マグマが冷却する過程と環境の違いによって異なる特徴を持っている。火山岩は地表近くで急速に冷却するため、細粒で均一な組織を持ち、斑晶と呼ばれる目に見える結晶を含むことがある。一方、深成岩は地下深くでゆっくりと冷却するため、大きな結晶構造を形成し、鉱物の境界がはっきりと識別できる。
岩石の形成過程は、地球のテクトニクス活動と密接に関連している。プレート境界における岩石の生成は、マグマの上昇、地殻変動、そして岩石の変成作用によって引き起こされる。例えば、海嶺では新しいマグマが地表に噴出し、大陸の衝突地帯では高温高圧下で岩石が変成され、異なる種類の岩石が形成される。これらの過程は、地球の地質学的な進化を理解する上で重要な要素となっている。
鉱物学の最新研究によれば、岩石の形成過程は単純な物理化学的変化ではなく、微生物の活動も重要な役割を果たしている可能性が示唆されている。特に堆積岩の形成において、微生物が鉱物の結晶化や化学組成に影響を与えることが明らかになりつつある。地球上の岩石形成メカニズムは、これまで考えられていたよりもはるかに複雑で、生物学的要因が関与していることが分かってきたのである。
<選択肢>
- 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。
- 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。
- 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。
(1)火山岩は地下深くでゆっくりと冷却し、深成岩は地表近くで冷却することから、両者の結晶構造と組織は異なる特徴を持っている。
(2)テクトニクス活動による岩石の形成は、プレート境界での新しいマグマの噴出と地殻変動、そして岩石の変成によって引き起こされる。
(3)岩石の形成は、地球のテクトニクス活動と深い関わりを持っている。
(4)マグマの上昇と地殻変動は、岩石の生成過程において同じ環境と条件で進行する。
【解答】(1)B
(2)A
(3)A
(4)B
【玉手箱・計数の例題】
【 】に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。
40×【 】÷0.5=50
<選択肢>
- 4/5
- 5/4
- 1/5
- 5/8
- 8/5
D.5/8
CABの例題
C
Webテストの受検が決まったらすぐ対策を始めよう
Webテストは就活を進める上で避けては通れないものです。志望企業でWebテストを実施することがわかったら、いち早く対策を始めることが重要になります。
ノー勉で受かるほど簡単なものではなく、学校のテストとは異なる能力も求められます。足切りは確実に回避できるように備え、なるべく高得点を狙って対策を重ねましょう。
また、Webテストは種類によって出題内容も様々です。対策が必要なWebテストを見極めて、効率良く時間を使うようにしましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen














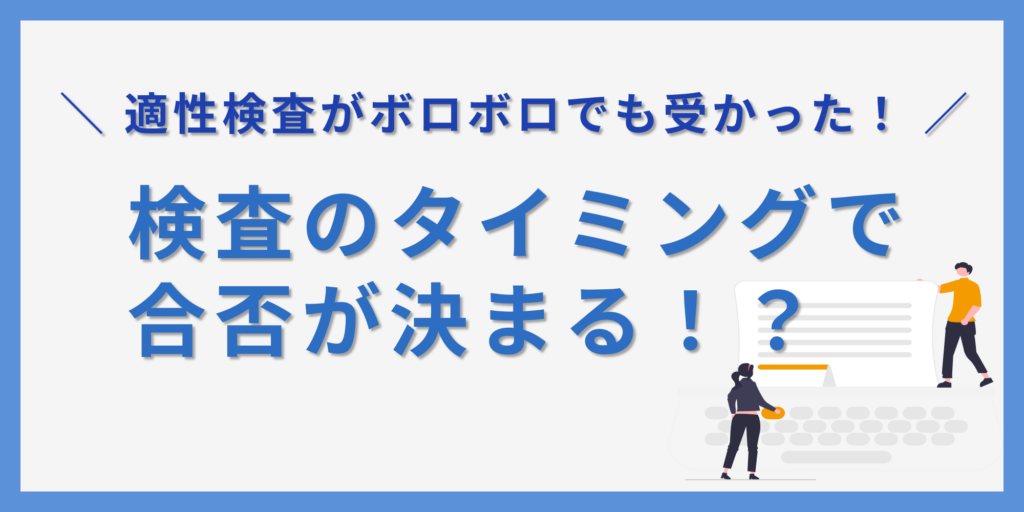 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?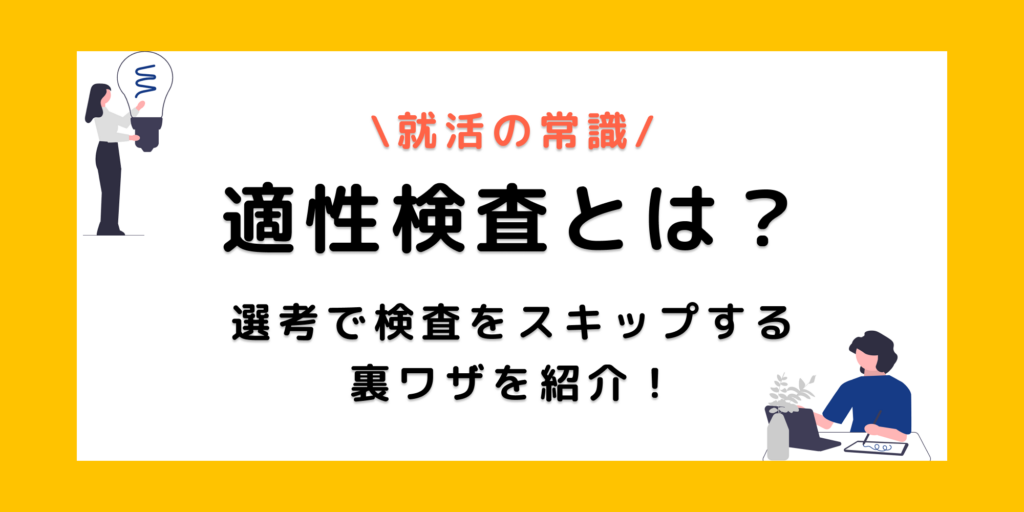 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!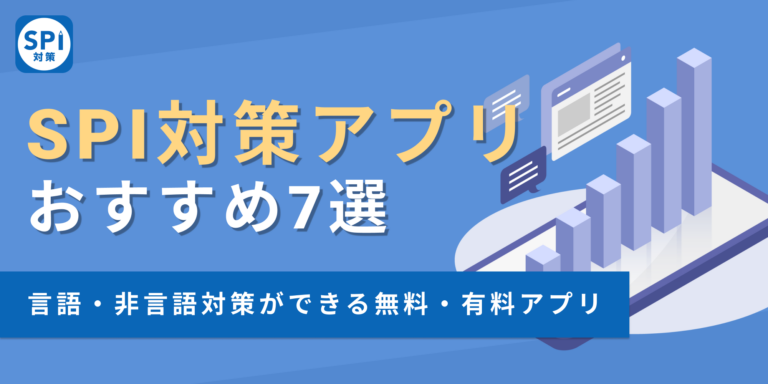 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ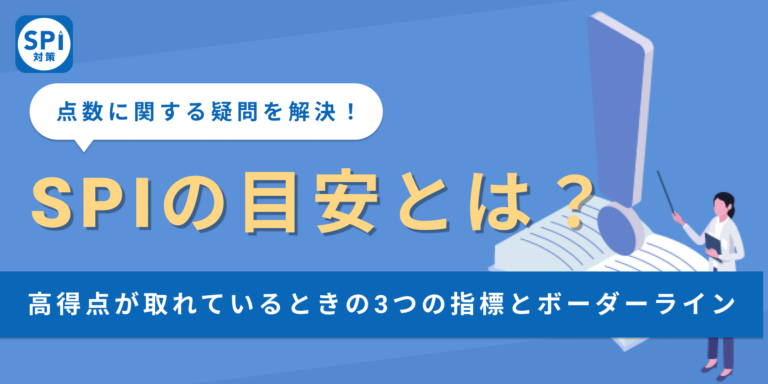 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点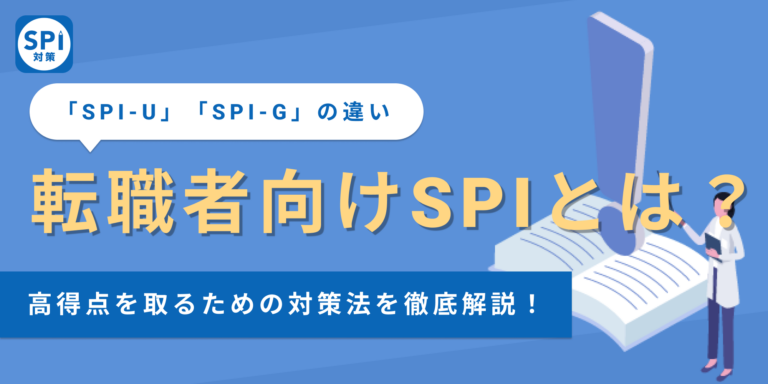 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説