
SPI選考がボロボロでも受かった意外な理由5選!受検しない就活戦略も紹介 | SPI対策問題集
就活で最も多くの企業が導入しているSPI。受検後に「ボロボロだった…」と感じても、実際には内定を勝ち取ったという就活生は少なくありません。
これは単なる偶然ではなく、企業の選考基準や評価方法に理由があるのです。だからこそ、SPIが思うように解けなかった場合でも、その後の面接や選考準備を入念に行うことが重要です。
本記事では、SPIがボロボロでも受かった理由をわかりやすく解説するとともに、その後の選考で意識すべきポイントや、SPIが苦手な人向けの就活戦略も紹介します。
目次
SPIがボロボロでも受かった意外な理由
志望者数が少ないまたは大量採用の場合
SPIの出来が悪かったと感じても、通過できた背景には「志望者数が少なかった」または「企業が大量採用枠を設けていた」可能性があります。
特に地方勤務や専門職、ニッチな業界の求人では志望者数が少なく、一定の基準さえ満たしていれば通過できるケースもあります。
また、大手企業の総合職などで100人単位の大量採用を行う場合、選考の早期で母集団を絞りすぎると、その後の面接や最終選考で人が足りなくなるリスクがあります。
そのため、SPIの合否ラインが緩やかに設定されることがあり、本人は「ボロボロだった」と思っていても、実際は問題なく合格ラインに達していたということもあり得ます。
実は意外と点数が高かった
SPIが難しく感じた=点数が低いとは限りません。SPIには、受検者の正答率によって問題の難易度が変化する「適応型出題」が導入されている場合があります。
この形式では、正解を重ねると難易度が上がっていくため、後半になるほど問題が難しくなり、「全然できなかった」と感じやすくなります。
しかし実際には、難しい問題にチャレンジできている時点で高得点ゾーンに入っていたという可能性もあるのです。
さらに、SPIの一部は相対評価で判定されているため、周囲の受検者の出来があまりよくなかった場合、自分のスコアが相対的に高くなることもあります。
特に選考初期では絶対的な満点を求めているわけではなく、「一定のラインを超えているかどうか」が判断基準となります。そのため、自分で感じているほど結果が悪くなかった、というケースは珍しくありません。
企業のSPIのボーダーが低い
企業によって、SPIに対する評価基準は大きく異なります。特にSPIを形式的に導入している企業や、能力検査よりも人柄・面接を重視する傾向のある企業では、SPIの通過基準が非常に低く設定されていることがあります。
例えば、SPIは全受検者に一律に課しているが、実際には極端に点数が低い人だけをふるい落とし、それ以外は面接で見極めるというケースです。
特に、採用にかけられる時間や人手が限られている企業では、SPIの結果を細かく分析せず、「このレベルなら問題ない」と大まかに判断することもあります。
また、SPIの結果がその後の選考評価にほとんど使われていない場合、通過の可否には大きく影響しない可能性もあります。
こうした企業では、SPIが参考程度にとどまることが多いため、少々ミスをしても通過できたという結果に繋がるのです。
性格検査の結果がよかった
SPIには、能力検査と並んで性格検査があります。これは数値的な能力を見るテストと異なり、受検者の性格傾向や職場での行動特性、価値観などを測定するものです。
企業は、この性格検査を通じて「自社に合う人材かどうか」「チームの中でうまくやっていけそうか」などを判断しています。
実はこの性格検査の評価が高ければ、能力検査の点数が多少悪くてもカバーできることがあります。
真面目で継続力がある、協調性が高くチームプレーが得意、ストレス耐性が高い、などの結果が出ていれば、企業は「一緒に働いてみたい」と前向きに考えることが多いのです。
反対に、能力検査で高得点でも、性格検査で大きく企業文化とズレていた場合、不合格となることもあります。「SPI=頭脳勝負」ではないということを頭に入れておきましょう。
書類審査で評価がよかった
Webテストの結果が良くなくても、書類審査で高評価を得ていれば次の選考に進める可能性があります。
特にエントリーシート(ES)や履歴書において、志望動機に一貫性があり、企業研究も十分にできていることが伝わる内容だと、会ってみたいと思われることもあります。
また、ガクチカが企業の事業や価値観とマッチしている場合、SPIの点数よりもその人の経験や考え方が重視されることもあります。
企業によっては「SPIの結果が少し悪くても、面接で話してみて最終判断したい」と考えるところもあり、特に人物重視の企業や、選考段階で柔軟性のあるベンチャー・中小企業に多く見られます。
つまり、書類の段階で「この人を落とすのはもったいない」と思わせる内容を書けていれば、SPIが多少ボロボロでも突破できるのです。
次のSPIでボロボロにならないための対策法

基本問題を反復練習する
SPIで出題されるのは、大半が中学・高校の問題です。そのため、少し簡単だと感じても基本問題の反復練習を怠らず、確実に正解できる問題を増やしていくと、高得点に繋がります。
また、SPI対策を行う際にやりがちなのが、問題集を何冊も購入し、同時並行で進めてしまうことです。
しかし、SPIの出題パターンはほぼ決まっており、1冊を何度も繰り返し解くことで慣れることができます。
本番までに、問題文を読まなくても解答できるレベルを目指しましょう。
SPIは日本で最も多くの企業に採用されている適性検査であり、就活を通して一度は受検の機会があるでしょう。
何度も反復練習を行うためにはそれなりの時間が必要です。就活本番を迎える前に早めに問題演習を始めましょう。
模試や本番形式の問題集で時間感覚を掴む
SPIで高得点を取るカギとなるのが、時間配分です。
全4形式のうち、実際に企業に赴いて受検するペーパーテストとインハウスCBTは、1問ずつの制限時間が設定されていません。そのため、分野全体で時間配分を考慮する必要があります。
苦手分野や解答スピードは人によって異なり、どの分野にどのくらいの時間をかければいいかも違っています。最大限の力を発揮できる時間配分を探し、本番にも活かしましょう。
また、本番での緊張を和らげるためにも模試や本番形式の問題集は有効です。対策を十分にしていないと本番のイメージがつかず、緊張も増すでしょう。
一方、テストセンターとWebテストには1問ごとに制限時間が設定されており、これを過ぎると自動的に次の問題に移る仕組みになっています。
1問ずつに全力を注ぐとともに、何も選択せずに問題が進んでしまうことがないように注意しましょう。
苦手分野を分析し重点的に克服
SPI対策において、苦手分野の克服は必須です。総合得点で評価されるSPIでは、どれだけ得意な分野で高得点だったとしても、苦手分野で失点すると、結果的に全体の点数が下がってしまうケースが多いです。
企業はSPIを足切り目的で採用していることが多く、不合格に直結するかもしれません。
苦手分野を分析するためには、まず問題集を1周解き、他よりも時間がかかったり、難しいと感じた問題をピックアップしておきましょう。
その後、ピックアップした問題が分野ごとにどのくらいあったかを数えると、苦手な分野が可視化されるでしょう。
隙間時間もアプリやWebサービスを活用
スキマ時間を利用したWebテスト対策に便利なのが、スマホアプリです。スキマ時間を活用して実践的な対策が可能であり、大学やアルバイト・サークル活動などで忙しい毎日を送る就活生におすすめです。
特に、最も多くの企業で採用されていて、基礎的な問題の出題が多いSPIの対策をすることで、その他のWebテストにも活かすことができます。
また、スキマ時間に少しでも問題を解いておくことで、本番でボロボロになる可能性は低くなります。
SPI対策問題集では、5分でできる簡単レベル診断や本番想定模試が無料で利用できます。
練習問題も豊富に掲載されているため、練習にも困りません。また、手書きできるメモ機能も搭載しており、移動中や外出先でも本番に近い形式で対策を進めることができます。
ボロボロだけど受かった場合の準備事項
企業分析と自己分析の徹底
SPIに受かった後の面接では、企業側は志望度の高さを重視します。志望度をアピールするためにも企業分析を細かく行い、自己分析の結果を基に企業との相性の良さを伝えましょう。
特に、SPIの結果がボロボロだったにも関わらず受かった場合、性格検査での企業との相性や、書類選考の評価が良かったことが理由として考えられます。
これらの結果を裏付けできるような内容をアピールすることで、さらなる好印象に繋がるでしょう。
また、企業分析や自己分析は入社後のミスマッチをなくすためにも大切です。その企業で自分の強みを活かすことができるのかを見極めることで、長く活躍することが可能になります。
面接練習は念入りに
- 自己紹介
- 志望動機
- 自己PR
- 自分の強み・弱み
- ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)
- 将来のキャリアプラン
- 困難な経験の乗り越え方
- 逆質問
面接練習は念入りに行いましょう。SPIの結果が通知された状態の面接では、性格検査での回答と面接での発言に矛盾が無いかどうかに面接官は着目します。
聞かれそうな質問に対しての回答をガッチリ固めるのではなく、あくまでも自然体での会話のキャッチボールを意識します。
ただし、自然体と言っても全く準備せず面接に臨むのはNGです。面接で聞かれることの多い質問は必ず確認し、回答はある程度準備してから行きましょう。
面接練習を繰り返すことで、本番で落ち着いて対応できるようになります。自信を持って面接に臨めるように面接練習は抜かりなく行いましょう。
適性検査が2回ある場合はしっかり対策
近年、就活生の間で適性検査のカンニングが横行していることから、選考フローの中で2度の受検を課す企業が増えています。
特に、最初の適性検査はオンラインで、2度目は対面のリアル会場で実施する、というケースが多くなっています。
この場合、オンライン実施で高得点を取ったとしても、リアル会場での受検で極端に低い点数を取ってしまうと、カンニングを疑われます。
2度目の受検は、選考フローの中でも最終に近い段階で行われることが多いため、ここで不合格になるのはもったいないです。どの形式でも安定した得点が取れるよう、問題演習を積みましょう。
SPIがどうしてもボロボロになる人向けの就活戦略
インターン経由の選考ルートで進む
インターン経由の選考ルートでは、SPIなどの適性検査が課されないことが多い傾向にあります。
SPIで安定した点数がなかなか取れない人は、大学3年生の夏〜冬に行われるインターン参加を目指して早めに就活を始めましょう。
ただし、インターン経由の選考でSPIを使用しなくても、インターンに参加するための選考で既にSPIを受検済みの場合が多く、どちらにしても対策は必須です。
インターン経由だからといって油断するのではなく、十分に対策を講じましょう。
学生の強みに合った選考フローを持つ企業を探す
新卒就活の一般的な本選考フローは、「エントリーシート(ES)→適性検査(SPIなど)受検→複数回の面接→内々定」となっています。
しかしこれ以外にも、学生の強みを引き出すための選考フローを実施している企業もあります。
例えば、コミュニケーションを重視する企業ではプレゼンテーション課題やグループワーク、論理性を重視する企業ではケース面接(面接官から与えられるビジネス上の問題に対して解決策を考え、面接官に論理的に説明する面接形式)、フェルミ推定を課すことがあります。
これらをSPIの代わりとして、SPIを実施しない企業も増えてきています。
多くの企業で採用されているSPIですが、全企業が使っているわけではありません。自分の強みを活かせる選考フローで有利に就活を進めるのも一つの方法です。
SPI重視の業界・職種を避ける手段も
SPIを実施している業界・職種の中でも、選考においてどれくらい重視しているかは異なります。どうしてもSPIが苦手な場合は、SPI重視の業界・職種を避けることも考えましょう。
自社独自のWebテストを実施することの多い外資系企業や、面接での評価が重視されるベンチャー企業、実際の制作物・実績をまとめた作品集であるポートフォリオ提出が求められるクリエイティブ職の採用では、SPIが重視されない、もしくは実施されないことが多いです。
しかし、SPIはあくまでも中高レベルの問題が出題され、対策すれば点数が大きく伸びます。
SPIだけを理由に特定の業界・職種を避けてしまうのは勿体ないため、まずは一度問題を解いてみましょう。
SPIで失敗しても就活は終わりじゃない!
SPIの出来が悪くても次の選考に進める可能性があります。ボロボロだったと感じても諦めず、面接やグループディスカッションなどで良い評価が得られるように準備を行いましょう。
また、SPIでは出題傾向が決まっており、問題集を1周するだけでも大きく点数を伸ばすことができます。反復練習を行うとともに、模試や本番形式の演習を積みましょう。
SPIでどうしても安定した点数が取れない人は、インターン経由でSPIを用いない選考を探したり、SPI重視の業界・職種を避けることも一つの手です。
しかし、これは最終手段として捉え、まずはしっかり対策を行って基礎力を高めましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen










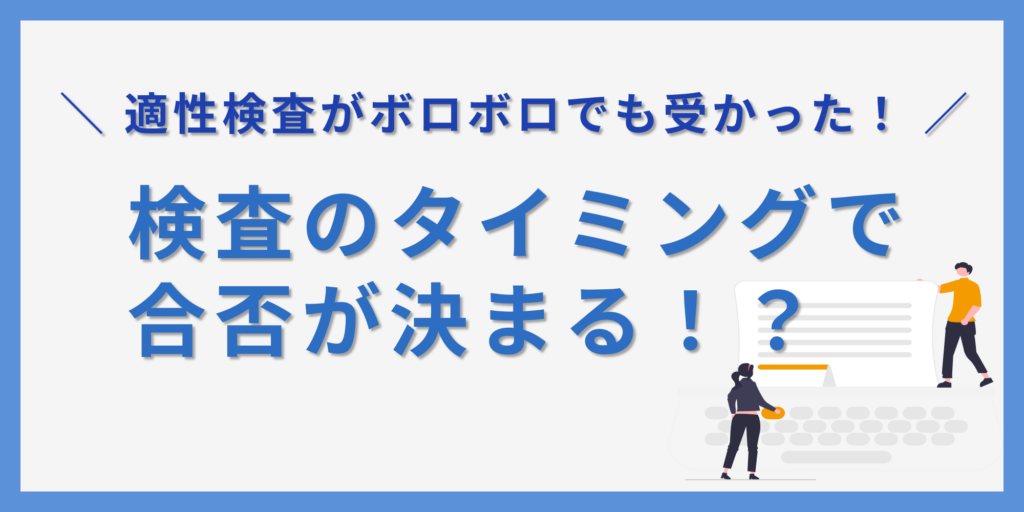 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?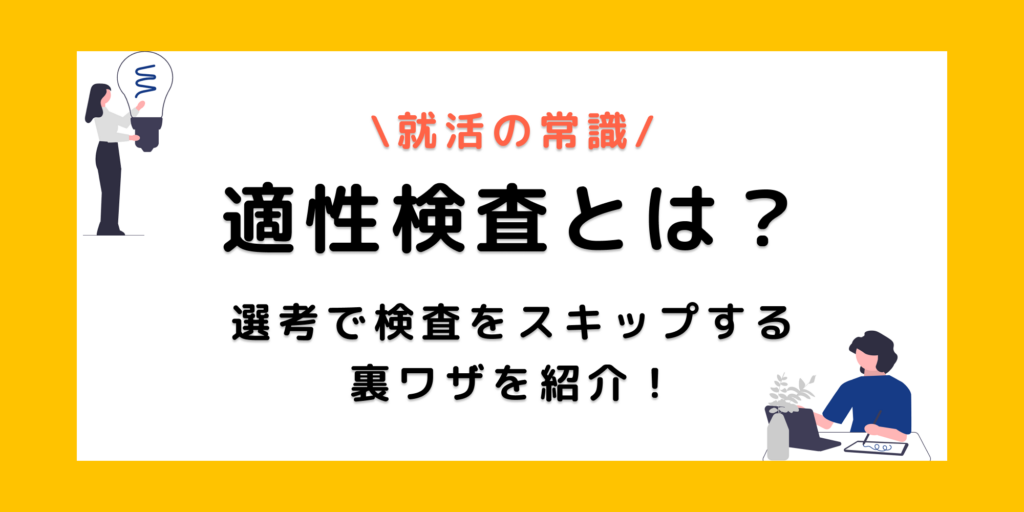 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!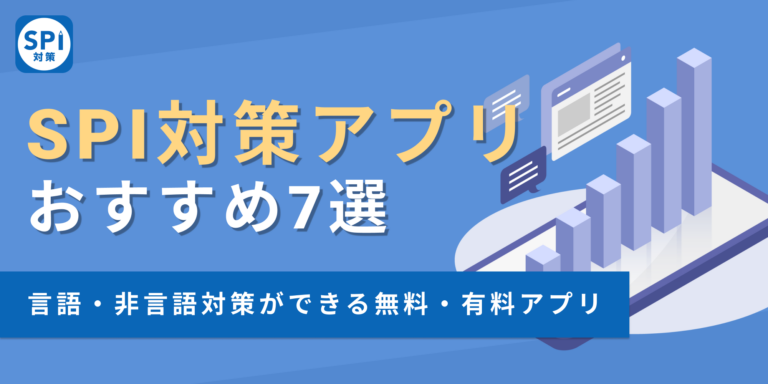 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ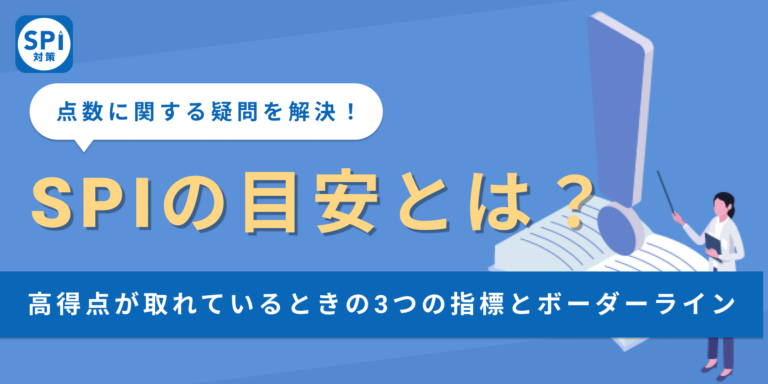 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点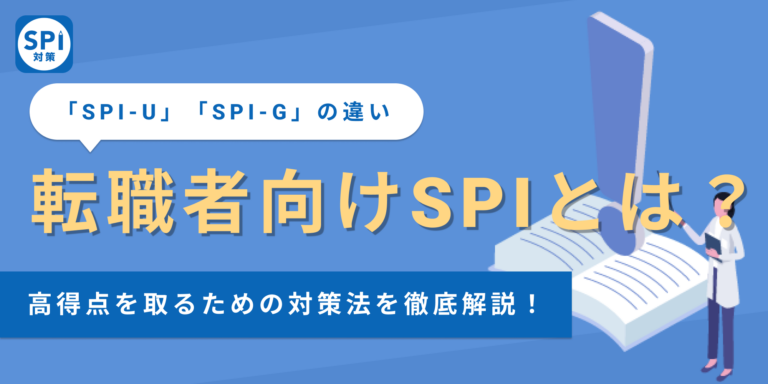 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説