
適性検査とは?就活・転職の第一関門を突破するための完全解説ガイド! | SPI対策問題集
就活で必ずと言っていいほど受検する「適性検査」。適性検査とは、応募者の能力や性格を測るテストの総称であり、「適性検査」という名称のテストは存在しません。
SPIや玉手箱、CABなど、種類や出題形式はさまざまで、受検形式に応じて対策も異なります。
本記事では、各適性検査の特徴や受検形式、効率的な練習法、模擬テストや対策本の活用方法まで、就活生が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
目次
適性検査とは?
就職活動において多くの企業が導入している「適性検査」は、応募者の能力や性格を客観的に測定し、採用判断に活かすための試験です。
代表的なものに「SPI」があり、これは数ある適性検査の一種に位置付けられます。SPI以外にも「玉手箱」「TG-WEB」「GAB/CAB」「CUBIC」「Compass」などがあり、特殊な形式を含めると10種類以上の適性検査が存在します。
つまり、就活で実施される能力検査や性格検査などの総称が「適性検査」です。
この段落では、適性検査の定義や目的、さらに採用選考における「足切り」の役割について解説します。
応募者の能力や性格を測るための検査
適性検査では、学力テストのように単純な知識量を問うのではなく、論理的思考力・計算力・文章理解力といった知的能力に加え、人柄や価値観、働き方のスタイルなども測定します。
企業はこの結果を参考にすることで、応募者が業務に必要なスキルを備えているか、また組織風土に合う人物かどうかを見極めることができます。
つまり、適性検査は、単なる「学力試験」ではなく、採用のミスマッチを防ぐための総合的な評価ツールとして活用されています。
企業は採用判断を効率化するために実施している
適性検査は、企業の採用活動を効率化するための手段として広く活用されています。
多数の応募者を面接だけで比較するのは時間や労力がかかりますが、適性検査を事前に実施することで、能力や性格を客観的に評価できます。
これにより、企業は必要な基準を満たす候補者を効率よく選び出すことが可能となり、面接や二次選考に進む人材の絞り込みが容易になります。
結果として、採用プロセス全体の効率と精度を高める効果があります。
選考フローの早い段階で実施される
適性検査は、多くの企業でエントリーシート提出や書類選考の直後といった、選考フローの早い段階に組み込まれます。
これは、応募者の能力や性格を早期に把握することで、面接やグループワークに進む候補者をあらかじめ絞り込む狙いがあるためです。
早い段階で実施されることで、応募者も適性検査の結果によって「次の選考に進めるかどうか」を早めに知ることができます。
そのため、不合格となった場合でも無駄に時間や労力を費やさずに済むという点がメリットです。
さらに近年はWeb受検が一般的になり、自宅や大学から受けられるケースも増えているため、遠方に住んでいる学生でも安心して受検できる環境が整っています。
足切りとして採用ラインに満たない応募者を見極める
適性検査には、企業が設定した基準に届かない応募者を次の選考に進めないようにする、いわゆる「足切り」の役割があります。
厳しいように聞こえますが、これは企業が大量の応募者の中から求める基準を満たす人材を選ぶために欠かせない仕組みです。
就活生にとっては、不合格となる場合もありますが、その経験を通じて自分の課題や強みを振り返るきっかけになります。
結果を前向きに受け止めることで、次の選考や他社への応募に活かすことができます。
適性検査は「能力検査+性格検査」が基本!

能力検査は言語・非言語が頻出
能力検査は、応募者の知的能力を測る試験で、言語力や計算力などの基礎学力に加え、論理的思考力や一般常識がどの程度身についているかを評価します。
構成は主に「言語(国語)」「非言語(算数・数学)」「英語」「論理的思考」などで、テストの種類によって出題内容や呼び方が異なります。
例えば、SPIでは基本的に「言語」と「非言語」が出題され、企業によってはオプションとして「英語」や「構造把握」などが追加されます。
玉手箱では「言語」「計数」「英語」の3科目が基本となります。このように、算数・数学に関する問題も「非言語」「計数問題」など呼び方が異なる場合があります。
そのため、受検するテストがどの種類なのかを事前に確認することが重要です。
能力検査の点数は、足切りの基準として用いられることが多く、一定の点数に満たない場合は不合格になることがあります。
企業によって基準は異なりますが、目安として最低でも7割以上を目指すと安心です。人気企業ほどボーダーラインは高くなるため、高得点を狙えるよう早めの対策が望まれます。
また、どの適性検査でも「言語」と「非言語」はほぼ必ず出題されるため、優先的に対策を進めることが効果的です。
性格検査は考え方や行動傾向を問われる
性格検査は、応募者の考え方や価値観、行動傾向など、個人のパーソナリティを測定する心理検査です。
代表例として、SPIの性格検査では約300問、玉手箱では約70問が出題され、検査の種類によって問題数や回答時間は大きく異なります。
この検査は、応募者の人柄や考え方を把握し、企業の社風や業務に合うか、適切な部署に配属できるかを判断する材料として活用されます。
中には企業の求める人物像に合わせて回答しようとする人もいますが、できるだけ自分の気持ちに正直に答えることが重要です。
性格検査には、矛盾した回答をチェックする仕組みが組み込まれている場合もあり、不自然な回答が多いと「自分を偽っている」と判断される可能性があります。
仮に性格検査を偽ったまま入社できたとしても、本来の自分と職場の要求に乖離が生じると、長く働くことが難しくなります。
そのため、性格検査では素直に回答することが最も安心で効果的な取り組み方です。
能力検査と性格検査はセットで受けるのが基本!
就職活動では、能力検査と性格検査をセットで受けることが一般的です。これは、どちらか一方だけでは応募者の全体像を十分に把握できないためです。
能力検査では、業務に必要な基礎的な知識や論理的思考力、計算力などが評価されますが、これだけでは職場での適応力やチームとの相性など、人物面の情報はわかりません。
一方、性格検査は応募者の考え方や価値観、行動傾向を測定することで、社風や業務スタイルとの適合度を判断する手がかりになります。
両方を組み合わせることで、企業は応募者の能力と人柄の両面を総合的に理解でき、採用後のミスマッチを防ぐことにつながります。
また、就活生にとっても、能力だけでなく人柄まで評価されることで、面接などの場で自信を持って自分をアピールしやすくなるというメリットがあります。
適性検査の代表的な種類
| テスト名 | 特徴 |
| SPI | ・言語、非言語、性格検査が必出 ・国内で最も広く利用されている ・様々な受検形式に対応 |
| 玉手箱 | ・言語、計数、英語、性格検査から企業が選んで出題 ・大手や外資系で頻出 ・PCで受検する形式のみ |
| TG-WEB | ・言語、計数、英語、性格検査を実施 ・ベンチャー企業で多い傾向あり |
| CAB |
・計数能力を重視した内容が出題 ・主にSEなどのIT系での実施が多い |
| GAB |
・言語、計数、性格検査が出題 ・外資系や金融などの人気企業で実施されやすい |
SPI
SPIはリクルートマネジメントソリューションズ社が提供する適性検査です。
就活生の間で最も広く利用されており、適性検査のシェアNo.1といわれています。現在使われているのは「SPI3」で、一般的には単に「SPI」と呼ばれます。
能力検査は「言語」と「非言語」の2分野で構成され、文章理解力や文法・国語力を測る言語分野、算数・数学を用いた論理的思考力や計算力を測る非言語分野が出題されます。
どちらも単なる知識ではなく、考え方や解き方、時間配分に慣れることが重要です。
企業によってはオプションとして「英語能力検査」や「構造的把握力検査」が課されることもあります。
英語能力検査は高卒レベルの長文読解や語彙問題が中心で、英語を日常的に使う外資系企業や商社で多く出題されます。
構造的把握力検査は、物事の関係性や構造を整理して理解する力を測る問題で、特にコンサルティングや総合商社、広告代理店などで求められます。
SPIの特徴として、問題数に対して制限時間が短い点があります。Webテストでは能力検査35分、性格検査30分、ペーパーテストでは能力検査70分・性格検査40分で、いずれも1問あたりにかけられる時間は短めです。
本番に備えて練習段階から時間を測り、自分のペースを把握しておくことが大切です。
玉手箱
玉手箱は、日本エス・エイチ・エル(SHL)社が提供する総合職向けの適性検査で、SPIと並んで代表的なテストです。
特に自宅で受検できるWebテストとしてはシェアNo.1を誇り、金融やメーカー系の人気企業で広く導入されています。そのため、SPIと併せて対策が必須といえます。
玉手箱の能力検査では「言語」「計数」「英語」の3科目が出題されます。
各科目には複数の問題形式がありますが、企業によって出題される科目や形式は異なるため、志望企業が過去にどの組み合わせで実施しているかを確認して対策することが重要です。
SPIとの大きな違いは、玉手箱の方が出題形式の種類が少なく、対策のポイントを絞りやすいことです。
SPIでは1つの形式に対し複数の問題パターンが出題されるため、幅広く準備する必要があります。その点、玉手箱は比較的効率的に対策できるといえるでしょう。
TG-WEB
TG-Webは、ヒューマネージ社が提供するWebテストで、SPIや玉手箱に次いで採用選考で利用される機会が増えています。
日系大手金融や外資系企業など、採用倍率の高い企業で導入されることが多く、難易度も高いとされています。
出題分野は「計数」「言語」「英語」「性格テスト」の4つで、SPIや玉手箱と大きくは変わりません。
しかし、「暗号問題」や「立体図形」といった、他のテストではあまり見られない形式の問題が出題されることもあり、慣れていないと時間が足りなくなる場合があります。
TG-Webは難解なテストですが、導入企業はSPIや玉手箱ほど多くありません。そのため、まずは志望企業がTG-Webを採用しているかを確認し、必要に応じて対策を行うのが効率的です。
その他(GAB/CABなど)
GABは、SHL社が提供する新卒総合職向けの適性検査で、知的能力や性格特性に加え、チームワークや職務適性まで評価できます。SPIより長文や図表問題が多く、時間が足りず難しいと感じる人も多いようです。
受検形式はテストセンターのC-GAB、自宅で受検できるWeb-GAB、企業実施のGABがあり、形式によって制限時間や問題数が異なるため事前確認が必要です。
CAB(Web-CAB)は同じくSHL社の適性検査で、主にSEやプログラマーなどコンピューター職向けです。
暗算・法則性・命令表・暗号などの論理的思考力を測る問題と性格検査で構成され、短時間で処理能力を問われるため、志望者は早めの対策が望まれます。
その他にも、CUBICやCompassなどマイナーな適性検査も多く存在し、企業ごとに実施されるテストは異なります。志望企業がどのテストを採用しているかを確認した上で、効率的に対策することが重要です。
適性検査の受検形式
| 受検形式 | 特徴 | メリット | 注意点 |
| Webテスト | 自宅PCやスマホから受検 | 移動不要で効率的 | 通信環境に左右される |
| テストセンター | 専用会場で受検 | 公平性が高い | 会場予約・移動が必要 |
| ペーパー(紙試験) | 会場でマークシート回答 | 操作に慣れる必要なし | 日程・場所が限定される |
| インハウス方式 | 企業の会場で受検 | 企業理解を深めやすい | 拘束時間が長くなる |
Webテスト
Webテストとは、自宅や大学などインターネット環境のある場所で受検できる適性検査の形式です。
SPIや玉手箱、TG-Webなど、多くのテストで採用されており、会場に行く必要がなく手軽に受けられるのが特徴です。
ただし、スマートフォンでの受検は推奨されていないため、できるだけパソコンから受検しましょう。
受検の流れはシンプルで、企業から届く案内メールのURLにアクセスし、IDとパスワードでログイン後、期限内にテストを受ければ完了です。試験開始後は途中で中断できないため、環境を整えてから受検しましょう。
Webテストでは問題ごとに制限時間が設けられており、時間切れになると自動的に次の問題へ進み、解き直しはできません。そのため、時間配分を意識して解答を進めることが大切です。
また、多くの形式で電卓の使用が認められているので、効率よく計算できるよう事前に慣れておくと安心です。
テストセンター
テストセンターは、全国に設置された専用会場でパソコンを使って受検する形式です。
受検者は専用サイトから日時と会場を予約し、当日は会場に設置されたPCで試験を行います。SPIやC-GABといった主要な検査に対応しており、大手企業を中心に広く導入されています。
テストセンターの大きな特徴は「結果を使い回せる点」です。これは同じ形式のテストに限り、過去に受けた結果を他企業にも提出できる仕組みです。
SPIテストセンターやC-GAB/C-GAB plusでは、一度受けた結果が約1年間保存され、複数の企業に送信できます。
保存されるのは常に直近の受検結果のみで、過去のスコアを選んで送信することはできないため、注意しましょう。
また、テストセンターでは電卓の持ち込みができないため、計算は暗算や筆算が前提となります。問題形式によってはタイピング解答もあり、スピードと正確さが求められます。
ペーパーテスト
ペーパーテストは、応募先の企業が用意した会場で紙と鉛筆を用いて受検する形式の適性検査です。
多くの場合はマークシート方式で行われますが、記述式問題が出題されることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
パソコンで受けるWebテストやテストセンターとは異なり、問題ごとに制限時間が設けられていません。
そのため、全体の問題数や出題内容を把握したうえで、時間をかけるべき問題と素早く解く問題を判断し、効率的に時間配分することができます。
また、解答の順番に制限がないため、確実に解ける問題から取り組み、難しい問題は後回しにするなど、自分のペースで進められる点がメリットです。
電卓の持ち込みはできないため、暗算や筆算に慣れておきましょう。事前に過去問や練習問題で紙に書く感覚を身につけておくと、本番でも落ち着いて取り組むことができます。
インハウスCBT
インハウスCBT(Computer-Based Testing)は、企業が自社で用意した会場のパソコンを使って受検する形式の適性検査です。インハウスCBTは他の形式と比較して導入企業が少なく、受検の機会は限られています。
Webテストと同様の問題形式が多いため、Webテストの対策を行うことが最も効果的です。特に、言語・非言語の基礎能力検査に関しては、問題演習を通じて解答スピードと正確性を高めることが求められます。
形式による注意点
適性検査は同じテストでも、受検する形式によって注意すべきポイントが変わります。
テストセンター方式や企業の会場で行うCBTでは、試験監督が常駐しており、本人確認や持ち込みルールが厳しくチェックされます。そのため、当日は身分証や受検案内を忘れないように準備しておきましょう。
一方で、自宅で受けられるWebテストは監督がいない代わりに、通信環境や静かな受検場所を整えるのが大切です。途中でネットが切れると再受検ができない場合もあるため、安定した環境を選ぶ必要があります。
また、形式によって受検可能な期間や開始時間の柔軟さも異なります。案内メールをよく確認し、余裕を持って準備することで、本番で安心して力を発揮できます。
適性検査の対策方法

【能力検査】出題形式ごとの問題に慣れておく
能力検査では、文章理解や計算、図形推理など、さまざまな分野の問題が出題されます。まずは、それぞれの問題形式に慣れることが大切です。
参考書や問題集で実際に手を動かして解くことで、出題パターンや解き方の流れが自然と身につきます。また、問題を解く際には「どの方法で解くのが効率的か」を意識して練習すると、本番で迷わず回答できるようになります。
適性検査とは、単に知識を問うだけでなく、考え方や処理能力を見るテストなので、形式に慣れることが得点アップの第一歩です。
【能力検査】時間配分を意識した練習を行う
能力検査は短時間で多くの問題を解く必要があり、時間配分が非常に重要です。最初はゆっくり解きながら問題の特徴をつかみ、その後、制限時間を意識して練習すると効率が上がります。
難しい問題に時間をかけすぎず、まずは解ける問題を確実に押さえることが得点のコツです。
また、模擬テストや過去問を時間を計って解くことで、試験全体のペース感を掴むことができます。こうした練習を重ねると、本番でも焦らず取り組めるようになります。
【能力検査】苦手分野の基礎を固める
苦手分野は全体の得点を下げやすく、避けて通るのは危険です。特に配点が高い問題も多いため、基本の公式や解き方を繰り返し確認し、少しずつ克服していくことが大切です。
就活生がつまずきやすいのは、非言語の計算問題・図形推理・長文読解のスピードです。
計算問題では分数や割合、速さといった中学レベルの内容が中心なので、四則演算や割合計算を毎日少しずつ練習すると効果的です。
図形問題に苦手意識がある人は、頭の中だけで考えず、実際に紙に書いて整理することで理解が進みます。長文読解は「設問ごとに本文のどこを読めばいいか」を意識すると、時間短縮につながります。
このように、苦手を放置せず基礎を固めるだけで得点は安定し、全体の底上げにつながります。直前に一気に克服するのは難しいため、できるだけ早めに取り組むのが成功のコツです。
【能力検査】模擬テストや過去問で総合的に練習する
能力検査の対策では、模擬テストや過去問を活用して本番さながらの練習を行うことが非常に効果的です。
実際の試験形式や制限時間に慣れておくことで、当日の緊張を和らげ、落ち着いて解答できる力を養えます。また、自分の得意・不得意分野を客観的に把握できる点も大きなメリットです。
模擬テストを選ぶ際は、出版社の信頼性はもちろん、最新年度の出題傾向に対応しているかどうかも重要です。加えて、解答・解説が充実しているかを確認することで、復習効率を高めることができます。
模擬テストや過去問を繰り返し解くことで「時間配分の感覚」や「解答の優先順位づけ」など、実戦に直結する力を磨けるため、必ず学習計画の中に組み込みましょう。
【性格検査】自己分析を活用して回答の一貫性を意識する
性格検査では、応募者の行動傾向や価値観をもとに、企業が人物像を判断します。
そのため、回答に一貫性があることが非常に重要です。一方で、何も準備せずに受けると、設問の表現によってつい矛盾した回答をしてしまい、評価が下がる可能性があります。
対策としては、まず自己分析を行い、自分の強み・弱みや行動の傾向を整理しておくことがポイントです。
自己分析を通じて「自分は計画的に物事を進めるタイプ」「チームワークを重視するタイプ」など、自分の特徴を言語化しておくと、設問に迷わず回答できます。
また、事前に回答パターンを理解しておくと、設問ごとの意図を把握しやすくなり、一貫した答え方が自然にできるようになります。
性格検査は正解のあるテストではないため、自己分析をベースに自分らしい回答を心がけることが、選考を有利に進めるコツです。
適性検査に関するよくある質問(FAQ)

SPIと適性検査の違いは?
SPIは企業の採用選考で広く使われる適性検査の一種で、能力検査と性格検査の両方を含む総合テストです。一方で「適性検査」とはSPIに限らず、企業が応募者の知識・能力・性格を評価するための幅広いテストの総称です。
つまり、SPIは適性検査の中の代表例にあたります。就活生にとって重要なのは、SPIもその他の適性検査も基本的な対策の流れは同じということです。
言語・非言語などの能力検査は問題形式に慣れること、性格検査は自己分析を通して一貫性のある回答を意識することがポイントです。
適性検査の結果は自分で見れる?
企業が実施する適性検査の結果は、基本的に受検者本人が直接閲覧できることはほとんどありません。結果は企業の採用判断に活用されるため、スコアや詳細な内容は非公開となる場合が多いです。
ただし、一部の模擬テストや自己診断型のWebテストでは、受検後にスコアや得点分布を確認できる場合があります。
就活生としては、結果が必ず確認できるわけではないことを前提に対策を行うことが重要です。結果を確認できる場合や、企業からフィードバックがもらえる場合には、それらを活用して次回の対策に生かしましょう。
このように、適性検査の結果の確認やフィードバックの有無は、企業やテストによって異なります。各企業の案内をしっかり確認し、適切な対策を講じることが大切です。
一度受けた適性検査の結果は他の企業でも使える?
基本的に、一度受けた適性検査の結果を他の企業で使い回すことはできません。
多くの企業では受検の回数や形式が個別に管理され、提出した結果はその企業専用として扱われます。そのため、複数社に応募する場合は、企業ごとに改めて受検する必要があります。
ただし、例外として、一部のテスト形式では同じ企業内や条件によって結果を活用できる場合があります。
どのテストでも使い回しができるわけではないため、就活生は「過去の結果がそのまま使える」と考えず、各企業の案内やテスト形式を確認したうえで受検計画を立てることが大切です。
適性検査の対策はいつから始めるべき?
適性検査の対策は、できるだけ早く始めることが成功のポイントです。
特に能力検査は出題形式や解き方に慣れることが重要で、遅くとも応募前の2〜3か月前には学習を始めるのがおすすめです。時間に余裕を持って取り組むことで、苦手分野の克服や時間配分の練習にも対応できます。
日々の習慣としては、短時間でも毎日問題演習を行い、計算や文章理解、図形問題などの基礎を確認することが効果的です。
また、模擬テストや過去問を定期的に解くことで、自分の得意・苦手を把握し、改善点を確認できます。これにより、本番でも焦らず正確に解答できる力が身につきます。
能力検査を中心に、早めに計画的に練習を積み重ねることが、適性検査での安定した得点につながります。
適性検査で落ちることはある?
適性検査で落ちることは十分にあり得ます。
能力検査で基準点に達しない場合や、性格検査で企業の求める人物像との一貫性が低いと判断された場合に、次の選考に進めず落ちることがあります。
特に人気企業では、応募者の数が多く、適性検査で足切りを行うケースも少なくありません。
目安として、主要なテストでは全体の70%以上の問題を正確に解けることが望ましいとされています。計算や文章理解、図形問題など、各分野の基礎をしっかり身につけておくことが重要です。
1問でも多く正解できるよう、高得点を目指してしっかり対策に取り組みましょう。落ちるリスクを減らすためにも、早めの準備が大切です。
適性検査を練習できるサイトや対策本はある?
適性検査の対策としては、まず基本的な問題に慣れることが大切です。そのため、Web上の無料練習サイトや対策本を活用するのがおすすめです。
能力検査の出題形式や問題のパターンを理解するには、単元ごとの練習問題が豊富なSPI対策サイトで練習するのが効果的です。
さらに、実際のテスト形式に近い環境で試せる無料のSPI模試を利用すれば、受検後にすぐ結果を確認でき、苦手分野を把握して重点的に練習することができます。
また最近では、スマホで手軽に利用できるSPI対策アプリも多くあるため、通学・通勤のスキマ時間を活用して継続的に練習可能です。市販の対策本と組み合わせることで、より理解を深めながら効率よく対策を進めることができます。
これらの練習サイトや対策本、アプリをうまく組み合わせて計画的に学習することで、能力検査の対応力を着実に高め、本番でも自信を持って取り組むことができます。
適性検査を正しく理解して対策に取り組もう!
適性検査は就活において、自分の能力や特性を示す重要なステップです。
SPIや玉手箱、TG-WEBなど複数の種類があり、テストごとに出題形式や内容が異なります。そのため、まずは自分が受検する適性検査の特徴を正しく理解することが成功への第一歩です。
その上で、模擬テストやWeb練習、対策本やアプリを活用し、問題パターンや苦手分野の克服に取り組むことで、自信を持って本番に臨めます。
適性検査とは何かを正しく理解し、計画的に準備を進めれば、高得点を目指すことも十分可能です。前向きに取り組み、自分の力を最大限発揮しましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen


















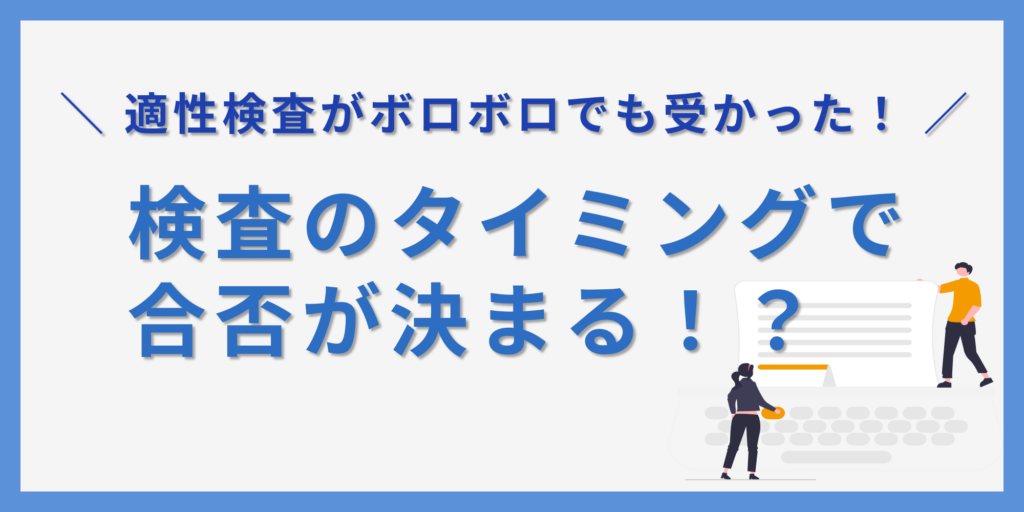 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?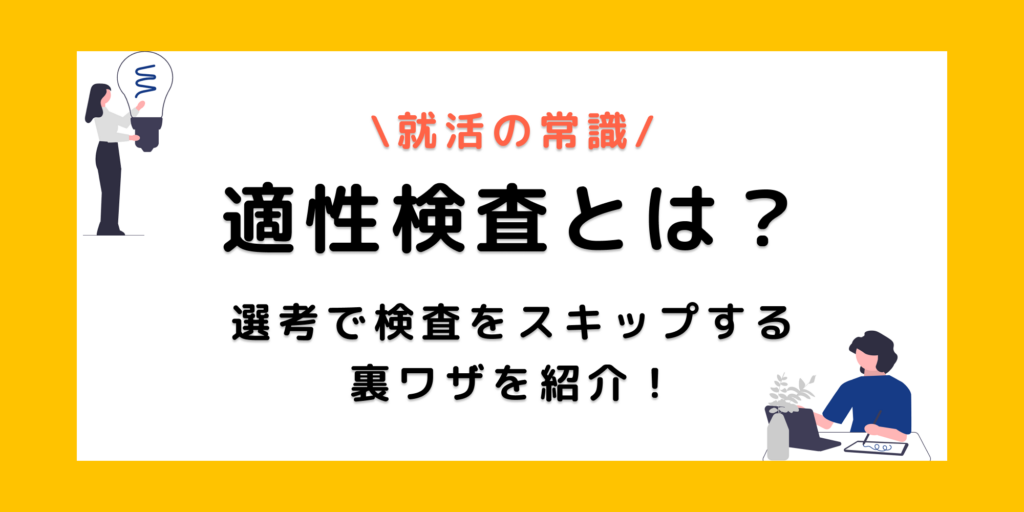 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!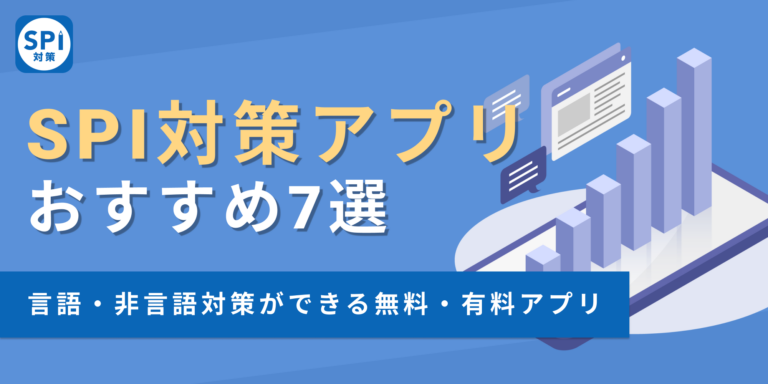 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ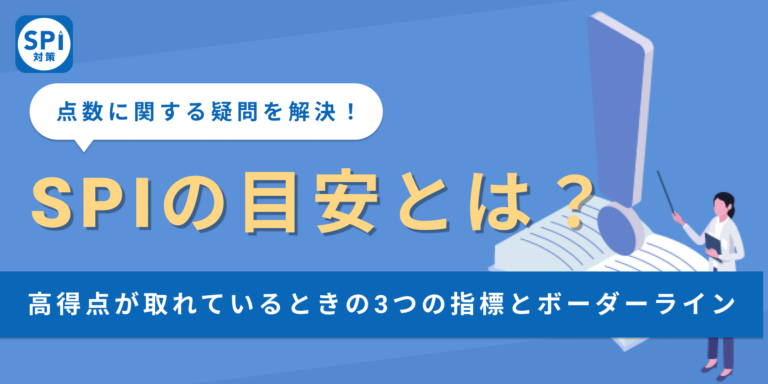 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点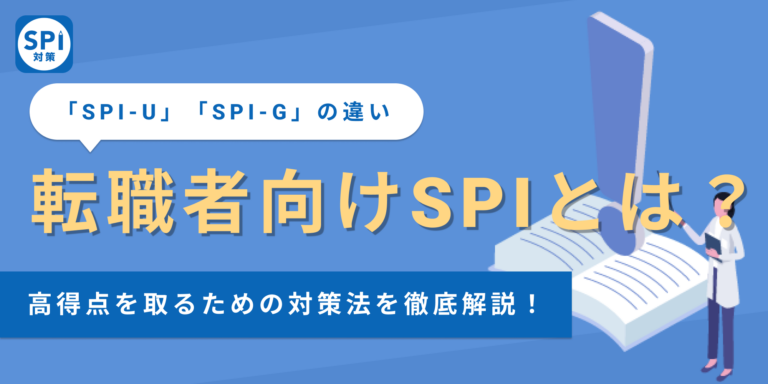 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説