
【適性検査とSPIの違い】SPIの種類の違いや受検形式について徹底解説! | SPI対策問題集
就活でよく耳にする「適性検査」と「SPI」は、どちらも同じだとだと思っていませんか?
適性検査とは、SPIを含む就活用のテスト全般を指す用語です。一方、SPIは最も多く実施される適性検査ではありますが、それ以外のテストが実施される可能性も十分にあります。
これら2つの違いを正しく理解した上で、適切な対策に取り組みましょう。
目次
適性検査とSPIの違いは?

そもそも「適性検査」とは?
「適性検査」とは、会社で働くにあたって必要なさまざまな能力を測るテストを指します。
テスト結果からは、受検者の企業との相性や職務の適性を知ることができます。
短時間の面接や履歴書から、応募者が持つポテンシャル、能力を判断して見極めるのは難しいため、より自社に合った人材を採用するためにも各企業は適性検査を実施するのです。
適性検査の結果は採用時だけではなく、入社後の人材配置や育成にも活かされます。
適性検査は学力や知的能力を測る「能力検査」と、受検者の人物像や特性を測る「性格検査」で構成されているのが一般的です。
適性検査には、SPI3、玉手箱、GAB、CAB、SCOA、TAP、TG-WEB、CUBIC、eF-1Gなど数多くの種類があります。
解答のスタイルや受検方式も適性検査の種類によってさまざまです。
問題に対して正しい答えを選んで解答するものや、自分で記述するもの、紙で解答するペーパーテストやパソコン上で解答するWebテストなどがあります。
「SPI」はどんなテスト?
「SPI」とは、リクルートマネジメントソリューションズが提供する適性検査です。
全国でもSPIを採用に取り入れている企業が多いことからその知名度は高く、適性検査と聞くとSPIを思い浮かべる人も少なくありません。
2021年12月期の実績では、受検者数は215万となっており、適性検査サービス導入者数において第1位になりました。
SPIは受検者の持つ能力や人となりを測定するテストです。
結果を活用することで、面接では見逃していた、企業で力を発揮してくれる人材を見つけだしたり、入社後はより活躍が見込める部署へ配置することができます。
数ある適性検査のうちの1つが「SPI」
適性検査もSPIも「受検者の能力やパーソナリティを測定するテストである」という点においては同じですが、適性検査はSPIや玉手箱、GABなど、たくさんの種類の適性検査を含んでいる言葉です。
一方のSPIはリクルートマネジメントソリューションズが提供する適性検査の名前です。つまりSPIは、数ある適性検査のうちの1つであるといえます。
採用選考を受けるなかで適性検査の実施がある場合、テストの種類はリクルートのSPIなのか、それとも他の会社が提供する適性検査なのかを必ず確認します。
適性検査の種類によって、問題の内容や対策法が異なります。
効率的に対策を行うためにも、適性検査の種類を確認してから対策に取り掛かりましょう。
適性検査として「SPI」を実施する理由
面接だけでは把握しきれない能力を知るため
面接だけで応募者を判断しようとする場合、履歴書からの情報と、採用担当者の感覚だけが頼りになります。
採用担当者が持つ過去の経験が大きな判断基準となってしまい、入社していれば大きな活躍をしていたかもしれない人材を取りこぼしてしまう可能性も大きいです。
SPIを実施することで採用担当者は、科学的かつ客観的な情報も手にすることができるので、SPIを実施しない時と比べ、効率的により良い人材を採用することができます。
企業と相性の良い人材を採用するため
企業にはそれぞれカラーがあり、社内でのコミュニケーションの取り方や社員の雰囲気にも違いがあります。
例えばチームワークや協調性を重んじる人が多い職場では、一方的なコミュニケーションを取りがちな人は浮いてしまいかねません。
しかし、SPIを取り入れることで、社内で活躍している人と似た特性をもつ人を採用できたり、会社の雰囲気に馴染みやすい人を採用することが可能です。
会社で活躍してくれる人が増えるというメリットを与えてくれたり、企業とのミスマッチから生まれる短期離職を防ぐことにもつながります。
入社後の人材配置・育成に活かすため
SPIは採用の場だけではなく、入社後の人員配置や人材育成の場においても活用することができます。
人はそれぞれ成果を発揮しやすい環境が異なります。
SPIで得た職務への適性やコミュニケーションの取り方、ストレスへの耐性などの結果を参考にすることで、最適な人員配置が叶います。
また将来の幹部候補など人を育てていく上でも、どのような人と環境のもとに社員を置くのが理想なのか、ということへのヒントがSPIの結果から得られるのです。
適性検査「SPI」の種類
- SPI3-U:新卒向けのSPI
- SPI3-G:中途採用・転職者向けのSPI
- SPI3-H:高卒者向けのSPI
- GSPI3:外国人向けのSPI
SPI3-U
SPI3-Uは大学4年生、いわゆる新卒採用向けのSPIです。就活生が適性検査でSPIを受検する際はこのSPIが用いられます。
新卒採用だけではなく他にも、正社員への登用、昇格、公務員試験などでSPI3-Uが使われることもあります。
SPIにまつわる対策本についても、基本的にはこのSPI3-Uを対象とするものが多いので対策しやすいのも特徴です。
SPI3-G
一般企業人、つまりすでに企業で働いている人が転職する際に中途採用試験で実施されることが多いSPIです。
中途採用だけではなく、正社員へ登用する際にも使われます。
問題の範囲などは他の種類のSPIと変わりはないものの、難易度に違いがあります。
特に「言語分野」は新卒向けのSPI3-Uよりも難易度が高くなっているので、油断禁物です。反意語や文章読解が難しくなっています。
また他の種類のSPIと違い、「資料解釈」の問題が出題されるのも特徴です。

SPI3-H
高校3年生、つまり高卒の受検者向けのSPIです。その他の種類のSPIと違い、難易度はそこまで高くありません。
出題内容や問題の形式は、新卒向けのSPI3-Uとそこまで変わりありません。
大卒向けのものと比べても問題は易しいので、これまで勉強してきたことをちゃんと復習していれば解くことができます。
中学〜高校前半レベルの問題が出題されるので、新卒向けや転職者向けの対策本が解けなくても焦る必要はないでしょう。
GSPI3
GSPI3は外国人向けのSPIです。検査内容は他の種類のSPIと同じく、能力検査や性格検査を行うことができます。
違いとしては、日本語だけではなく英語や中国語、韓国語で受検することができるという点です。受検者がしっかり問題を把握できるよう、適切な言語を選ぶことが可能です。
また、結果の比較対象は日本人なので、外国人同士ではなく日本人と比べた能力やパーソナリティを把握することができます。
SPIの受検形式
- Webテスト:自宅のパソコンで受検するテスト
- テストセンター:会場を予約して受検するテスト
- ペーパーテスト:企業が用意した会場で受検する、マークシート形式のテスト
- インハウスCBT:主に企業へ行き受検する、実施頻度の低いテスト
Webテスト
自宅のパソコンで受検するテスト形式です。
Webテストでは言語・非言語の能力検査と、性格検査を合わせて60分以上の時間がかかり、1問ごとに制限時間があります。
他の受検形式との大きな違いは、電卓の使用が可能であるということです。
電卓が使える前提の問題が出る可能性もあるので、Webテストを受ける場合は電卓に使い慣れておきましょう。
また、記述式の問題が多いため、明確な答えを自分で考える必要があります。
テストセンター
リクルートが提供する専用のテスト会場に出向いて受検する形式です。解答に使うのは紙ではなくパソコンです。
能力検査、性格検査の全てにかかる時間は約65分です。
他の受検形式との大きな違いは、テスト結果の使い回しが可能という点にあります。
過去1年以内にテストセンターで受検したことがある場合に、受検の予約画面から前回の試験結果を企業に送信できるようになっています。
テストセンターと同様にパソコンを使って受検する「Webテスト」の結果は使い回すことができないので、注意しましょう。
ペーパーテスト
ペーパーテストは文字通り、筆記試験のことです。企業が用意した会場でマークシートを使って紙で解答していきます。
Webテストをはじめ、パソコン上で答えを入力・選択していたのに対し、正しい答えを選んでマークシート上で解答します。
ペーパーテストの能力検査では、言語が30分で約40問、非言語は40分で約30問の問題を解いていきます。
能力検査の時間だけで70分と、他の受検方式の倍ほどの受検時間が設けられているため、高い集中力が必要になります。
インハウスCBT
実際に企業へ行き、用意されたパソコンを使って解答する形式です。面接と同時に実施されることもあります。
1日で選考の大部分を済ませられるため、就活生にとってはメリットも大きい形式となっています。
ただし、インハウスCBTを実施している企業は全体の1%程度なので、ほとんどが前述した3つの方法での受検となります。
SPIの検査内容
受検者のパーソナルに迫る「性格検査」
性格検査では、30分程度で約300問の質問に解答します。
与えられた質問に対して、「はい~いいえ」「当てはまる~当てはまらない」を4段階で選ぶ形式です。
日頃の行動や考え方を聞くことで、受検者のコミュニケーションスタイルや、困難な時にはどのように振る舞うタイプなのか、などの情報を企業は知ることができます。
性格検査では、自分を良く見せようと嘘の解答をすると、分析結果からバレてしまいます。素直に解答することを第一としましょう。
知的能力を測る「能力検査」
能力検査では、単に知識を持っているかどうかではなく、持っている知識をいかに活用、応用できるのかという知的能力が見られています。
SPIの能力検査では「言語分野」と「非言語分野」に大きく分かれており、言葉の意味や文章の理解力、論理的思考力、計算能力などから知的能力を測っていきます。
科目としてはいわゆる国語や数学の問題が出題されるのが能力検査です。
SPIでは「言語分野」と「非言語分野」の能力検査を「基礎能力検査」と呼んでいます。
企業によっては「オプション検査」が出題される
SPIでは「基礎能力検査(言語・非言語)」に加えて、「英語能力検査」と「構造的把握力検査」も実施される場合があります。
「英語能力検査」は基礎的な英語力を測定する検査で、主に語彙力や文法力・読解力を問われる内容になっています。
問題は20分間で約30問が出題されます。
一方、「構造把握力検査」とは、ものごとの構造を把握する力を測る検査です。
公式を使って問題を解いていくのではなく、与えられた情報から共通点を探したり、分類・整理したりできる力が必要になります。
これらの2つはオプション検査であり、企業が指定した場合のみ実施されます。
選考を受ける企業が過去に実施しているかを事前に調べておきましょう。
SPIを受検するときのポイント
対策アプリで問題を一通り解いてみる
SPIは採用数の多い適性検査のため、対策アプリも豊富に配信されています。
中でも、SPI対策アプリは幅広い範囲に対応した問題を無料で解くことができる、おすすめのアプリです。
本番に近い感覚で使える手書きメモや、成績の確認などの便利機能も搭載されています。
アプリを使って問題を一通り確認することで、自分の得意分野と苦手分野がはっきりとわかるでしょう。
その後、分野ごとの対策の進め方を決めることで、明確な目標設定もできるようになります。
制限時間に慣れておく
SPIではいずれの受検形式でも制限時間が設けられています。
1問にかけられる時間が短いので、スピーディーかつ正確に問題を解いていかなくてはなりません。
さらに、パソコンで受検する際には、画面上で1問ごとに制限時間が表示されるので、問題を解きながらも視覚的に時間に追われる感覚になります。
時間を意識しなければすぐに解けていた問題も、焦りから思うように解けなくなるということも起こり得ます。
事前の対策では、時間を測りながら解くなどを繰り返し、時間に追われる緊張感に慣れておくことも大切です。
形式ごとの出題範囲だけを練習する
前述した通り、SPIでは4つの受検方式があります。
テストの形式によって問題の出題内容にも違いがあるので、自分が受検する方式にあった対策本を使って対策していきましょう。
ペーパーテストを受検する人がWebテスト用の対策本で対策していた場合、「勉強していた問題と違う問題ばかり出て解けなかった」という事態にもなりかねません。
受検の形式と対策本が合っているかしっかり確認しましょう。
性格検査は正直に解答する
性格検査で自分を偽ると、結果に矛盾が生じ、「よく見せようとしてる」と企業側に見抜かれてしまう可能性があります。
SPIの性格検査では、受検者の意図的な解答を見抜くような問題の仕組みになっているので、嘘をついてもあまり意味がないといえるでしょう。
また仮に嘘をついて選考に通ったとしても、本来の自分にマッチしていないため、苦手な職種に就いてしまったり、社風に合わず疲れてしまうかもしれません。
性格検査で取り繕った場合、いずれにせよ好ましくない結果が待っている可能性が高いので、最初から正直に率直に答えていきましょう。
模擬試験を受ける
SPI対策を進める中で、「これで実際に通用するの?」と不安になることも多いです。
そんな時は、Web上で受けられる模擬試験に挑戦してみましょう。
SPI対策模試では、簡単な実力診断と本番想定の本格的な模試を選んで受けることができます。
どちらも無料のサービスであり、負担になりません。いつでも好きな時に受けられるので、数十分の隙間時間で実力を試すことが可能です。
また、仮に模擬試験で良い結果を出せなくても気にする必要はありません。問題形式に慣れておき、本番で緊張しないようにできれば十分な成果といえます。
SPIは適性検査の一種!的確な対策をしよう
SPIと適性検査は同一視されがちですが、SPIは「数ある適性検査の1つ」に過ぎません。
こうした違いを知らずに漠然と対策をしても、良い結果には繋がりません。
志望企業の実施する適性検査の種類を調べて、それに合ったピンポイントな対策をすると効率的です。
就活ではSPI以外にも様々な選考プロセスの対策が必要です。偏った対策にならないよう、要点を押さえて対策を進めましょう。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen

















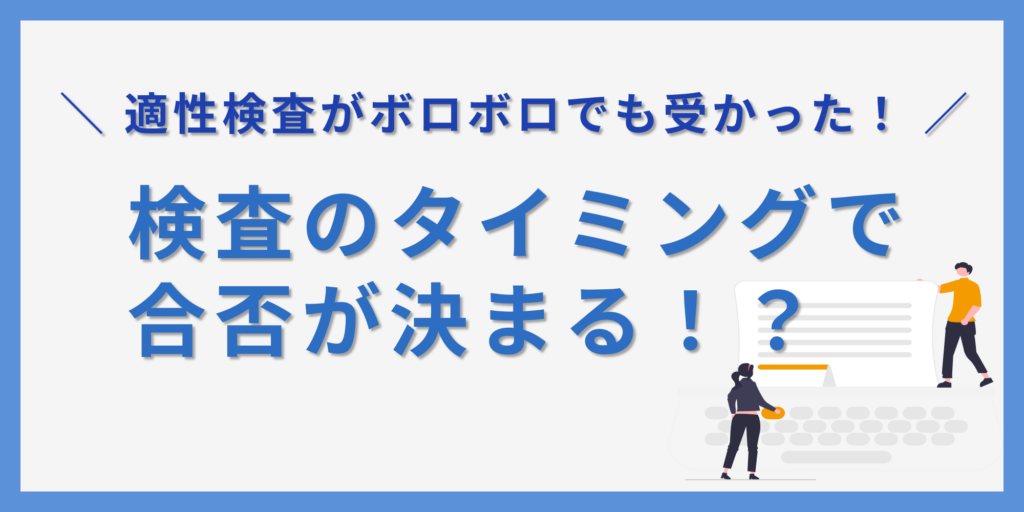 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?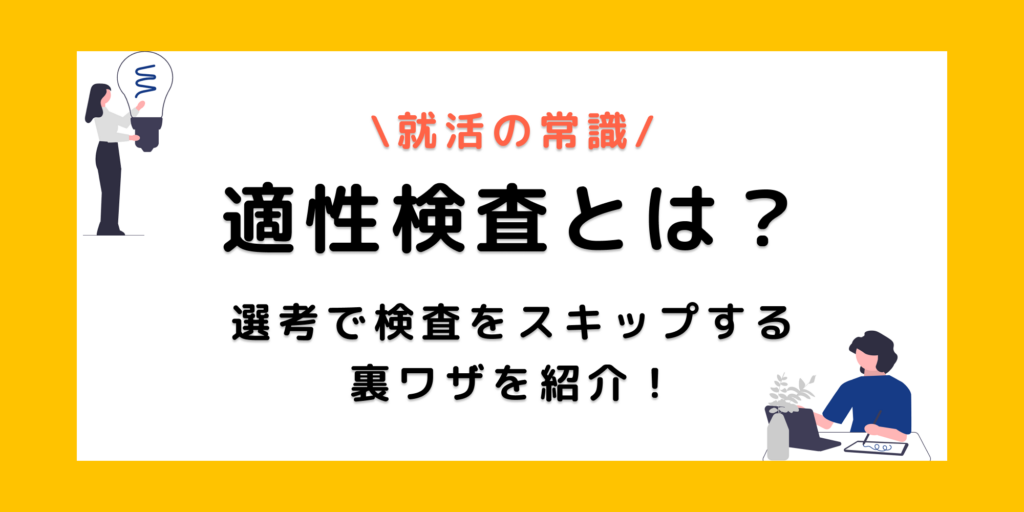 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!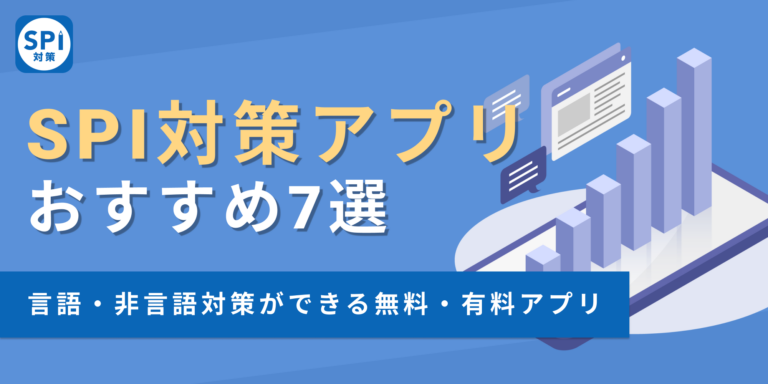 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ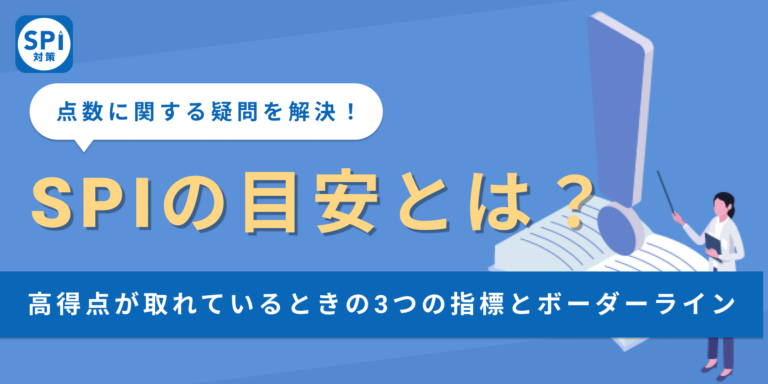 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点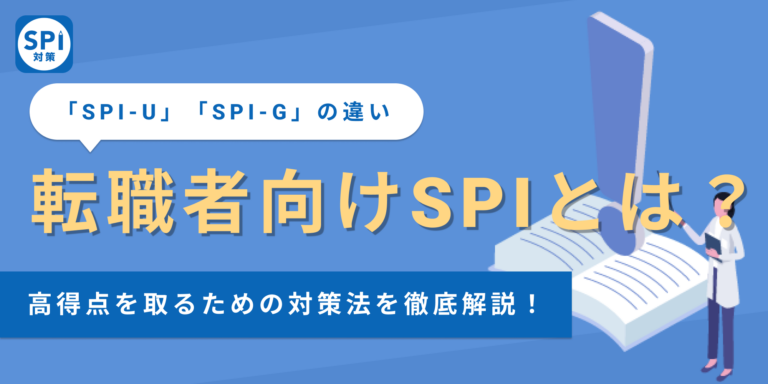 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説