
SPIの問題数を一覧で紹介!数をこなせる練習方法はどれ? | SPI対策問題集
SPIは、多くの企業で採用されている適性検査で、限られた時間内に多くの問題を正確に解くことが求められます。
しかし、受検形式によって問題数が異なるため、具体的な対策方法がわかりにくいと感じる人も少なくありません。
この記事では、SPIの主要な4つの受検形式ごとの問題数と時間の目安を一覧表でわかりやすく紹介します。
また、問題数を効率よくこなすための具体的な練習方法も解説しているため、SPI対策を始めたい方、得点力を上げたい方はぜひ参考にしてください。
目次
【形式別】SPIの問題数一覧
| ペーパーテスト | テストセンター | Webテスト | インハウスCBT | |
| 言語 | 約40問/約30分 | 解答状況によって変化/あわせて約35分 | 言語 約40問
非言語 約20問/あわせて約35分 |
言語 約40問
非言語 約20問 /あわせて約35分 |
| 非言語 | 約30問/約40分 | |||
| 構造把握 | 出題なし | 約20問/約20分 | 出題なし | 出題なし |
| 英語 | 約45問/約30分 | 解答状況によって変化/約20分 | 出題なし | 出題なし |
SPIには複数の受検形式が存在し、それぞれ出題される問題数や時間配分、出題形式に違いがあります。
事前に自分がどの形式で受けるかを把握していないと、試験当日に戸惑ったり、時間が足りなくなったりするリスクがあります。そのため、対策の第一歩として形式ごとの特徴を理解しておくことが重要です。
ここでは、SPIの代表的な4つの受検形式「テストセンター」「Webテスティング」「ペーパーテスト」「インハウスCBT」について、それぞれの出題科目・問題数・試験時間の目安とともに詳しく解説します。
ペーパーテスト
ペーパーテストは、企業が会場で紙と鉛筆を使って実施する形式です。
問題数は言語40問、非言語30問と比較的多めになっています。記入はマークシートが中心で、見直しも可能です。
時間は合計で約70〜90分が一般的で、性格検査もあわせて実施される場合があります。テスト全体の構成が明確なため、事前に問題集で十分に対策しやすいのが特徴です。
テストセンター
テストセンター形式は、全国に設置された専用会場でパソコンを使って受検します。
この形式はCAT(コンピュータ適応型)方式を採用しており、受検者の正答状況によって出題の難易度や問題数が変動するのが特徴です。
前の問題に戻ることはできず、残りの問題数も表示されないため、時間配分とテンポの良さが特に求められる形式です。
Webテスト
Webテストは、自宅など受検環境を整えられる場所からパソコンで受けるオンライン受検形式です。
問題の難易度の変化もなく、企業ごとのカスタマイズも少ないため、最も予測しやすく対策が立てやすいのが特徴です。
自宅で落ち着いて受けられる一方で、通信環境や操作ミスには注意が必要です。模擬テストやオンライン対策アプリであらかじめ操作に慣れておくようにしましょう。
インハウスCBT
インハウスCBTは、企業が設定した会場でパソコンを用いて実施する形式です。出題内容や形式は企業によって若干異なります。
ただしCAT方式ではないため、問題の難易度や数は基本的に固定されます。企業独自のカスタマイズが加えられているケースもあるため、事前に案内メールや練習問題などが配布された場合は、内容をよく確認することが重要です。
SPIの問題を制限時間内に解くコツ

制限時間を体感で覚える
SPIは時間との勝負です。頻繁に時計を確認すると、それだけでタイムロスになります。そのため、日頃の練習から1問あたりの制限時間を意識し、タイマーを使って解く習慣をつけましょう。
例えば、非言語問題なら1問1分を目安に設定し、自然と時間感覚を身につけるのが理想です。
対策を始めたばかりの段階では時間を測らずにゆっくり解く練習でも良いですが、本番形式に近づけるには時間内で解ききる感覚を養うことが非常に重要です。
暗記問題は捨てる判断も大切
語彙や熟語の意味、あまり使わない数学の公式など、解くのに知識が必要な暗記系の問題は、考えても答えにたどり着けないことがあります。
そのような問題に無理に時間をかけるより、すぐに飛ばして次の問題に進む方が得策です。
特にSPIはスピード重視の試験なので、迷ったり、わからないと感じた時点で即決する判断力が大切です。
解ける問題に時間を確保することで、全体の得点効率を高めることができます。
問題によって時間配分を変える
すべての問題に同じだけ時間をかけるのではなく、どの問題に時間をかけるかの見極めが重要です。
苦手な分野やわからない問題ばかりに時間をかけてしまうと、自分が得意な問題や解ける問題を解く時間もなくなってしまいます。
常に「この問題に何秒かける価値があるか」を意識して、限られた時間を最大限有効に使うようにしましょう。
この科目が出題されたら1問何秒あたりで進めるかなどをあらかじめ決めておくことでテンポよく解答を進めることができます。
解答は考え直さない
一度解いた問題を見直したくなる気持ちはわかりますが、SPIではその時間が大きなロスに繋がります。特に制限時間が短い形式では、見直す余裕がほとんどありません。
そのため、1問1問をもう解き直さないことが大事です。迷いながら出した答えをまた変えることで、逆にミスを増やすリスクもあります。
練習の段階から見直しはしない前提で練習を重ねると、本番での判断も早くなります。
SPIの問題数についての注意点

1問にこだわりすぎるのは危険
SPIでは、1問に時間をかけすぎると全体の得点力が大きく下がります。
難しい問題にこだわって時間を費やしてしまうと、後半の簡単な問題にたどり着けず、大きな失点につながるリスクがあります。
「この問題にこれ以上時間をかけても見合わない」と感じたら、すぐに見切りをつけて次に進む判断力が非常に重要です。
テンポよく解き進め、取れる問題を確実に取る姿勢が、高スコア獲得の鍵となります。
解答した問題には戻れない
SPIでは、一度解答した問題に戻って見直すことができない形式が一般的です。特にテストセンターやWebテストでは「戻る」ボタンがなく、過去の問題を修正することは不可能です。
そのため、各問題はその場で確実に判断する必要があります。迷いすぎたり、「あとで見直そう」と思ってもできないので、悩んだ時点で最も可能性が高い答えを選び、次に進むのが正解です。
逆に、考えすぎて解答を出せずに時間を浪費してしまうと、その後の問題に十分な時間を割けず、得点が伸びにくくなります。
解答は一発勝負だという意識を持つことが、攻略のポイントです。
テストセンターは残りの問題数がわからない
テストセンター方式のSPIでは、現在の進行状況や残りの問題数が表示されない仕様となっています。
そのため、受験者は常に「あと何問あるのか」が分からないまま進める必要があります。
この仕組みの影響で、ペース配分が非常に難しくなります。前半の問題に時間をかけすぎてしまうと、後半にまだ多数の問題が残っていた場合に間に合わなくなる可能性があります。
時間配分を自分の感覚で管理しなければならないため、日頃の練習からタイマーを使い、時間感覚を養うことが非常に重要です。
全体を通して安定したテンポで解き進める意識が求められます。
SPIの問題をたくさん解ける練習ツール
無料の対策アプリ
SPI対策アプリでは、多くの問題を全て無料で解くことができます。
隙間時間で手軽に練習ができる上、本番に近い解き方もできる手書きメモなどの便利機能も搭載しています。
また、復習用の機能も充実しており、間違えた問題を中心にランダム出題されるモードなどを利用可能です。
色んなツールが試せる練習問題サイト
SPI対策問題集のサイトでは、SPIの様々なツールを試すことができます。
サイト内に入れ込まれている問題集はもちろん、現在の実力レベルも診断できるSPI対策模試やSPIの模試、頻出語句集、解答テクニック集が一つに凝縮されたSPI最短突破3選パックなどがあります。
SPI対策模試で自分の実力を試し、SPI最短突破3選パックで効率の勉強方法を学び、SPI対策問題集で演習を重ねるというサイクルで活用することができます。
問題集で反復練習する

出典:Amazon
まとまった時間でじっくり取り組みたいなら、就活生に人気のこれが本当のSPI3だ! 2028年度版の問題集がおすすめです。
頻出問題や典型的なパターンが網羅されているため、解答力を底上げしやすくなっています。
頻出問題や典型的なパターンが網羅されており、基礎から応用まで効率よく解答力を伸ばせます。
タイマーを使って時間を計りながら解くことで、本番さながらの時間配分にも慣れることができます。
解説も丁寧で自己採点がしやすく、自分の弱点を明確にしながら次の学習に活かせるのが特徴です。
SPIの問題数に関するQ&A
何問正解すれば合格できる?
SPIには明確な合格点はありません。企業ごとに合否の判断基準が異なり、正答率や得点のバランス、志望職種によっても変わります。
一般的に、正答率6割〜7割以上が目安とされ、難関企業では8割以上が求められる場合もあります。
大切なのは、苦手分野を放置せず、どの科目でも安定して得点できる力をつけることです。
1問1問を確実に解きつつ、全体として高い正答率を維持することが、合格ラインを超えるカギとなります。
全部解答できないと落ちる?
全部解答できなかったからといって必ず落ちるわけではありません。しかし、解けた問題数が多い方が正答率が上がる可能性は高いため、解答数が多いことに越したことはないです。
SPIは時間制限が厳しく、全問を解ききれないことはよくあります。そのため、すべての問題に手をつけることよりも、「取れる問題を確実に取り、時間をかけすぎない」ことが大切です。
わからない問題を飛ばして次に進む判断力も重要なスキルの一つです。
特にテストセンター形式では、解答済みの問題に戻れないため、テンポ良く進めることが合格への近道になります。
問題数を事前に判別するには?
問題数そのものは公表されていませんが、案内メールに記載された受検形式からある程度予測することが可能です。
ペーパーテストでは、言語・非言語をあわせて70問が出題されます。
正答率によって問題数や難易度が動的に変化する、テストセンターとWebテストでは、正確な問題数は提示されていませんが、言語/約40問、非言語/20〜30問が目安とされています。
また、インハウスCTBでは、企業によって問題数は異なるものの、言語・非言語合わせて60問程度と言われています。
受検前にあらかじめ形式を確認し、それに応じた対策や時間配分の戦略を練ることが重要です。
SPIの問題数を理解して時間切れを防ごう
SPIでは、時間切れによって本来解けるはずの問題を落としてしまうケースが非常に多く見られます。その原因の一つが問題数や形式を事前に把握していないことです。
SPIは受検形式によって問題数や出題ペースが異なり、特にテストセンターでは残りの問題数が表示されないため、ペース配分が非常に難しくなります。
しかし、受検案内メールに記載された形式から、ある程度の出題傾向や問題数は予測可能です。
事前に形式を調べ、自分の解答スピードと照らし合わせておくことで、時間切れを防ぎ、安定して得点できるようになります。
SPIは問題を解くスピードと正確さのバランスが合格の鍵です。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen












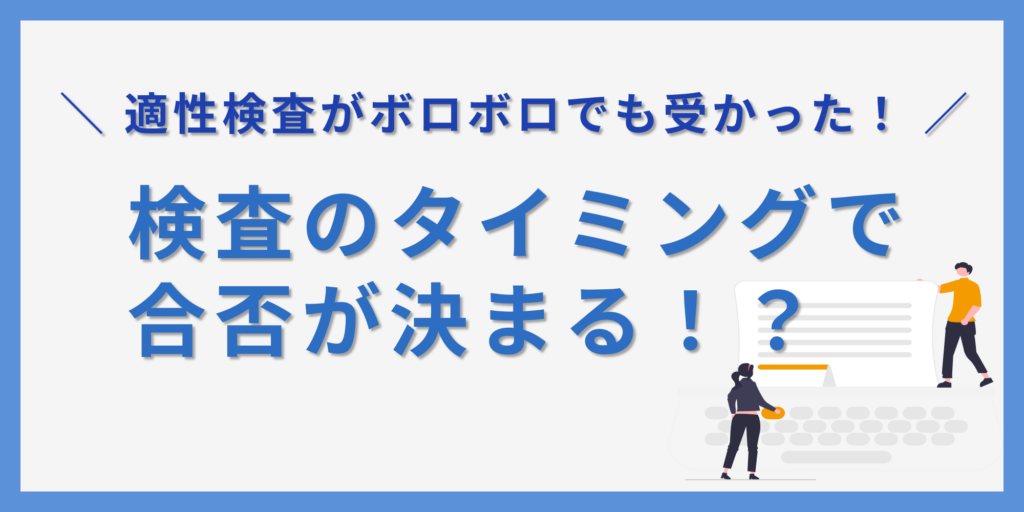 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?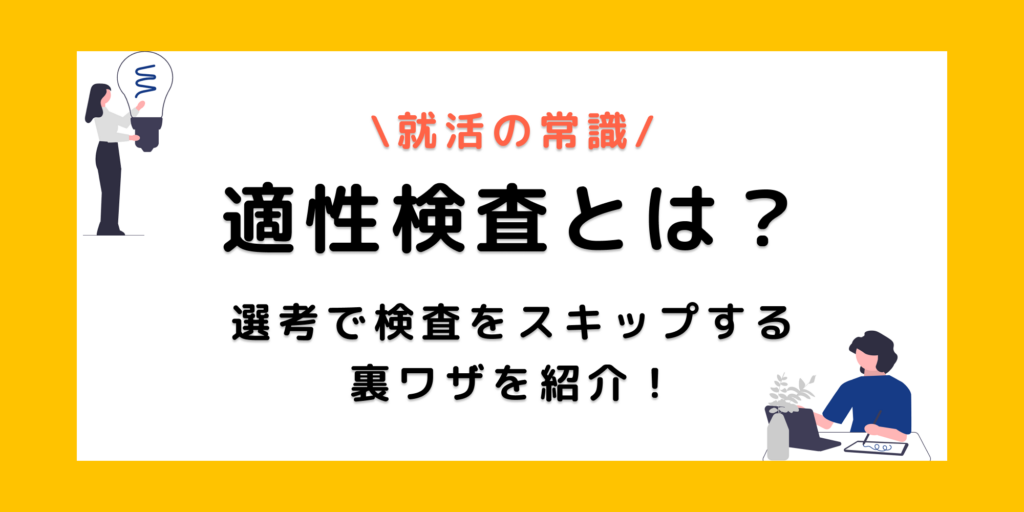 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!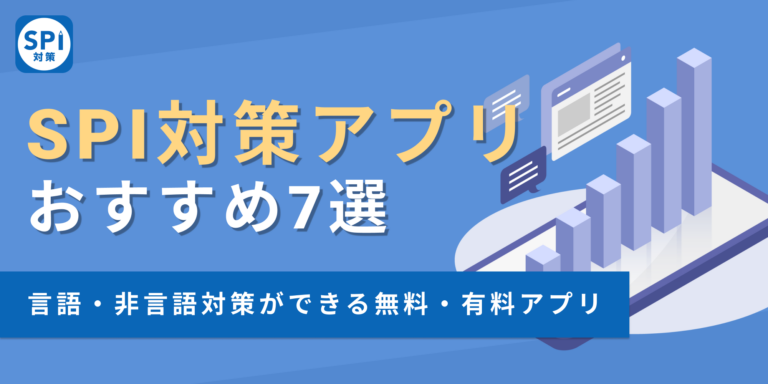 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ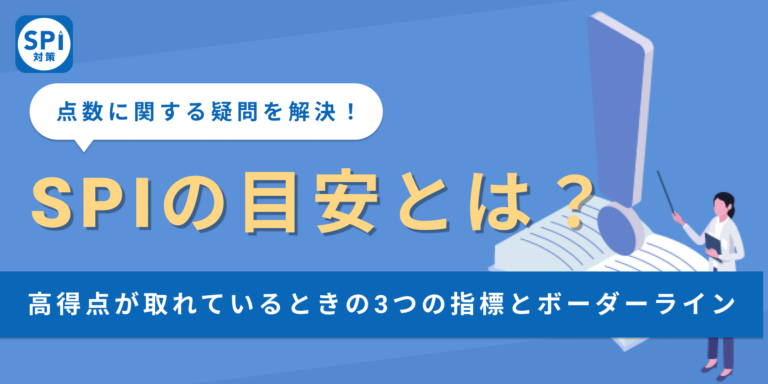 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点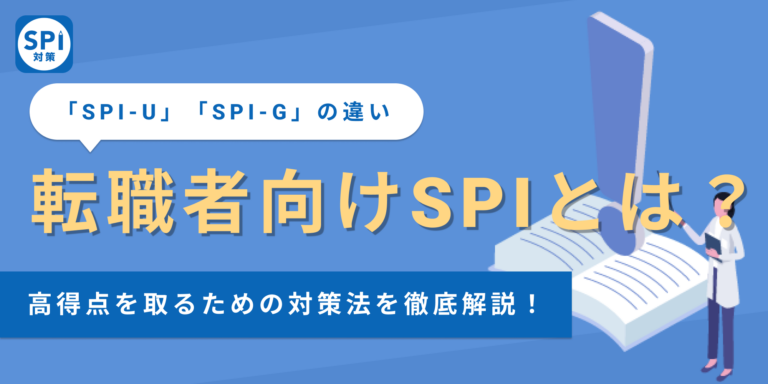 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説