
【SPI】難易度が変わるウワサって本当?知っておくべき適応型テストの正体 | SPI対策問題集
SPIを受検した就活生の間でよく話題になるのが「SPIは難易度が変わるらしい」というウワサです。
実はこれは一部本当で、SPIの受検形式によっては問題の難易度が途中で変化する仕組みが採用されています。
特にテストセンター形式やインハウスCBT形式では、受検者の解答状況に応じて出題レベルが調整されるのです。
本記事では、SPIで難易度が変わる仕組みの正体とその理由をわかりやすく解説します。
また、難しい問題に直面したときの具体的な対策法も紹介するので、これからSPIに挑む方はぜひ参考にしてください。
目次
SPIは一部形式で問題の難易度が変わる!

SPIは受検形式によって細かい出題方法に違いがあります。「問題の難易度が変わる」というウワサは、一部の形式においては本当のことです。
一方、最初から出題内容が決まっており、途中で難易度が変化しない形式もあります。難易度が変わるかどうかで評価方法も異なっているため、それぞれの違いを確認しておきましょう。
テストセンターとインハウスCBTは変化あり
全国にある会場で受ける「テストセンター」と、企業に行って受ける「インハウスCBT」では、解答状況によって問題の数や難易度が変化します。
この2つは「適応型テスト」と呼ばれ、受験者の能力に合わせた問題が出題されるのが特徴です。
例えば、前半の問題で正答率が悪かった場合、後半は難易度が低めの問題が出題されやすくなります。逆に、高い正答率を維持していると、難しい問題が続きやすいです。
このシステムから、一見すると「正答率が高いと不利になるのでは?」と思うかもしれません。しかし、これらの形式では問題の難易度も評価基準に含まれています。正答数が同じでも、難しい問題を解いていた人の方がより高い評価を得られるのです。
Webテストとペーパーテストは変化なし
自宅で受ける「Webテスト」と、マークシート方式の「ペーパーテスト」は、あらかじめ決められた内容で出題されます。Webテストはテストセンターと似た形式ですが、問題数や難易度が変わることはありません。
これらの形式は受検者ごとに内容の違いが出ないため、単純な正答数で成績に差が付きます。一方、難易度が変わらないことで「どれだけ正答できているか」の目安がなく、得点が判断しにくいという特徴もあります。
基本的な難易度はテストセンターやインハウスCBTと共通であり、どちらの方が難しいという傾向はありません。出題範囲にだけ注意しながら対策を進めれば、どの形式にも対応できます。
難易度の変化はどうやってわかるの?
チェックボックスが登場する
【例題】
18個のボールをP、Q、R、Sの4人に配った。これについて次のことが分かっている。
Ⅰ PとRがもらった個数の平均は、QとSがもらった個数の平均と等しい。
Ⅱ Pがもらった個数は4人の中で最も多い。
Ⅲ 4人がもらった個数は全て異なる。
このとき、必ず正しいといえる推論の組み合わせはどれか。当てはまるものを全て選べ。
<選択肢>
ア. Qがもらった個数はSがもらった個数よりも多い。
イ. QかSのうちどちらかは、4人がもらった個数の平均よりも少ない。
ウ. Rがもらった個数は4人の中で最も少ない。
正解:
イとウ
チェックボックスは、選択肢を複数選べる形式の問題です。部分点はなく、完全解答でなければ得点になりません。通常の問題よりも難しいため、難易度が変わったことの指標とすることができます。
チェックボックスは、非言語の推論や言語の長文読解で出る可能性があります。「あてはまるものを全て選ぶ」ことを指定されますが、必ず2つ以上選ぶわけではありません。
問題によっては、正解の選択肢が1つだけということもあるでしょう。複数選択という形式を勘違いしないように注意が必要です。
抜き出し問題が出題される

抜き出しは言語で出題される可能性がある形式です。長文から語句を抜き出して答える内容となっています。
抜き出す語句には「〇文字」「〇文字以下」などの指定があり、選べる幅が広くなるほど難しい問題だと判断できます。最も難しいのは「文字数指定なし」というケースです。
具体的な語句を探す必要があり、長文読解の「それらしい要点だけを拾う」といったテクニックが通じません。時間はかかりますが、その分だけ高い評価に繋がりやすい問題でもあるので、じっくり取り組むことがおすすめです。
長文が2問以上出題される

言語・英語では、長文読解の出題数で難易度を測ることができます。基本的に1問は出題されますが、それ以上出題されるかどうかは正答率によって左右されます。
長文読解は他の問題よりも時間がかかりやすいため、難易度が高めです。多めに出題された長文読解にも正解することができれば、高い評価を残せます。
なお、英語では言語よりも長文読解がやや多めに出る傾向があります。より高い得点を目指すのであれば、英語は「長文3個以上」を目安にすると良いでしょう。
非言語の問題が4タブで始まる

非言語では、1つの問題に対して複数の小問が出題されることがあります。この場合、各小問は問題文の下のタブをクリックすることで切り替えることになりますが、このタブの数も難易度の指標です。
タブの数が多ければそれだけ難しくなり、最大の4タブで最も難易度が高くなります。ただし、計算や考え方というよりは、時間配分の面での難しさの方が感じやすいでしょう。
テストセンターとインハウスCBTでは1問ごとに制限時間が設けられています。しかし、複数タブの問題では「全てのタブを含めて1つの問題」として時間が設定されているため、感覚で時間を割り振る必要があります。
時計の針がどのような形で止まっているか

全ての解答を終えた後、残り時間がどう表示されていたかで、どれだけの難易度だったか推測することができます。
残り時間は円形のマークで表示されますが、厳密には経過時間を表しているのは外側の円だけです。内側の円は残りの問題数を示すもので、これら2つのバランスが難易度のヒントとなります。
テストセンターとインハウスCBTでは、明確な制限時間が決まっていません。問題の進捗によっては急に終了することもあります。
検査が終わった時に、「残り時間は余らず、残りの問題が余っている」という状態が理想的とされています。逆に、「残り時間が余り、残りの問題がなくなった」場合、簡単な問題が多かった可能性が高いでしょう。
難易度の変化に対応するための対策方法
対策本で基礎力を徹底的に固める
単元ごとに基礎を固めておけば、難易度の変化にも対応しやすくなります。対策本は徹底した勉強に向いており、やればやるほど伸びやすい方法です。
問題の難易度が上がっても、基本的な解き方に変化はありません。多少考えることが増える程度で、求められる知識は同じです。通常の長文読解や推論を迷いなく解けるようになっていれば、形式が難しくなっても迷わず対応できます。
また、途中までの正答率が高くなければ、そもそも難しい問題に挑むことができなくなってしまいます。難易度が上がったりしない問題についても、十分な正答率を出せるようにしておきましょう。
時間配分とスピード対策をする
難易度が上がれば、解答時間が伸びるのは自然なことです。しかし、1問あたりの制限時間が伸びるわけではないため、難易度にかかわらず一定の時間配分を維持する必要があります。
本番では残り時間が表示されますが、いちいち気にしていると不注意によるミスの原因になるでしょう。そのため、練習段階から時間を計りながら問題を解くようにして、感覚的に時間配分ができるようにしておくと安心です。
また、模擬試験を活用することで、より本番に近い時間配分を体感することが可能です。無料で挑戦できるSPIレベル診断で、今の実力を試しながら理想的な時間配分を掴みましょう。
難問に慣れておく

出典:Amazon
難易度の高いチェックボックスや4タブといった形式に、「難しいらしい」という知識だけで臨むと失敗しやすいです。せっかく難しい問題が出ても、正解できなければ勿体ない結果になってしまいます。
そのため、通常の形式に加えて、難しい形式の問題も練習しておきましょう。簡易的な対策本ではなく、本格的な勉強用の問題集などを使えば、経験が積みやすいです。収録されている問題数も参考にしつつ、自分に合った問題集を選びましょう。
それでも練習できる数は少なめなので、万全に仕上げることは難しいかもしれません。しかし、形式に慣れておくだけでも、本番での焦りを大きく減らすことに繋がります。
出題傾向を常にチェック
SPIは受検形式によって出題範囲が変わる適性検査です。問題の難易度が変化するテストセンターとインハウスCBTも、それぞれ出題範囲は異なります。
また、同じ形式でも毎年少しずつ出題傾向は変化しています。最新の対策本や、就活サイトで受検者の体験談などを確認することをおすすめします。
就活中にSPIの問題を全て仕上げるというのは現実的ではありません。少しでも効率的に対策を済ませるのであれば、志望企業が実施する受検形式に合わせて勉強すると良いでしょう。
SPIの難易度の変化に関するQ&A
難易度が変わるのに結果の使い回しって可能なの?
SPIのテストセンターを受けた結果は、他の企業でテストセンター受検を求められた時に使い回して提出することが可能です。
「毎回難易度が変わるのに使い回していいの?」と思うかもしれません。しかし、テストセンターの結果は単純な得点ではなく「解いた問題の難易度も含めた評価」として計測されます。実力が良く反映されるため、正確な能力を判断しやすいのです。
ただし、結果の使い回しができるのはテストセンターを受検する時だけです。例えば、同じく難易度が変わるインハウスCBTでは、結果は使い回せません。
また、テストセンターの結果を、他の形式の結果として提出することもできません。あくまでテストセンターに行く回数を減らせる制度であるという点に注意しましょう。
難易度が一定のWebテストが使い回し不可なのはなぜ?
Webテストの結果が使い回せない理由は、公式には発表されていません。しかし、受検形式から2つの理由が考えられます。
1つは、不正防止が困難であるということです。Webテスト形式は自宅で受検し、さらにカメラやマイクによる監視が行われません。仮に、複数人で解答していたとしても、不正として検知することができないのです。
そのため、厳正な結果として用いるには信頼性に欠け、一般的な選考でもそれほど重要な扱いはされにくい傾向にあります。
もう1つは、そもそも低コストで実施できる適性検査であり、精密な結果を出せないという点です。
Webテストは主に大量採用を行う人気企業で用いられやすい形式であり、足切りとしての用途が多くなっています。基準以上のスコアが出せれば通過となるので、厳密な評価が下されません。
こうした理由から、SPIのWebテストは使い回しができないようになっているのでしょう。
難易度が上がることによる受検者側のメリットは?
問題の難易度が上がることで、最終的に良い評価を得られる可能性が高くなります。
難しい問題が出た時に誤答してしまうと、簡単な問題を多く正答するよりも評価が低いように思えるかもしれません。しかし、「難しい問題が出た」という時点で既に高い正答率を出せていることが期待できます。
難しい問題が一切出ないまま、簡単な問題だけを解いていった人は、思っていたよりも正解できていない可能性が高いです。一方、「難しい問題ばかりで上手くできなかった」と感じる人は、意外と高いスコアが出ていることもあります。
難しい問題は、解いている時にはデメリットに感じても、最後には良い評価に繋がりやすいという点がメリットです。
難易度が難しくなったらプラスに捉えよう!
SPIのテストセンターやインハウスCBTで難易度の高い問題が出題されることは、悪いことではありません。むしろ、自分の正答率の高さの表れとして、プラスに捉えるべきです。
人気企業の選考で高いスコアを狙うのであれば、難しい問題は出てきて当たり前といえます。その上でしっかり正解できるように、本格的な対策本で練習しておくと良いでしょう。
難易度の差は、考えることよりも制限時間に強く表れます。単に問題を解けるだけでなく、「制限時間内に解ける」というレベルを目指して対策することが大切です。
 編集者Yuka
編集者Yuka 監修者gen
監修者gen












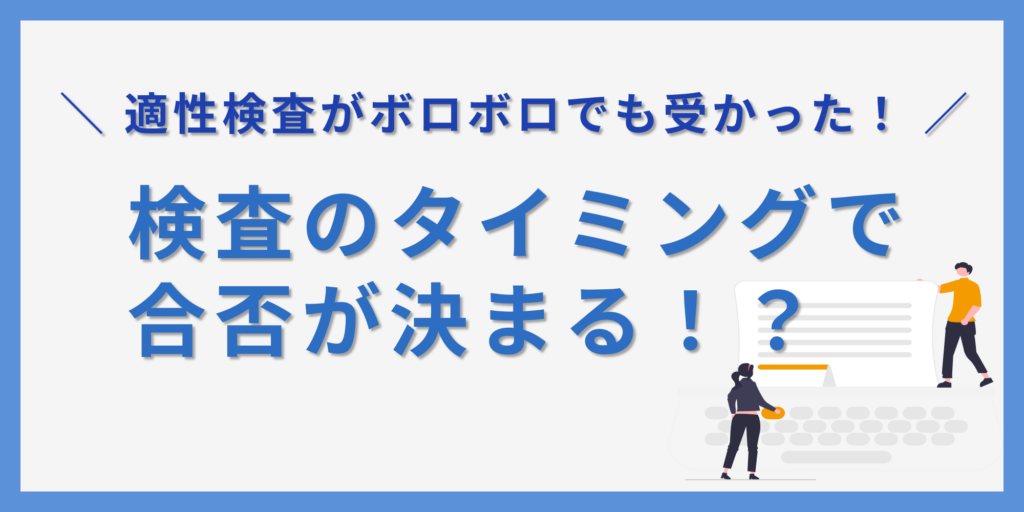 適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?
適性検査がボロボロでも受かった人はいる?検査の実施タイミングに秘密が!?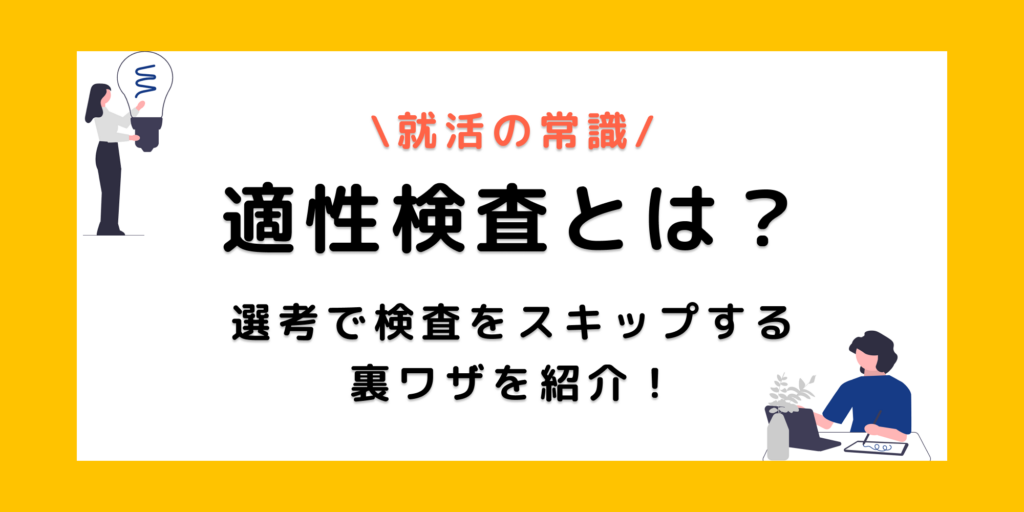 就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!
就活でよく聞く適性検査とは?検査をスキップする4つの裏ワザを紹介!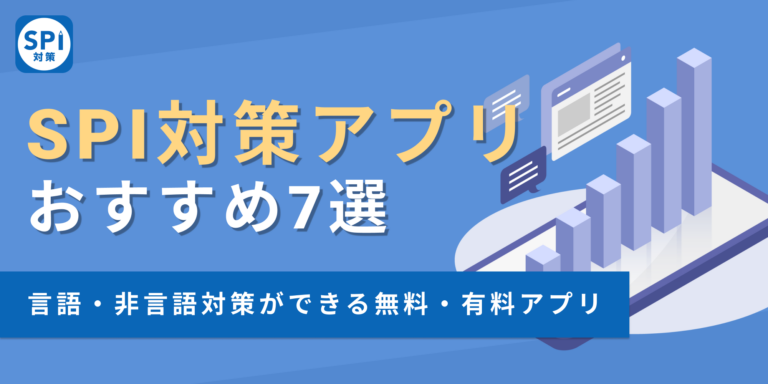 【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ
【SPI対策アプリ】言語・非言語対策におすすめの無料・有料アプリ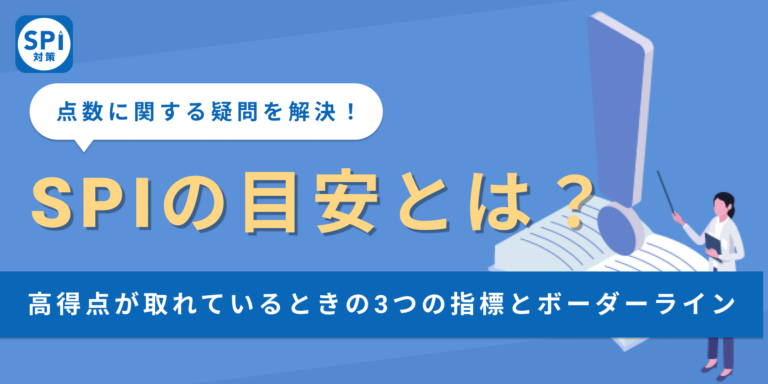 SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン
SPIの目安とは?高得点が取れているときの3つの指標とボーダーライン 【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点
【SPI対策本おすすめ16選】26卒必見!対策本の選び方と注意点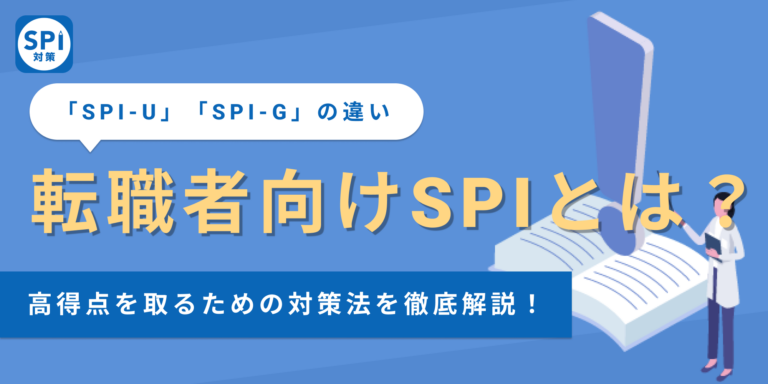 【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説!
【転職者向けSPIとは?】新卒向けSPIとの違いから対策法まで解説! 【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説!
【適性検査GABとは?】出題傾向から対策法まで例題を用いて徹底解説! 【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
【SPIテストセンター攻略法】特徴や問題例、対策法まで徹底解説!
 SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要?
SPIで英語があるかないか判別する3つの方法!ない場合でも英語力は必要? SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説
SPIの受検方法は?主流のWebテストとテストセンターの流れを解説 【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは?
【SPI英語問題集】就活生の定番おすすめ本3選!高得点を狙う勉強法とは? SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック
SPI対策を1ヶ月で仕上げる勉強法!正答率を上げる必須テクニック 【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法
【無料あり】SPI模試おすすめ5選!オンライン受検の流れと結果の活用法 【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説
【SPI英語の頻出単語200選】暗記中心で高得点を取る対策法を解説